M&Aとは?意味や動向とM&Aを行う目的・メリットなどをわかりやすく解説!
2025年2月28日更新業種別M&A
清酒酒造・日本酒業界のM&A・事業承継の動向!事例・案件・相談先も紹介
本記事では、清酒酒造・日本酒業界のM&Aの最新動向を紹介します。清酒酒造・日本酒業界では、今後もM&Aが増加する見込みです。M&Aを成功に導くべく、メリットやスキーム、事業規模を整理しつつ事例を分析することが大切です。M&Aを検討中の方は必見です。
目次
清酒酒造・日本酒業界を取り巻く環境
清酒酒造・日本酒業界は、日本酒の酒造や販売事業を行う業界です。そんな清酒酒造・日本酒業界では、経営難や後継者不足といった問題に悩まされている経営者が多いです。こうした状況を受けて、最近ではM&A件数が増加しています。
M&Aとは、他社に経営を引き継いでもらう方法です。M&Aによって後継者不足問題の解決や経営基盤の安定化が実現できれば、事業を継続できます。ここからはそんな清酒酒造・日本酒業界の現状とM&A動向について、詳しく解説します。
清酒酒造・日本酒業界の現状
清酒酒造・日本酒業界において欠かせない商品である日本酒は、2013年に和食がユネスコ無形文化遺産に登録されたことも相まって、世界各地で人気を得ています。しかし近年では売上減少の傾向が見られ、酒造メーカーは年々減少している側面もあります。
そんな清酒酒造・日本酒業界の現状としては、以下3つの特徴が見られます。
- 酒造メーカー・酒蔵の数が減少傾向にある
- 国内市場は縮小傾向にある
- 9割以上を中小企業・小規模事業者が占めている
これら3つの特徴について、それぞれ詳しく解説していきます。
酒造メーカー・酒蔵の数が減少傾向にある
近年、日本酒業界が活気づいているように見える一方で、実際には日本酒メーカーの数は減少し続けています。日本酒の消費量が最も多かったのは1975年で、当時の製造免許場の数は3,229場に達していました。
しかし、2022年時点では約1,536場まで減少しており、ピーク時からおよそ半数にまで減っています。このように、日本酒業界は厳しい状況が続いているのが現状です。
国内市場は縮小傾向にある
少子高齢化や人口減少といった人口動態の変化に加え、消費者の低価格志向、ライフスタイルの多様化、嗜好の変化などの影響により、国内市場は全体的に縮小傾向にあります。
酒類ごとの課税数量の構成比率を見てみると、その内訳が大きく変化していることがわかります。特にビールの課税数量が大幅に減少しており、これはビールから低価格帯の発泡酒やチューハイなどの「新ジャンル飲料」への消費シフトが一因と考えられます。
9割以上を中小企業・小規模事業者が占めている
清酒製造業者は酒類業界の中でも最も多いものの、市場全体の売上規模は決して大きくありません。
その背景には、日本の高齢化に伴う日本酒の消費量減少があり、市場の縮小が続いています。
その結果、業界の9割以上を占める中小企業や小規模事業者は経営の厳しさに直面しており、事業の存続や成長が課題となっています。
国外での需要が高まっている
世界の清酒市場は2018年に約73億5,000万米ドルと評価され、2026年には104億7,000万米ドルに達すると予測されています。
日本酒は、米を発酵させて作られる日本独自のアルコール飲料であり、一部の国では「ライスワイン」とも呼ばれています。
甘みのある風味と淡い色合いが特徴で、「サキ(Sake)」の名称でも広く認知されています。
近年、日本酒は海外市場で急速に認知度を高めており、特に西洋諸国や東南アジア諸国への輸出量が大幅に増加しています。
世界的には日本酒に関する知識の普及や、専門店・レストランでの取り扱い拡大が進んでいることから、今後も海外市場の成長が期待されています。
清酒酒造・日本酒業界が抱える課題
清酒酒造・日本酒業界が抱える課題を3つご紹介します。
設備の老朽化
多くの酒蔵は長い歴史を持っていますが、その分、設備の老朽化が進んでいる場合が多いです。新しい設備への更新には多額の投資が必要であるため、十分な資金が確保できず、設備を更新できない酒蔵も少なくありません。
ブランディングの難しさ
日本酒業界では、問屋との密接な関係性や伝統の維持が求められるため、新たなブランディングを行うことが難しいとされています。このため、販売量の低迷から抜け出せない酒蔵も多いのが現状です。
製造時期の制約
日本酒の味は、製造時の「気温」に大きく左右されます。そのため、主に気温が低い冬に製造が集中し、夏場の製造は行わない、または冷蔵設備を用いて製造する場合が一般的です。
このような季節による製造の偏りにより、安定した売上を通年で確保するのが難しくなります。また、原料となるお米の仕入れに伴うキャッシュフローの問題や、季節ごとに必要な人員数が変動することによる雇用問題にも直面しています。
清酒酒造・日本酒業界のM&A・事業承継の最新動向3選
これまでの紹介した現状を受けて、清酒酒造・日本酒業界におけるM&Aでは、以下のような動向が見られます。
- 業界内・異業種問わずM&A件数が増加している
- 規制と許認可の課題
- M&Aのマッチングに関する課題
これらの動向について、それぞれ詳しく解説していきます。
①業界内・異業種問わずM&A件数が増加している
清酒酒造や日本酒業界におけるM&Aの件数は増加しています。現在、多くの日本酒メーカーや酒蔵が、経営難や財政状況の悪化という深刻な課題に直面しています。
このような状況を打開し、業界の再編を図る目的で、大手企業や異業種の企業による清酒酒造や日本酒関連会社の買収が活発化しています。これにより、業界全体の構造転換が進められているのです。
②規制と許認可の課題
酒造業界は、多くの法律や規制を遵守しながら事業を運営する必要がある業界です。M&Aにおいても同様に、さまざまな留意点が存在します。特に酒税法に基づく酒類製造免許の取得は規制が厳しく、新たに許認可を取得しようとする法人や個人にとって大きな障壁となることが多いです。そのため、M&Aを活用して許認可を引き継ぐ方法が注目されています。
特に日本酒製造においては、新たに許認可を取得することが難しいため、既存の酒蔵をM&Aで引き継ぐ事例が増えています。ただし、日本酒製造は伝統や地域社会との関係が深いため、M&Aを進める際には地域との調和や伝統の尊重といった点にも十分に配慮する必要があります。
③M&Aのマッチングに関する課題
日本酒を製造する酒蔵は、設備の更新やブランディングに成功しても、一年を通じて安定した供給を維持することが難しい現状があります。さらに、設備の老朽化によって多額の設備投資が必要になり、経営が厳しくなるケースも少なくありません。
また、後継者不足が原因で存続の危機に直面している酒蔵も多く、これらの課題が業界全体の問題となっています。そのため、酒造業界ではM&Aが効果的な解決手段とされています。ただし、M&Aのマッチング(相手探し)を進める際には高度な専門知識が求められる上、多くの留意点が存在します。
仮に慢性的な赤字や債務超過の状態であっても、事業再生の可能性があります。その場合、スポンサーとして支援を申し出る法人も少なくありません。今後はM&Aの積極的な活用により、日本の伝統である日本酒製造が持続し、後世に受け継がれていくことが期待されます。
清酒酒造・日本酒業界M&A・事業承継の買収メリット
清酒酒造・日本酒業界の会社をM&Aで買収するメリットは、以下のとおりです。
- 事業規模・事業エリアの拡大
- 競争力の強化
- 顧客・取引先・ノウハウ・経験・設備の獲得
- 杜氏(酒蔵の最高製造責任者)・従業員の確保
- 相互的なサポートの実現
- 清酒酒造・日本酒業界への新規参入
上記のように、清酒酒造・日本酒業界をM&Aで買収すると様々なメリットが期待できるため、買収に名乗りを上げる企業の規模や種類は多種多様です。前述のように異業種の企業が、清酒酒造・日本酒業界への参入を目的として買収を実施するケースも増えています。
同業者が買収を行うケースであれば、事業規模や事業エリアの拡大、競争力の強化をはじめ、様々なメリットを享受できます。同業者同士のM&Aは、双方のノウハウや経験、設備などを活用することで、相互に支え合うという側面が強くなります。
清酒酒造・日本酒業界M&A・事業承継の売却メリット
清酒酒造・日本酒業界の会社をM&Aで売却するメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 後継者不足問題の解決
- 経営基盤の安定化
- 創業者利益(売却利益)の獲得
- 個人保証・担保の解消
- 従業員の雇用維持
M&Aによる会社の売却では、後継者不足問題の解決・経営基盤の安定化・創業者利益の獲得・個人保証や担保の解消・従業員の雇用の維持といった様々なメリットが得られます。これは清酒酒造・日本酒業界における売却であっても、例外ではありません。
とくに清酒酒造・日本酒業界では、売却目的として後継者不足問題の解決や経営基盤の安定化が挙げられるケースが多いです。これは、清酒酒造・日本酒業界ならではの解決すべき問題と重なっています。
希望どおりの売却を成功させるには、買い手にとって魅力になる部分をしっかりとアピールすることが大切です。日本酒やその酒蔵・日本酒メーカーなどに魅力を感じてもらえれば、それだけ買い手に名乗り出る企業が増えます。
そして事業を売却して経営を任せる以上、信頼できる相手企業を見つけなければなりません。経済効果の高いM&Aを実現するためにも、売却相手の事業内容を分析した上で、幅広い観点から最適なM&Aを検討する必要があります。
清酒酒造・日本酒業界のM&A・事業承継案件例2選
弊社M&A総合研究所が取り扱っている清酒酒造・日本酒業界のM&A・事業承継案件例をご紹介します。
①【高認知度×業歴300年以上】九州の酒類製造業
焼酎、清酒に加え、リキュールの製造免許も保有しており、幅広い商品開発/販売が可能です。全国的な知名度がある自社商品を既に保有しており、自社で商標も保有しています。
| エリア | 九州・沖縄 |
| 売上高 | 1億円〜2.5億円 |
| 譲渡希望額 | 5000万円〜1億円 |
| 譲渡理由 | 後継者不在(事業承継) |
②【中部地方 × 酒蔵】200年超の歴史ある酒造会社
中部地方にて、200年超の歴史ある酒蔵運営を手掛ける企業です。希少性の高い全酒類卸売、一般酒類小売り免許を保有しています。え
| エリア | 中部・北陸 |
| 売上高 | 1000万円〜5000万円 |
| 譲渡希望額 | 〜1000万円 |
| 譲渡理由 | 財務的理由、戦略の見直し |
③【関東地方×酒蔵】約300年の歴史ある酒造会社
関東地方にて、創業約300年の歴史ある酒蔵運営を手掛ける企業です。
旧酒造免許・旧酒販免許を保有しています。300年近くの歴史を誇り、長年に渡って手作りの日本酒を製造しています。
営業利益は赤字となっていますが、販路拡大を行うことでPLは改善される見通しです。。
| エリア | 中部・北陸 |
| 売上高 | 1000万円〜5000万円 |
| 譲渡希望額 | 応相談 |
| 譲渡理由 | 後継者不在(事業承継)、戦略の見直し |
清酒酒造・日本酒業界のM&A・事業承継の成功事例4選
これまで解説した業界の現状やM&A動向を踏まえ、ここではM&Aで清酒酒造・日本酒業界における経営難や後継者不在などの問題解決に成功した事例や、業種や規模の異なる企業が清酒酒造・日本酒業界でのM&A買収に成功した事例をまとめて紹介していきます。
①夢酒蔵と若宮酒造のM&A・事業承継
2024年11月28日、夢酒蔵(京都府京都市)は、若宮酒造(京都府綾部市)の発行済株式98.8%を取得しました。夢酒蔵は酒蔵に特化したマネジメント・サポートを提供する企業で、若宮酒造は大正9年創業の老舗酒蔵で「綾小町」などを製造しています。
若宮酒造は後継者不在により事業継続が危ぶまれていましたが、2024年9月から夢酒蔵の経営支援を受け、酒造技術者の派遣・指導のもとで酒造を再開しています。今回の株式取得により、夢酒蔵が若宮酒造の事業を本格的に引き継ぐこととなりました。
②マルコメと千代の亀酒造のM&A・事業承継
2024年10月1日、マルコメ(長野県長野市)は、千代の亀酒造(愛媛県喜多郡)の全株式を取得し、子会社化したと発表しました。株式取得は2024年6月24日付で実施され、同日に開催された株主総会と取締役会で、マルコメ取締役常務執行役員の小川浩司氏が代表取締役社長に就任しました。
千代の亀酒造は江戸時代から清酒を製造する歴史ある酒蔵で、マルコメはその販路拡大を目的として全株式を取得しました。マルコメは味噌や糀、大豆製品の製造販売を主力とし、国内外で事業を展開しています。
③日本酒類販売と秋田県酒類卸のM&A・事業承継
日本酒類販売は2023年6月、秋田県酒類卸の発行済株式を取得しました。
日本酒類販売は、酒類、清涼飲料水、食料品の原材料売買、不動産賃貸などを行っています。対象会社の秋田県酒類卸は、秋田県内最大の酒類卸会社です。秋田県全域を対象として、酒類や清涼飲料水の他、嗜好飲料や調味料および食料品の卸売を行う会社です。
今回のM&Aにより、相互機能の補完と関係強化を図り、地域と全国をつなぐ食文化の発展を目指します。
④RiceWineが4社の投資引受先へ第三者割当増資を実施
RiceWineは2022年9月、4社の投資引受先から、第三者割当増資による総額3億円の資金調達を実施した。
引受先はDIMENSION、ロッテベンチャーズ・ジャパン、横浜キャピタル、三菱UFJキャピタルです。
RiceWineは、全国の酒蔵と提携し、特定名称酒へ特化したオリジナルブランドを製造しており、日本酒ブランド「HINEMOS(ひねもす)」を展開しています。自社ECやポップアップを通じた消費者への直接販売など、企業独自の手法を展開しています。
今回の第三者割当増資により、RiceWineは製造・販売強化やブランドの世界展開を目指すための人材採用を積極的に行う予定です。
清酒酒造・日本酒業界M&A・事業承継の相場と費用
近年の清酒酒造・日本酒業界のM&Aは、大手企業・異業種の企業・中小企業・ベンチャー企業による買収まで、事例のタイプが多様化しています。M&Aによる売買価格の相場は、数百万円から数千万円程度が目安ですが、相場と費用を具体的に判断することは困難です。
しかし相場と費用を判断しにくいとはいえ、相場・費用を全く考慮しないわけにはいきません。ある程度の目安をつけておかないと、想定外の費用が発生してしまうおそれがあります。類似事例をこまめにチェックしておけば、おおよその見当をつけることができます。
つまりM&Aの相場と費用については、自社と類似する規模の会社が実施したM&A事例を徹底的に分析することが大切です。具体的には、M&Aの目的・M&Aの当事会社の規模・対象事業の規模・会社の業績・従業員数・M&A手法などをチェックし、類似事例を徹底的にチェックします。
相場と費用をより詳しく把握したいなら、M&A仲介会社・M&AアドバイザリーなどのM&A専門家に相談することをおすすめします。清酒酒造・日本酒業界におけるM&Aの成約実績が豊富な業者であれば、相場や費用に関する詳細な情報を教えてもらえます。
清酒酒造・日本酒業界に詳しいM&A仲介会社に悩んだら、M&A総合研究所にご相談ください。M&A仲介会社であるM&A総合研究所には、M&Aに関する専門知識や経験が豊富なアドバイザーが在籍しており、M&Aをフルサポートいたします。
スピーディーなサポートを実践しており、一般的にM&Aは半年から1年程度は時間を要しますが、M&A総合研究所は、最短3ヶ月という短期間での成約実績があります。
料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。相談料は無料となっておりますので、清酒酒造・日本酒業界でのM&Aをご検討中でしたら、お気軽にご相談ください。
清酒酒造・日本酒業界のM&A・事業承継時におすすめの相談先3選
清酒酒造・日本酒業界のM&A・事業承継時におすすめの相談先をご紹介します。
①金融機関
金融機関である銀行や証券会社は、豊富な顧客ネットワークと情報収集力を持っており、M&Aの相談先として適しています。特に、日頃から取引のある銀行に相談すれば、自社の経営状況を十分に理解しているため、スムーズに話が進むという利点があります。
ただし、金融機関のM&A支援は主に大企業を対象とすることが多く、中小企業には対応していない場合もあります。また、手数料が高額に設定されているケースもあるため、コスト負担が発生する可能性についても注意が必要です。
信頼できる金融機関がある場合、M&Aの相談先として検討する価値は十分にあります。ただし、提供されるサービスが自社のニーズに合っているかを慎重に確認することが重要です。
②公的機関
零細・中小企業を対象とした事業承継の相談窓口として、「事業承継・引継ぎ支援センター」が設置されています。このセンターは国が運営しており、信頼性が高く、安心して相談できる点が大きな特徴です。
しかし、センターの認知度がまだ十分に広がっておらず、利用者が限られているため、希望条件に合うマッチングが難しい場合もあります。そのため、他の専門機関やM&A仲介会社と併用し、セカンドオピニオンとして活用するのが効果的です。このように多方面から支援を受けることで、より適切で実用的なサポートが期待できます。
③M&A仲介会社
M&A仲介会社は、豊富な経験と専門知識を持ち、多くの案件を手掛けてきた実績があるため、信頼性の高い相談先と言えます。相談者の状況に似たケースへの対応力もあり、的確な支援が期待できます。
ただし、仲介会社は買い手と売り手の双方をサポートする中立的な立場を取るため、一方の利益だけを優先することはありません。そのため、自社の利益を最優先に考えたアドバイスが得られない場合がある点には注意が必要です。
M&Aプロセスを計画段階から契約締結、実行まで一貫してサポートしてほしい場合には、M&A仲介会社は特に有力な選択肢となります。
清酒酒造・日本酒業界のM&A・事業承継まとめ
日本酒は国内だけでなく海外でも人気がありますが、売上の減少傾向や酒造メーカーの減少といった側面もあります。また清酒酒造・日本酒業界は中小企業が多く、経営難や後継者不足といった問題が発生しています。こうした状況のなかで、やむを得ず廃業をしてしまうケースも見られます。
廃業は手間やコストがかかるほか、取引先や顧客、従業員などにも影響を与えてしまいます。これまで培ってきた伝統が終わってしまうことにもなります。近年の清酒酒造・日本酒業界ではM&Aを活用して、後継者不足問題の解決や経営基盤の安定化を実現することが可能です。
M&Aによって廃業の危機から脱し、事業を継続することができるのです。事業の継続は伝統を守ることでもあります。中小企業が多い清酒酒造・日本酒業界では、今後もさらにM&Aが加速する見込みです。
M&Aを成功に導くためにも、M&Aの目的・スキーム・会社や事業の規模などを整理した上で、類似事例を徹底的に分析しながら、様々な視点から総合的に判断することが大切です。
M&A・事業承継のご相談なら24時間対応のM&A総合研究所
M&A・事業承継のご相談は成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A総合研究所にご相談ください。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴
- 譲渡企業様完全成功報酬!
- 最短43日、平均7.2ヶ月のスピード成約(2025年9月期実績)
- 上場の信頼感と豊富な実績
- 譲受企業専門部署による強いマッチング力
M&A総合研究所は、M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。
また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。
相談も無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたにおすすめの記事

M&Aとは?意味や動向とM&Aを行う目的・メリットなどをわかりやすく解説!
近年はM&Aが経営戦略として注目されており、実施件数も年々増加しています。M&Aの特徴はそれぞれ異なるため、自社の目的にあった手法を選択することが重要です。この記事では、M&am...

買収とは?用語の意味やメリット・デメリット、M&A手法、買収防衛策も解説
買収には、友好的買収と敵対的買収とがあります。また、買収に用いられるM&Aスキーム(手法)は実にさまざまです。本記事では、買収の意味や行われる目的、メリット・デメリット、買収のプロセスや...

現在価値とは?計算方法や割引率、キャッシュフローとの関係をわかりやすく解説
M&Aや投資の意思決定するうえでは、今後得られる利益の現時点での価値を表す指標「現在価値」についての理解が必要です。今の記事では、現在価値とはどのようなものか、計算方法や割引率、キャッシ...

株価算定方法とは?非上場企業の活用場面、必要費用、手続きの流れを解説
株価算定方法は多くの種類があり、それぞれ活用する場面や特徴が異なります。この記事では、マーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチといった株価算定方法の種類、株価算定のプロセス、株...

赤字になったら会社はつぶれる?赤字経営のメリット・デメリット、赤字決算について解説
法人税を節税するために、赤字経営をわざと行う会社も存在します。しかし、会社は赤字だからといって、必ず倒産する訳ではありません。逆に黒字でも倒産するリスクがあります。赤字経営のメリット・デメリット...
関連する記事

百貨店業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!
本コラムでは百貨店関連のM&Aについてまとめました。主な内容として、百貨店業界の動向、百貨店のM&Aによる売却・譲渡で得られるメリットやM&Aの流れ、百貨店をM&...

ペット関連の業界動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!
本コラムは、ペット関連業界のM&Aについて特に売却側の視点に立ってまとめました。主な内容は、ペット関連業界の動向、ペット関連会社をM&Aで売却・譲渡する際の流れやメリット・注意点...

病院の業界動向とM&Aのメリット!売却・買収事例や流れと注意点も解説!
病院は一般の株式会社とは違うため、M&Aを実施する際もその点に留意が必要です。本コラムでは、病院の業界動向、M&Aにおける注意点、売却側・買収側それぞれのM&Aメリット、...

酒蔵業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例や流れと注意点も解説!
酒造業界では、国内市場の縮小や海外輸出への対応、後継者問題や人手不足問題を抱えている酒蔵が増加しており、その解決策としてM&Aが注目されています。この記事では、酒蔵業界でのM&A...

税理士事務所業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例や流れと注意点も解説!
税理士事務所業界では経営者の高齢化などにより事業承継の必要性が高まっていて、その打開策の一つとしてM&Aを検討するところが増加しています。この記事では、税理士事務所業界におけるM&...

トラック物流業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例や流れと注意点も解説!
トラック物流業界では、後継者問題や人手不足問題などを理由としたM&Aが活発化しています。この記事では、トラック物流業界でM&Aを実施するメリットやM&Aを行うときの注意点...

インドネシアのM&A動向と特徴を解説!海外での企業買収のメリットと注意点とは?
平均年齢が若く今後も人口増加が見込めるインドネシアはM&A市場でも魅力的な国の一つです。この記事では、インドネシアでM&Aを実行する上で理解しておきたい、同国の経済動向やM&am...
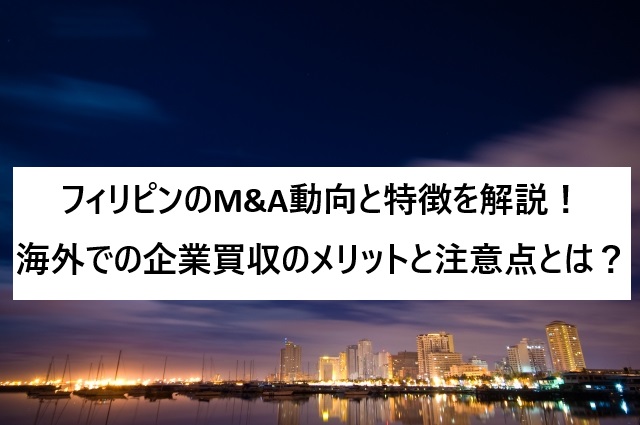
フィリピンのM&A動向と特徴を解説!海外での企業買収のメリットと注意点とは?
海外進出をM&Aで図りたいと考えているのなら、親日国であるフィリピン企業の買収がいいといわれています。この記事では、フィリピンでのM&Aの動向とメリット、日本とは異なる点があるM...

工場業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例や流れと注意点も解説!
工場業界では、人手不足や後継者問題などの理由で、M&Aでの売却を検討する経営者が増加しています。工場のM&Aによる売却はどのような点を注意するべきなのでしょうか。この記事では、工...
























株式会社日本M&Aセンターにて製造業を中心に、建設業・サービス業・情報通信業・運輸業・不動産業・卸売業等で20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、アドバイザーを統括。ディールマネージャーとして全案件に携わる。