M&Aとは?目的・メリットから手法、最新動向までわかりやすく解説
2022年6月6日更新業種別M&A
訪問看護ステーションのM&A・事業承継!動向・流れ・注意点、相場を解説【事例付き】
高齢化が進む日本では、訪問看護ステーションの需要は今後も増加すると考えられており、それに伴う事業規模拡大や新規参入を目的としたM&Aや事業承継も増加すると見込まれています。この記事では、訪問看護ステーションのM&Aや事業承継について、動向や注意点を解説します。
目次
訪問看護ステーションのM&A・事業承継

訪問看護ステーションは需要が高くなっていますが、開設するための人数要件は看護職員の2.5人配置(常勤換算)と少なく、事務所・移動用の車・最低限の備品があれば基準を満たすことができます。
参入障壁の低さから小規模で開設するケースも多いですが、看護職員に該当する看護師や保健師などを十分な人数確保するのが難しいという問題もあります。そのような背景から、同業間でのM&Aや事業承継が行われるケースも増加しています。
訪問看護ステーションとは
訪問看護ステーションとは、保健師・看護師・理学療法士など訪問看護を行う従事者が所属している事業所を指し、職員は訪問看護ステーションから利用者宅や施設を訪問し、状態観察やケアなどを行います。
訪問看護サービスを利用するためには「訪問看護指示書」が必要であり、これは利用者の主治医が判断して作成します。年齢による利用制限はないため、小さな子どもから高齢者まで利用することができます。
訪問看護ステーションの現在
人生の最期を自分らしく過ごしたい、親しんだ場所で穏やかに最後を迎えたいと考える人も多く、その希望が実現するように介護や生活支援サービスなどが一体となって、地域包括ケアシステムの構築が進められています。
このような背景からも訪問看護ステーションの必要性は年々高くなっており、参入障壁が低さも相まって訪問看護ステーション事業者が増加しています。
訪問看護ステーションの今後
訪問看護ステーションは、将来的にM&Aの件数が増加すると予想されています。訪問看護ステーション事業は参入障壁が低いため事業者数は増加していますが、十分な人数の看護師や保健師など確保することが難しく、1事業所当たりの従業員数も少ない傾向がみられます。
これでは利用者増加に対応できないだけでなく、ほかの訪問看護ステーション事業内と差別化を図ることも難しくなり、訪問看護ステーションの経営悪化にもつながりかねません。
もし廃業となれば、訪問看護ステーションの利用者へのサービスを急に止めることはできないため、徐々に縮小していかなければならないなどの問題もあります。
M&Aはそのような問題を解決するための有効な手段であり、職員や看護師などの人材確保によって安定した事業継続が見込めるだけでなく、訪問介護ステーション利用者へのサービスも継続して提供することができます。
M&Aとは
M&Aとは会社の買収や合併のことを指し、近年では経営課題の解決や成長戦略として広く活用されています。M&Aには多くのスキームがありますが、多く用いられるものに株式譲渡と事業譲渡があります。
株式譲渡
株式譲渡は、自社の株式を相手先へ譲渡することで経営権を移行させるM&A手法です。株式譲渡のメリットは手続きが簡便であること、自社の従業員や関係先に大きな影響を与えないことです。
株式譲渡に必要な手続きは、取引完了後の株主名簿の書き換えだけなので、事業譲渡や合併などほかのM&A手法に比べると非常に簡単です。
また、株式譲渡では、権利や義務、資産や負債、雇用契約なども譲受側の会社へそのまま引き継がれるため、周囲への影響や混乱も少なくて済みます。
事業譲渡
事業譲渡は、自社の事業単位(一部または全部)について売買を行うM&A手法です。大きな特徴は、譲渡あるいは譲受する対象を選択できることです。
前述の株式譲渡は包括承継する手法なので、負債や簿外債務など経営上のリスクが高いものも含めて引き継ぐことになります。
事業譲渡では、譲渡対象となるものを細かく決めることができるため、譲受側にとっては負債や不要な資産を引き継がなくてよいというメリットがあります。譲渡側も自社にとって不要な事業を切り離し、主軸となる事業に専念できるなどのメリットがあります。
ただし、事業譲渡は個別承継であるため、従業員や関係先との契約などについては、相手の同意を得たうえで改めて契約しなければなりません。手続きに手間と時間を要することは、事業譲渡のデメリットの1つともいえるでしょう。
事業承継とは
事業承継とは、自社が現在行っている事業を後継者に引き継ぐことをいいます。事業承継は後継者として誰を据えるかによって、以下の3つに分類することができます。
【事業承継の種類】
- 親族内事業承継
- 親族外事業承継
- M&Aによる事業承継
親族内事業承継
親族内事業承継とは、現経営者の子どもなど親族を後継者として事業を引き継ぐ方法です。現経営者の親族を後継者とするため、早い段階から準備ができ、育成時間を十分にとることも可能です。
また、生前贈与を活用して株式や事業用資産を少しずつ後継者へ移行することもできます。かつての日本では、経営者の子どもが事業を引き継ぐケースが一般的でした。
しかし、経営者が子どもの意思を尊重したり、自社の将来を考えて引き継がないという選択するケースも増えており、親族内承継は段々とその割合が減ってきています。
親族外事業承継
親族外事業承継は、現経営者の親族以外を後継者として事業を引き継ぐ方法です。後継者となるのは、自社の役員や従業員などが多く、優秀な人材を選べることがメリットです。
また、自社の役員などであれば経営理念や自社の状態も把握しているため、スムーズな事業承継が可能です。
しかし、親族内承継の場合は自社の株式などは有償譲渡するのが一般的であるため、後継者資金力がネックとなることも多いです。また、経営者の親族から理解を得られない場合は、トラブルになるケースもあります。
M&Aによる事業承継
M&Aによる事業承継は、M&A仲介会社などを利用して承継先を探して事業を引き継ぐ方法です。M&Aによる事業承継は幅広いなかから承継先を探すことができるので、適任者がみつかる可能性が高くなります。
親族内承継や親族外事業承継であれば後継者を育成する時間が必要ですが、M&Aによる事業承継であれば、その時間も手間も不要になります。
また、現経営者は譲渡・売却益を得ることができるもの、M&Aによる事業承継のメリットといえるでしょう。
訪問看護ステーションのM&A・事業承継動向

訪問看護ステーションのM&A・事業承継の件数は増加すると見込まれており、その理由としては以下の2つがあります。
- 訪問看護ステーションの数が多く職員が不足している
- 要介護度が高い状態の高齢者が増加している
記事冒頭で述べたように、訪問看護ステーションを開設するための人数要件は看護職員が常勤換算で2.5人となっています。
初期段階の設備投資も少なくて済むため、小規模で事務所を開設するケースも多く、次々に事業所が開設されています。
しかし、看護職員である看護師などは病院などの医療機関でも不足している状態であり、訪問看護ステーションでも十分な人員確保が難しくなっています。
また、高齢化の進む日本では要介護度の高い高齢者も増加しています。訪問看護ステーションの利用者が増えても、人員不足などの理由によって自社のみでは対応できないケースもでてくる可能性があります。
このような背景から、今後は人員確保を目的とする訪問看護ステーションのM&A・事業承継が増加すると予測されます。
訪問看護ステーションのM&A・事業承継の流れ

訪問看護ステーションのM&A・事業承継は、どのような流れで行われるのでしょうか。この章では、訪問看護ステーションのM&A・事業承継の一般的な流れについて解説します。
【訪問看護ステーションのM&A・事業承継の流れ】
- M&A・事業承継の専門家に相談
- M&A・事業承継先の選定及び、交渉開始
- M&A・事業承継先のトップと面談
- M&A・事業承継先との基本合意書の締結
- M&A・事業承継先によるデューデリジェンスの実施
- 最終契約書を締結する
- クロージング
1.M&A・事業承継の専門家に相談
訪問看護ステーションのM&A・事業承継を行う際は、M&A仲介会社など専門家に相談しながら進めていくのが一般的です。
訪問看護ステーションのM&Aや事業承継の成功確率を上げるためには、訪問看護ステーションのM&A動向を把握し、計画的かつ戦略的に進める必要があり、専門家のサポートは不可欠ともいえるものです。
M&A仲介会社などの専門家にはそれぞれ得意とする規模や分野があるので、HPなどを確認して自社に合ったところを選ぶようにしましょう。
2.M&A・事業承継先の選定及び、交渉開始
サポートを依頼する専門家が決まったら、次はM&A・事業承継先の選定を行います。M&A仲介会社の場合、自社の希望条件をM&Aアドバイザーに伝えると候補先を数社リストアップしてくれるので、そのなかから選びます。
交渉希望先が決まったらM&A仲介会社を通じて打診をし、相手先の意思を確認できたら具体的なM&A・事業承継の交渉へと移ります。
3.M&A・事業承継先のトップと面談
訪問看護ステーションのM&A・事業承継の交渉がある程度進んだ段階で、譲渡側・譲受側のトップが直接顔を合わせる場が設けられます。
トップ同士の面談は価格などの交渉を行うというよりも、互いの企業理念を確認したり人間性などを確認する意味合いが強く、本当にM&A・事業承継先の相手としてふさわしいのかを見極めます。
4.M&A・事業承継先との基本合意書の締結
次は、譲渡側・譲受側企業間で基本合意書を締結します。基本合意書には、ここまで交渉した内容に互いに合意したことを示すものであり、これ自体に法的拘束力はありません。
しかし、独占交渉権などの一部内容については、法的拘束力を持たせるケースが多いです。
訪問看護ステーションのM&A・事業承継で利用するスキームや譲渡価格についても記載されますが、以降実施されるデューデリジェンスの結果などにより、条件が変更される可能性もあります。
5.M&A・事業承継先によるデューデリジェンスの実施
訪問看護ステーションのM&A・事業承継についての基本合意書を締結した後は、譲受側によってデューデリジェンスが実施されます。
デューデリジェンスとは企業監査のことであり、財務面や法務面などのあらゆる側面から譲渡側企業を調査します。
この結果をもとに、訪問看護ステーションのM&Aや事業承継を行っても問題がないか、交渉した取引価格は妥当であるかなどを判断します。
6.最終契約書を締結する
デューデリジェンスを終え、訪問看護ステーションのM&A・事業承継を実施して問題がないと判断されれば、
最終的な条件交渉を行います。
この交渉では、デューデリジェンスの結果を受けて、必要であれば条件の追加や変更などをします。その内容に両社が合意すれば、最終契約書の締結へと進みます。
最終契約書はすべての内容において法的拘束力をもつため、締結後は特別な理由がない限り破棄することはできません。
7.クロージング
クロージングとは、最終契約書の記載内容に基づいて資産の移動や対価なの支払いを行うことです。
クロージングが完了することで、訪問看護ステーションのM&A・事業承継一連の手続きは完了します。
訪問看護ステーションのM&A・事業承継の注意点

訪問看護ステーションのM&A・事業承継を行う際は、いくつか注意すべき点があります。ここでは、重要な2点について解説します。
【訪問看護ステーションのM&A・事業承継の注意点】
- M&A・事業承継の理由は明確にする必要があること
- 職員・看護師が退職するのを防ぐこと
1.M&A・事業承継の理由は明確にする必要がある
1つ目は、訪問看護ステーションのM&A・事業承継のを行う理由を明確にすることです。自社が何を目的としてM&Aや事業承継を行うのかを明確にしておかなければ、一貫した交渉を進めることはできません。
訪問看護ステーションに限らず、M&A・事業承継の交渉では譲渡側・譲受側それぞれ譲歩が必要になります。
従業員の雇用維持を最優先とするのか、少しでも高く売却したいのかは各々ですが、理由を明確にしておくことで、大きな選択を迫られた場合に誤った判断を防ぐことができます。
M&Aや事業承継を行うためには多額の費用がかかるので、もし失敗すれば大きなダメージを受けることにもなりかねません。まずは、なぜM&Aや事業承継を行いたいのか明確にしておきましょう。
2.職員・看護師が退職するのを防ぐ
2つ目の注意点は、訪問看護ステーションの職員・看護師の離職を防ぐことです。訪問看護ステーション事業を行うためには人数要件満たしているだけでなく、サービスを提供するための職員や看護師が不可欠です。
特に、ベテランの職員・看護師はノウハウや経験なども豊富にもっているため、M&Aや事業承継における企業価値を高める要素にもなります。
自社がM&Aや事業承継を行うことや以降の処遇なども丁寧に説明するなどして、職員や看護師の退職を防ぐように努める必要があります。
訪問看護ステーションのM&A・事業承継の相場

訪問看護ステーションのM&A・事業承継を検討する場合、どの程度で売却できるのかは当然気になるものです。
しかし、M&A・事業承継の相場は対象企業の営業成績や事業規模などでも異なり、最終的には譲渡側・譲受側の交渉によって決定されるため、一概に述べることはできません。
M&A・事業承継の価格は企業価値をもとに決定されるのが一般的であるため、自社の企業価値を算定すれある程度の予測は立てることが可能です。
企業価値の算出方法にはさまざまな種類がありますが、訪問看護ステーションのM&A・事業承継の場合、従業員の依存度が高いという理由から正確な算出が難しい面もあります。
そのため、経験の浅い従業員が多い訪問看護ステーションの場合、歴史ある企業が運営していても低い価格で取引されるケースもあります。
反対に、設立して間もない会社であっても、業界での経験が長い従業員が多ければ高い価格で成立することもあります。
訪問看護ステーションのM&A・事業承継の事例

最後に、実際に行われた訪問看護ステーションのM&A・事業承継の事例を3つ紹介します。
- センコーグループHDによるビーナスの買収
- セントケアHDによるミレニアの子会社化
- メディカルシステムネットワークによるひまわり看護ステーションの買収
1.センコーグループHDによるビーナスの買収
1例目は、2017年に行われたセンコーグループHDによるビーナスの買収です。センコーグループHDとビーナスは、ともに訪問看護ステーション事業を行っている企業です。
ビーナスは、大阪府内に43か所のデイサービスおよび訪問看護ステーションを運営しており、センコーグループHDは自社が運営している住宅型老人ホームと連携と業容の拡大を目的に当M&Aを実施しています。
| 買収企業 | センコーグループHD |
| 被買収企業 | ビーナス |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 目的 | 現業態との連携と業容の拡大 |
2.セントケアHDによるミレニアの子会社化
2例目は、2017年に行われたセントケアHDによるミレニアの子会社化です。セントケアHDは訪問介護、ミレニアは東京都を中心に訪問看護ステーション事業を行っていました。
セントレアHDはニレニアを傘下とすることで、ノウハウを共有しグループ内のさらなる連携を図るとしています。
| 買収企業 | セントケアHD |
| 被買収企業 | ミレニア |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 目的 | グループ内の連携、ノウハウの共有 |
3.メディカルシステムネットワークによるひまわり看護ステーションの買収
3例目は、2016年に行われたメディカルシステムネットワークによるひまわり看護ステーションの買収です。
メディカルシステムネットワークは調剤薬局事業を、ひまわり看護ステーションは訪問看護ステーション事業を行っていました。
当案件により、メディカルシステムネットワークは、訪問看護ステーション事業に新規参入しています。
| 買収企業 | メディカルシステムネットワーク |
| 被買収企業 | ひまわり看護ステーション |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 目的 | 訪問看護ステーション事業への新規参入 |
訪問看護ステーションのM&A・事業承継の相談先

訪問看護ステーションのM&A・事業承継をよりよい条件で成立させるためには、M&A仲介会社など専門家によるアドバイスやサポートがおすすめです。
M&A総合研究所は、幅広い業界・業種のM&A支援実績を有しておりますので、訪問看護ステーションのM&A・事業承継のサポートもお任せいただけます。
実績・知識ともに豊富なM&Aアドバイザーが担当につき、交渉や契約手続きなどクロージングまでしっかりサポートいたします。
M&A総合研究所の料金体系は、成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。
無料相談は随時お受けしておりますので、お電話またはメールフォームよりお気軽にご連絡ください。
まとめ

訪問看護ステーションの需要は今後さらに高くなると見込まれています。しかし、訪問看護ステーションは開設要件は看護職員の2.5人配置(常勤換算)と少なく、初期費用も他業種に比べると少なくて済みます。
参入障壁の低さから小規模で開設する事務所が増えており、看護職員に該当する看護師や保健師などを十分な人数確保するのが難しくなっています。
その解決手段としてM&Aや事業承継が行われており、今後も増加すると見込まれているため、訪問看護ステーションのM&A・事業承継を検討している場合は動向を注視しておくとよいでしょう。
【訪問看護ステーションのM&A・事業承継動向】
- 訪問看護ステーションの数が多く職員が不足している
- 要介護度が高い状態の高齢者が増加している
- M&A・事業承継の専門家に相談
- M&A・事業承継先の選定及び、交渉開始
- M&A・事業承継先のトップと面談
- M&A・事業承継先との基本合意書の締結
- M&A・事業承継先によるデューデリジェンスの実施
- 最終契約書を締結する
- クロージング
- M&A・事業承継の理由は明確にしておく
- 職員・看護師が退職するのを防ぐ
M&A・事業承継のご相談なら24時間対応のM&A総合研究所
M&A・事業承継のご相談は成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A総合研究所にご相談ください。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴
- 譲渡企業様完全成功報酬!
- 最短43日、平均7.2ヶ月のスピード成約(2025年9月期実績)
- 上場の信頼感と豊富な実績
- 譲受企業専門部署による強いマッチング力
M&A総合研究所は、M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。
また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。
相談も無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたにおすすめの記事

M&Aとは?目的・メリットから手法、最新動向までわかりやすく解説
M&Aは、事業承継や事業拡大の有効な手段として注目されています。しかし、成功には目的や手法の正しい理解が不可欠です。本記事では、M&Aの基礎知識から目的、メリット・デメリット、最...

買収とは?用語の意味やメリット・デメリット、M&A手法、買収防衛策も解説
買収には、友好的買収と敵対的買収とがあります。また、買収に用いられるM&Aスキーム(手法)は実にさまざまです。本記事では、買収の意味や行われる目的、メリット・デメリット、買収のプロセスや...

現在価値とは?計算方法や割引率、キャッシュフローとの関係をわかりやすく解説
M&Aや投資の意思決定するうえでは、今後得られる利益の現時点での価値を表す指標「現在価値」についての理解が必要です。今の記事では、現在価値とはどのようなものか、計算方法や割引率、キャッシ...

株価算定方法とは?非上場企業の活用場面、必要費用、手続きの流れを解説
株価算定方法は多くの種類があり、それぞれ活用する場面や特徴が異なります。この記事では、マーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチといった株価算定方法の種類、株価算定のプロセス、株...

赤字になったら会社はつぶれる?赤字経営のメリット・デメリット、赤字決算について解説
法人税を節税するために、赤字経営をわざと行う会社も存在します。しかし、会社は赤字だからといって、必ず倒産する訳ではありません。逆に黒字でも倒産するリスクがあります。赤字経営のメリット・デメリット...
関連する記事

百貨店業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!
本コラムでは百貨店関連のM&Aについてまとめました。主な内容として、百貨店業界の動向、百貨店のM&Aによる売却・譲渡で得られるメリットやM&Aの流れ、百貨店をM&...

ペット関連の業界動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!
本コラムは、ペット関連業界のM&Aについて特に売却側の視点に立ってまとめました。主な内容は、ペット関連業界の動向、ペット関連会社をM&Aで売却・譲渡する際の流れやメリット・注意点...

病院の業界動向とM&Aのメリット!売却・買収事例や流れと注意点も解説!
病院は一般の株式会社とは違うため、M&Aを実施する際もその点に留意が必要です。本コラムでは、病院の業界動向、M&Aにおける注意点、売却側・買収側それぞれのM&Aメリット、...

酒蔵業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例や流れと注意点も解説!
酒造業界では、国内市場の縮小や海外輸出への対応、後継者問題や人手不足問題を抱えている酒蔵が増加しており、その解決策としてM&Aが注目されています。この記事では、酒蔵業界でのM&A...

税理士事務所業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例や流れと注意点も解説!
税理士事務所業界では経営者の高齢化などにより事業承継の必要性が高まっていて、その打開策の一つとしてM&Aを検討するところが増加しています。この記事では、税理士事務所業界におけるM&...

トラック物流業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例や流れと注意点も解説!
トラック物流業界では、後継者問題や人手不足問題などを理由としたM&Aが活発化しています。この記事では、トラック物流業界でM&Aを実施するメリットやM&Aを行うときの注意点...

インドネシアのM&A動向と特徴を解説!海外での企業買収のメリットと注意点とは?
平均年齢が若く今後も人口増加が見込めるインドネシアはM&A市場でも魅力的な国の一つです。この記事では、インドネシアでM&Aを実行する上で理解しておきたい、同国の経済動向やM&am...
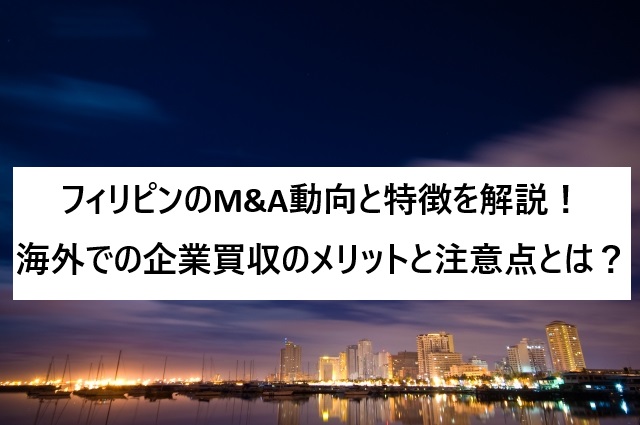
フィリピンのM&A動向と特徴を解説!海外での企業買収のメリットと注意点とは?
海外進出をM&Aで図りたいと考えているのなら、親日国であるフィリピン企業の買収がいいといわれています。この記事では、フィリピンでのM&Aの動向とメリット、日本とは異なる点があるM...

工場業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例や流れと注意点も解説!
工場業界では、人手不足や後継者問題などの理由で、M&Aでの売却を検討する経営者が増加しています。工場のM&Aによる売却はどのような点を注意するべきなのでしょうか。この記事では、工...














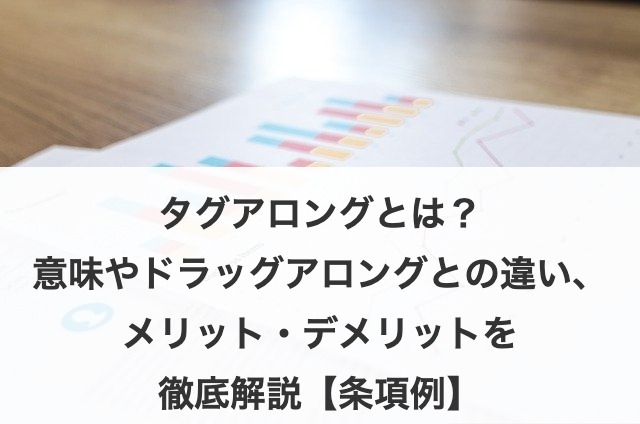










株式会社日本M&Aセンターにて製造業を中心に、建設業・サービス業・情報通信業・運輸業・不動産業・卸売業等で20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、アドバイザーを統括。ディールマネージャーとして全案件に携わる。