M&Aとは?意味や動向とM&Aを行う目的・メリットなどをわかりやすく解説!
2025年11月20日公開業種別M&A
専門学校業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収の流れや注意点も解説!
近年、少子化による生徒数減少などの影響で経営が厳しい専門学校のM&Aによる売却希望が増加しています。専門学校のM&Aは一般企業とは異なる方法で行います。この記事では、専門学校のM&Aについて詳しく解説します。
専門学校の概要
専門学校は、少子化による生徒数の減少と、大学進学率の向上による専門学校に対する志望者数の減少のダブルパンチによって、経営環境が年々厳しくなりつつあるところが増加しています。
そこで、M&Aによって現状を打開する道を探る専門学校の経営者が増えているようですが、専門学校のM&Aは一般企業のM&Aとは手法や流れが大きく異なるので多くの注意が必要です。
この記事では、専門学校業界の近年の動向とM&Aについて詳しくみていきましょう。まずは、専門学校業界の概要です。
専門学校とは
専門学校とは、専修学校の中の専門課程がある学校のことです。
専修学校とは、学校教育法第124条で定められている、修業年限1年以上の学校で、専門課程、高等課程、一般過程のいずれか、もしくは複数が設置されています。
専門学校と呼ぶことができる専門課程は、高校過程の修了者が、職業上必要な専門的な能力を身に着けたり、高度な教養の向上を図ったりするために、組織的な教育を行います。
高等課程は中学校修了者に対して職業教育を行います。通信制高校と連携して、高卒資格を得ながら美容師や看護師などの資格を取得する事ができる高等専修学校もあります。
一般過程は、特に入学資格は定められておらず、学校ごとに入学基準を決めることができるのが特徴です。専修学校の中では、教員資格などの設置基準が最も緩く、大学受験予備校の高卒者コースの「大学受験科」などが該当します。
専門学校は、専修学校のこれらの3つの過程の中で、専門的な技能や職業教育などを実施するための学校のことです。
専門学校のガバナンス体制
専門学校は高い公共性を求められる教育事業であることから、一般企業とは異なるガバナンス体制が取られます。
一般企業では少数の経営陣や株主の意向で経営方針を決定できますが、専門学校では幅広い意見を反映させた運営体制の構築が求められる点に注意が必要です。
学校法人が専門学校の設置者であれば、私立学校法に基づいて、理事会、監事、評議員会の設置が必要です。
学校法人以外の準学校法人が設立する専門学校であれば、特にガバナンス体制が法的に定められている事はありませんが、第三者による学校評価でのガバナンス体制の検証が求められるようになりました。
専門学校では、ガバナンス体制を整えて、社会の人材ニーズを満たすために、どのような教育目標を持って学校運営しているのか、適切な情報公開を行い、生徒を卒業後に送り出す産業界や経済団体からの評価を受けることが重要です。
専門学校の業界動向・現況
専門学校業界の近年の動向はどうなっているのでしょうか。近年の業界動向とM&A動向について解説します。
専門学校に通う生徒数・教員数
専門学校業界の将来性を図る上で、生徒数と教員数の推移は重要なポイントです。
専門学校への入学者数は、最もピークだったのが1992年の36万4,687人です。その後、2006年まで30万人台をキープし続けてきましたが、2007年には28万2,019となり、その後は20万人台が続いています。
2020年の入学者は27万9,586人、2023年の入学者は24万0,626と減少傾向が続いています。
一方、教員数は少人数指導を打ち出す専門学校が増加していることで、生徒数の減少と比較すると増加しています。
専修学校の教員数の推移は、1990年には3万1,773人だったのが、2005年には4万1,776人、2020年には多少減少しましたが4万0,824人と、最も生徒数が多かった1990年代前半と比較しても多いことがわかるでしょう。
生徒数と比較して多くの教員を抱えていることで、人件費が経営を圧迫している専門学校も多いのが現状です。
参考:ナレッジステーション「令和5年度 専門学校への入学状況」 文部科学統計要覧(令和3年版)「12.専修学校 」
許認可を得るのが難しい
教育事業を行う専門学校には、高い公共性が必要なことから、他の業種と比較すると経営の安定性と公平性が厳しく求められます。
そのために、許認可が他の業種と比べるととても難しいことから、専門学校の新設ではなく、すでに運営されている専門学校のM&Aでの買収を望む事例もみられます。
専門学校を含めた専修学校を設置する場合には、学校教育法と専修学校設置基準、各種学校課程規定を満たした上で、所轄庁である都道府県知事の認可が必要です。また、準学校法人も同時に設立する場合にも、都道府県知事の認可を取らなくてはいけません。
また、株式の発行などで資金調達をすることはできずに、寄附行為で設立することも必要です。
制度の規制に則る必要がある
専門学校は、小学校から大学までの一条校ではありませんが、専門的な技能を身につけた社会に有用な人材を輩出するという使命のある教育機関なので、法律が定める規制に則った運営が求められます。
具体的には、専門学校の設置者には学校運営にあたって必要な経済的基盤があること、学校運営に必要な知識や経験を備えていること、社会的な信望のあること、といった要件を満たしていることが必要です。
また、専門学校の設置要件として、1年以上の修業年限、専修学校設置基準以上の授業時間数を確保すること、常時40名以上の生徒がいること、といった基準を満たす必要もあります。
生徒数により収益が左右される
専門学校の収益は生徒数によって大きく変動します。専門学校は、学校法人が運営母体であれば私学助成金の補助を受けられる可能性もありますが、その他の社団法人などが運営している場合には私学助成金はありません。
専門学校の収益は生徒が納める入学金と学費などが70%以上を占めます。生徒数が定員を満たしていれば運営に支障は出ませんが、大幅な定員割れが長期間続く場合には、経営が苦しくなる可能性が高まるでしょう。
定員割れも多い
近年、多くの専門学校で定員割れが起きています。2016年のリクルートによる調査では、専門学校の定員充足率は平均で63.64%でした。
少子化により18歳人口の減少が続いていることに加えて、大学進学を希望する高校生の割合が増加し続けていることで、専門学校を志望する生徒の減少が続いていることが要因です。
専門学校の学科によっては横ばいや増加している学科もありますが、ほとんどの学科で志望者数の減少が続いています。
専門学校は生徒数によって収益が大きく左右されるので、M&Aによって規模を拡大することで生徒数を確保する動きもみられるようです。
参考:株式会社リクルートマーケティングパートナーズ「専門学校の教育に関する調査 2016」
専門学校をM&Aで譲渡するメリット
専門学校を売却、譲渡するメリットとはどのようなものがあるのでしょうか。専門学校のM&Aで特に大きな2つのメリットを紹介します。
スケールメリット
専門学校をM&Aで売却、譲渡するメリットの一つは、スケールメリットを得られるようになるという点です。M&Aによって他の専門学校や学校法人などと経営統合すれば、教育施設を拡充したり、教員の専門性の幅を広げることができるでしょう。
規模を拡大することで経営の効率化も図ることができる上に、教育内容も充実させることができれば、志願者数の増加によって収益の増加も望めます。
退職金の支給
専門学校をM&Aで売却、譲渡するメリットの一つは、退職金が支給される可能性が高まるという点です。
もしも、経営が悪化して経営破綻することになれば、退職金は望めません。しかし、経営が悪化する前にM&Aで売却できれば、M&Aをきっかけに学校運営から退く経営陣や、退職する教師には退職金が支払われる可能性があります。
専門学校をM&Aで売却・買収する際の流れ
専門学校のM&Aによる売却や買収はどのような流れで進めるのでしょうか。専門学校のM&Aの流れについて解説します。
M&Aの専門家に相談を行う
専門学校のM&Aによる売却や買収を検討し始めたら、最初にM&Aの専門家へ相談することをおすすめします。
M&Aを実施するためには、M&Aに関する法律や財務の高度な知見が必要になります。また、一般企業のM&Aでよく用いられる株式譲渡のスキームを利用することができません。
専門学校のM&Aを検討し始めたら、まずはM&Aの専門家のアドバイスを仰ぐようにしましょう。
M&Aのご相談はお気軽にM&A総合研究所までお問い合わせください
専門学校業界で事業譲渡を適切に行うには、各業界に精通した専門家によるサポートを受けるのがおすすめです。
M&A総合研究所では、M&Aの支援経験豊富なM&Aアドバイザーが専任につき、事業譲渡を丁寧にフルサポートいたします。
また、料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です。(※譲渡企業様のみ)
無料相談も随時受け付けておりますので、こちらの業界で事業譲渡をご検討の際はM&A総合研究所までお気軽にご相談ください。
全体的な流れ
専門学校のM&Aでの売却や買収の流れは、一般企業のM&Aとほぼ変わりません。しかし、都道府県知事からの設置許可を得ている専門学校では、M&Aによる売却や買収に関して、行政との調整が必要な場合が出てくる可能性があります。
M&Aによる専門学校の譲渡によって、学校名に変更がある場合には、4月の新年度の始まりに合わせて校名変更を実施すると、M&Aの影響を最小限に抑えることができます。専門学校のM&Aを進めるときには、4月1日から新体制で始められるように準備を進めましょう。
専門学校をM&Aで譲渡する際の成功ポイント・注意点
専門学校のM&Aでの譲渡を成功させるためには、どのような注意点に気をつけたらいいのでしょうか。特に気をつけたい7つの注意点について解説します。
特殊なM&Aの手法が一般とは異なる
一般企業のM&Aでは、株式譲渡のスキームが用いられることが多いのですが、専門学校では株式を発行していないので株式譲渡でのM&Aは利用できません。
専門学校のM&Aで用いることができるM&Aのスキームは、支配権の承継(役員の入れ替え)、事業譲渡、合併の3つです。
支配権の承継は株式譲渡の代わりに用いられることが多く、専門学校の役員を入れ替えて支配権を承継し、旧役員に退職金を支払います。
事業譲渡は複数の専門学校を持っている法人から一部の学校のみを譲渡したり、専門学校の一部の施設のみを譲渡したりする場合に使うスキームです。
合併を実施するために、理事の3分の2以上の同意と、所轄庁の許可が必要です。合併には新設合併と吸収合併がありますが、専門学校が他の専門学校をM&Aで合併する場合には、吸収合併のスキームがよく用いられます。
M&Aの効果が得られるのは次年度
専門学校でM&Aを実施して、規模を拡大したり学科を新設したりしても、その効果が出るのは次年度まで待たなくてはいけません。
その理由は、M&A実施後に新体制となった専門学校に新しく生徒が入学してくるのが年度初めの4月に集中しているためです。
専門学校の収益の70%が生徒からの納入金であると説明しましたが、M&Aの効果による収益増加を判断できるのは、次年度が始まるまでわかりません。
主に私立の専門学校がM&Aの対象となる
専門学校には公立学校と私立学校があります。この中でM&Aの対象になるのは私立学校のみである点に注意しましょう。公立の専門学校をM&Aで買収することはできません。
私立の専門学校がM&Aで売却される場合には、経営状態が悪化したことによる経営改善を求めてのことが多いようです。
入念にM&Aの計画を立てる必要がある
専門学校のM&Aによる売却を検討し始めたら、入念に売却計画を立てる必要があります。
専門学校は新設が難しいことから、M&Aで売却に出せば買収希望者が現れる可能性はあるでしょう。しかし、売却側が買収側に対して自校を多額の金額で買収するメリットを提示できなければ、希望する金額や条件での売却は難しくなります。
M&Aの具体的な道筋に入る前に、M&Aの専門家の助言も参考にしながら、売却計画をしっかりと立てることが重要です。
生徒数・教員数が充実していると譲渡しやすい
専門学校の収益の大部分を生徒が納める納入金に頼っている一方で、定員割れの専門学校が多くある現場では、生徒数が充実している専門学校のほうが買い手が付きやすいという現実があります。
また、専門的な知識を教えることができる教員が充実していれば、M&A成立後の運営もスムーズに進めることができるでしょう。
生徒や教員は短期間で増やせるものではありません。将来的にM&Aによる専門学校の売却を検討しているのであれば、数年単位で増やしていくようにしましょう。
教育できる人材の確保が重要
定員割れの専門学校が多くありますが、中には定員をオーバーしている専門学校や定員の8割以上の生徒数を常に確保できている専門学校もあります。
生徒が多く集まる専門学校の特徴として、成長市場に対応した人材を育成していることが挙げられます。今後、確実に就職できて長く世間から必要とされる分野についての専門的な技能を身につけられる専門学校であれば、少子化の影響を受けずに生徒を集めることができます。
専門学校で成長市場に対応した学科を開設するためには、その分野を教えることができる人材の確保が重要です。先々のM&Aによる売却を成功させるためには、時代を先読みして、今後必要となる分野を開拓し、その分野に精通した教員を確保するように努めましょう。
経営においてのマイナス要素がないこと
専門学校をM&Aで確実に売却したいと考えているのなら、経営面でのマイナス要素を改善することが重要です。
学校経営においてマイナス要素と判断されるポイントは次のような点があります。
- 負債が多い
- 多大な借り入れ
- 校地、校舎を自己保有していない
負債や借り入れが多い専門学校や、借りた校地や校舎で運営している専門学校が売却できないわけではありませんが、これらのマイナス要素が少ないほうが評価が高くなり、より良い条件での高額が望めます。
また、施設や設備に対する投資が適切に実施されているかどうかも、専門学校の運営を判断する上で重要なポイントになります。
情報関連や工学関連の専門学校では技術革新のサイクルが早まっているので、必要なソフトや機材の定期的な入れ替えが必要です。
資金繰りが円滑にできていなければ、時代遅れの機材や設備で生徒に学習させている可能性もあるので、そのようなマイナスポイントがないか、良くチェックしましょう。
専門学校のM&A・事業売却まとめ
専門学校の数は徐々に減少していますが、学校が減少するペースよりも18歳人口の減少スピードのほうが早いのが現状です。さらに、大学進学の希望者は増加していることから、今後も多くの専門学校の経営状態の悪化が続くでしょう。
専門学校の将来が不安でM&Aによる売却を検討しているのであれば、まずはM&Aの専門家へ相談してみましょう。M&Aをするべきか、といったところから丁寧に相談に乗ってくれるはずです。
M&A・事業承継のご相談なら24時間対応のM&A総合研究所
M&A・事業承継のご相談は成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A総合研究所にご相談ください。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴
- 譲渡企業様完全成功報酬!
- 最短43日、平均7.2ヶ月のスピード成約(2025年9月期実績)
- 上場の信頼感と豊富な実績
- 譲受企業専門部署による強いマッチング力
M&A総合研究所は、M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。
また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。
相談も無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたにおすすめの記事

M&Aとは?意味や動向とM&Aを行う目的・メリットなどをわかりやすく解説!
近年はM&Aが経営戦略として注目されており、実施件数も年々増加しています。M&Aの特徴はそれぞれ異なるため、自社の目的にあった手法を選択することが重要です。この記事では、M&am...

買収とは?用語の意味やメリット・デメリット、M&A手法、買収防衛策も解説
買収には、友好的買収と敵対的買収とがあります。また、買収に用いられるM&Aスキーム(手法)は実にさまざまです。本記事では、買収の意味や行われる目的、メリット・デメリット、買収のプロセスや...

現在価値とは?計算方法や割引率、キャッシュフローとの関係をわかりやすく解説
M&Aや投資の意思決定するうえでは、今後得られる利益の現時点での価値を表す指標「現在価値」についての理解が必要です。今の記事では、現在価値とはどのようなものか、計算方法や割引率、キャッシ...

株価算定方法とは?非上場企業の活用場面、必要費用、手続きの流れを解説
株価算定方法は多くの種類があり、それぞれ活用する場面や特徴が異なります。この記事では、マーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチといった株価算定方法の種類、株価算定のプロセス、株...

赤字になったら会社はつぶれる?赤字経営のメリット・デメリット、赤字決算について解説
法人税を節税するために、赤字経営をわざと行う会社も存在します。しかし、会社は赤字だからといって、必ず倒産する訳ではありません。逆に黒字でも倒産するリスクがあります。赤字経営のメリット・デメリット...
関連する記事

インドネシアのM&A動向と特徴を解説!海外での企業買収のメリットと注意点とは?
平均年齢が若く今後も人口増加が見込めるインドネシアはM&A市場でも魅力的な国の一つです。この記事では、インドネシアでM&Aを実行する上で理解しておきたい、同国の経済動向やM&am...
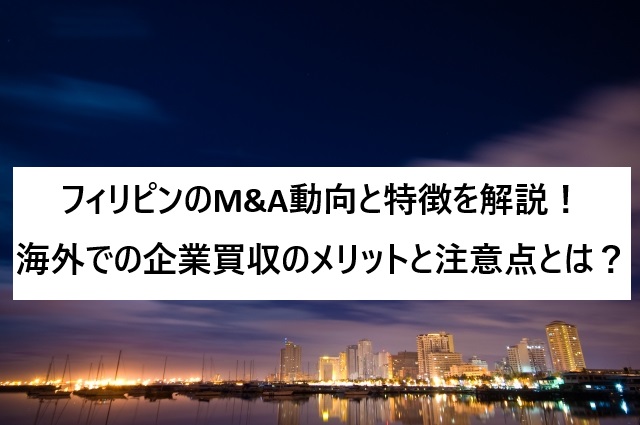
フィリピンのM&A動向と特徴を解説!海外での企業買収のメリットと注意点とは?
海外進出をM&Aで図りたいと考えているのなら、親日国であるフィリピン企業の買収がいいといわれています。この記事では、フィリピンでのM&Aの動向とメリット、日本とは異なる点があるM...
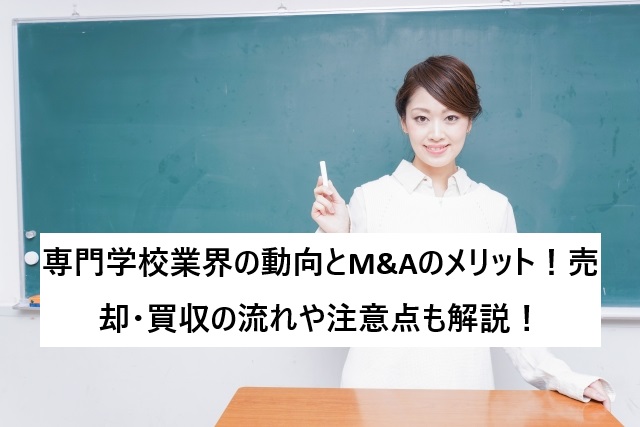
専門学校業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収の流れや注意点も解説!
近年、少子化による生徒数減少などの影響で経営が厳しい専門学校のM&Aによる売却希望が増加しています。専門学校のM&Aは一般企業とは異なる方法で行います。この記事では、専門学校のM...

工場業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例や流れと注意点も解説!
工場業界では、人手不足や後継者問題などの理由で、M&Aでの売却を検討する経営者が増加しています。工場のM&Aによる売却はどのような点を注意するべきなのでしょうか。この記事では、工...

社会福祉法人の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例や流れと注意点も解説!
社会福祉法人の中には、採算が取れない、後継者問題を解決できないなどの理由で、M&Aでの会社や事業の売却を検討する法人があります。この記事では、社会福祉法人業界の近年の動向と、M&...
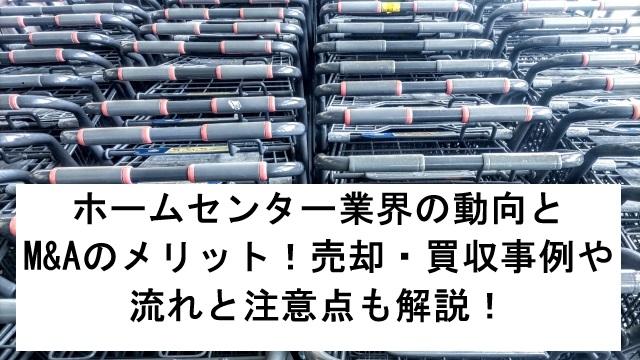
ホームセンター業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例や流れと注意点も解説!
ホームセンター業界では競争激化による1店舗あたりの平均売上が減少しており、M&Aによって生き残りを図ろうとする動きが見られます。この記事では、ホームセンター業界で実施されているM&...

遊園地業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例や流れと注意点も解説!
遊園地業界では、コロナ禍を受けた事業構造改革やサービスの共同開発などを目的としたM&Aが活発に行われています。そこで本記事では、遊園地業界の動向およびメリットや実際の事例やM&A...
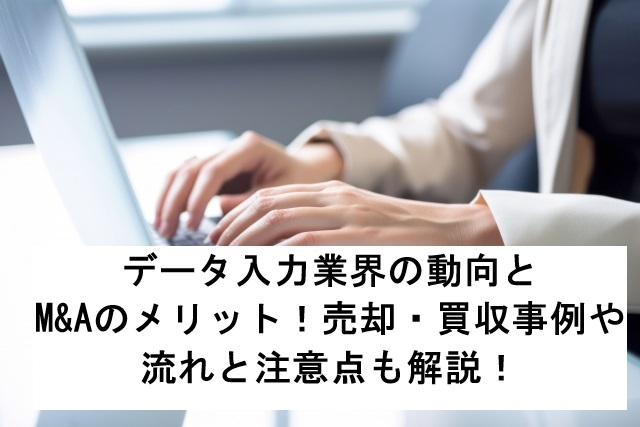
データ入力業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例や流れと注意点も解説!
データ入力業界は参入障壁が低いために競合する会社が多く、厳しい状況を改善するためにM&Aでの生き残りを図る動きがみられます。この記事では、データ入力業界でM&Aを行うメリットや実...

携帯販売代理店業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例や流れと注意点も解説!
携帯電話の契約者数が頭打ちになり低成長時代に入った携帯販売代理店業界では、経営効率化や規模の拡大などを目的にしたM&Aが実施されています。この記事では、携帯販売代理店業界におけるM&am...



















株式会社日本M&Aセンターにて製造業を中心に、建設業・サービス業・情報通信業・運輸業・不動産業・卸売業等で20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、アドバイザーを統括。ディールマネージャーとして全案件に携わる。