M&Aとは?メリット・手法・最新動向を専門家がわかりやすく徹底解説
2023年1月10日更新資金調達
スケールメリットが経営に与える効果は?意味や仕組みを具体例に徹底解説!
スケールメリットとは、同種の業種やサービスが多く集まることで単体よりも大きな成果を生み出せることです。会社経営を行う際、不必要な経費を活用しているケースが多いです。このような課題を解決できるスケールメリットの意味や仕組みを具体的に解説していきます。
スケールメリットとは?

スケールメリットとは、同種のものが多く集まることで単体よりも大きな成果を生み出せることです。
スケールメリットは、会社経営や事業拡大を行う上で意味を理解しておきたい言葉のひとつです。
企業はスケールメリットを行うことによって、新規事業拡大やグループ企業の効率化など、経営にさまざまな影響を与えます。
意味を理解し活用することで大きなメリットにも繋がるため、仕組みを理解し活用しましょう。
それでは、スケールメリットについて解説していきます。
スケールメリットの意味は?

スケールメリットは、和製英語といわれており、通称「規模のメリット」「規模の優位性」とも呼ばれています。
会社経営や事業における規模が大きくなればなるだけ、経済効果・生産性・知名度などが向上することを指して使用されることが一般的です。
スケールメリットを活用することで、大規模になった企業の同じような事業をまとめ、分散していた知識やスキルを集結させ、より効果的に効率的に事業を展開することができます。
これから事業を拡大させたい、余分に使用してしまっていた経費を削減したい、と考えている企業はぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。
スケールメリットの仕組み

スケールメリットの仕組みについて解説していきます。
例えば、パン屋さんが200万円の設備を導入した場合を考えてみましょう。
この設備を使用して原価50円のクロワッサンを1個焼いた場合、クロワッサン1個当たりの精算費用は200万50円です。
このクロワッサンを1万個焼いたらどうなるでしょうか。
1個あたりの生産費用は250円となります。
10万個焼いたら1個あたり生産費用は70円です。
計算式は以下の通りです。
(50円×100,000個+2,000,000)÷10,000=70円
(50円×10,000個+2,000,000)÷10,000=250円
このように、人件費や設備費、家賃などの固定費の割合は生産量が多くなるほど少なくなります。
生産規模の拡大によってコストが削減し、利益率が高まることになるのです。
これを、スケールメリットが生まれるということです。
スケールメリットが経営に与える効果

ここからは、スケールメリットが経営に与える効果について紹介していきます。
スケールメリットの効果は以下の通りです。
・経営効率化
・経費、コストの削減
・生産量拡大
それでは具体的に見ていきましょう。
経営効率化

スケールメリットが経営に与える効果の1つ目は、経営効率化です。
例えば、グループ会社をいくつか展開しており、それぞれの事業内容が重複していると考えましょう。
これらの事業を経営統合し、同じような事業を一つの場所で行うことによって、経営効率化が期待できます。
これは、フランチャイズシステムにも該当するのです。
フランチャイズ化を行うことによって、普通の店舗も大手企業の看板を掲げることができます。
一般の店舗で知名度がなく、なかなかお客さんを集客出来ないという経営課題も、フランチャイズ化することによって知名度を活用し、集客をすることができます。
このように、重複している事業や企業でスケールメリットを行うことによって経営の効率化をすることが可能です。
また、スケールメリットと間違われやすいシナジー効果があります。
シナジー効果は、複数の要素を組み合わせると、それぞれの単体で得られる効果の合計がより大きな成果を生むことです。
スケールメリットとシナジー効果が混同しないよう注意しましょう。
経費・コストの削減

スケールメリットが経営に与える効果の2つ目は、経費・コストの削減です。
商品を一度に大量仕入れをすることで、仕入れにかかる費用を削減することができることもメリットです。
似たような作業を行う場合、その作業をルーティン化して作業スピードや精度を高めることができます。
結果、人件費の削減などのコストカットに繋げることができます。
さらには、輸送先が同じ商品であれば、荷物をまとめることで運用・物流にかかる費用を抑えることができるのです。
ただし、一度にまとめて在庫を抱えると、商品が売り切れなかったときのリスクがあるため、まとめて発注をする量に注意しましょう。
生産量拡大

スケールメリットが経営に与える効果の3つ目は、生産量拡大です。
生産量拡大というのは、販売ルートを確立することです。
商品を販売する場所が限られていると、生産できる状態が整っていても、その量や数を調整する必要があります。
しかし、スケールメリットを活用し、グループ会社のすべてに商品を卸すようにすれば、大量生産を行うことが可能です。
スケールメリットの注意点

ここからは、スケールメリットの注意点を紹介していきます。
スケールメリットには、さまざまメリットがあることから、うまく活用すれば大きな武器となります。
しかし、スケールメリットの活用方法を活かすことができなければ、リスクを背負うことにもなるのです。
スケールメリットの注意点を理解し、正しくスケールメリットを活用しましょう。
それでは具体的に見ていきます。
在庫を抱えすぎないよう生産調整を行う

スケールメリットの注意点1つ目は、在庫を抱えすぎないことです。
前述のメリットでは、経費・コスト削減と説明をしました。
大量発注をする一方、在庫を抱えすぎてしまうと売れなかったときに大きなリスクとなってしまいます。
大量生産を行うスケールメリットの前提にあるのは大量消費です。
大量生産と大量消費が比例することで初めてスケールメリットは成立します。
大量消費が見込めていないままスケールメリットをしてしまうと、リスクを抱える可能性が高くなるため注意が必要です。
顧客のニーズを見つける

スケールメリットの注意点2つ目は、顧客のニーズを見つけることです。
前述の大量消費と結びつきます。
大量消費が行われるということは、その商品に需要があるということです。
購入者たちは時代や環境においてニーズが異なります。
今まで売れていた商品が売れなくなる可能性も考えられるのです。
そのため、スケールメリットを行うときは、時代のニーズに合っているのか、そのニーズの顧客層は大量消費できる存在なのか、経営戦略を練った上でスケールメリットを行いましょう。
インターネットサービスやソフトの開発を大量に行わない

スケールメリットの注意点3つ目は、インターネットサービスやソフトの開発を大量に行わないことです。
スケールメリットの基本は、固定費が一定であり変動しません。
つまり、固定費に含まれる人件費は増加してはいけないということです。
しかし、インターネットサービスやソフトの開発を大量に行おうとすると、それに応じて開発をするための人件費が増えてしまいます。
このような場合の産業では、スケールメリットは通用しません。
生産量に応じて固定費が変動しないことが基本であるにも関わらず、開発に人件費がかかる商品は、インターネットサービスやソフトに限らず、スケールメリットには向いていません。
効率的なコミュニケーション方法を確立させておく

スケールメリットの注意点4つ目は、効率的なコミュニケーション方法を確立させておくことです。
生産量の単純増加ではなく、経営・企業全体の規模を拡大するときにもスケールメリットが有効な場合があります。
しかし、そのとき必要不可欠なのがコミュニケーションコストです。
単純な伝言だけでは、その意図が読み取れないためコミュニケーションを取らなければ伝えることができません。
効率的なコミュニケーション方法を確率させておかないと、会議や社内連絡にコストを割かれてしまい、効率的に進めることができなくなる可能性があります。
そのため、コミュニケーションが必要と言えるでしょう。
スケールメリットの業界別具体例

ここでは、スケールメリットの業界別具体例を紹介していきます。
以下の業界を解説していきます。
・飲食業
・小売業
・運送業
・製造業
・人材業
・教育業
それでは具体的に見ていきましょう。
飲食業

複数の店舗を展開しているケースが多い飲食業界も、スケールメリットを得やすい業種の一つです。
外食チェーンを展開する企業は、店舗数を増やすことによって認知度・知名度が向上します。
このことにより、お客さんからの信頼を獲得することができるのです。
また複数の店舗を展開している場合、一括仕入れによって食品メーカーや卸問屋から好条件で仕入れを行いやすくなります。
店舗共通のポイントカードやクーポンなどを発行することによって、お客さんはどの場所でも馴染みのある味や雰囲気を楽しめる、という安心感を得られるのです。
小売業

小売業界も複数の展開によって、認知度や知名度の向上に繋がります。
出典を一部の地域に限定し、その地域に住む住民の行動特性を考えた商品を揃えることも効果的です。
また、地域密着型企業としてブランド力を向上させることも方法のひとつです。
運送業

運送業界では、ガソリン代などのエネルギーに関する人件費・費用などのコストが発生します。
例えば、貨物運送であれば一度にたくさんの荷物を運ぶことで、コストを分散することが可能です。
また、目的地が同じ荷物をまとめることで荷物1個あたりの経費を削減することができます。
人件費も同様に、多くの人数を乗せることができれば1人あたりのコストを下げることができます。
製造業

製造業界では、工場の施設や機械設備の導入にきゃがくの投資が必要となり、固定費削減の面で大きな効果をもたらします。
工場設備の稼働率が上昇し、生産量が増加すれば、コスト全体に占める固定費割合が減少します。
さらに、古城施設の土地代や家賃。機械設備のメンテナンスなどに経費が発生しているほど、生産量増加によって固定費割合を圧縮できるのです。
近年、製造業では、製造から出荷までの工程を自動化する企業も増えており、より多くの工程を自動化すればさらに人権費などの経費も可能です。
人材業

人材業界では、求職者と企業をマッチングする職業紹介業においては、ブランドイメージや信頼度が重要です。
人材業界の企業は、ブランドイメージが営業収益に直結するため、広告宣伝費をかけて登録者数の増加を目指します。
登録者が増加すれば実績が増え、さらなるブランドイメージの向上を図れます。
一方、求職者が満足できないサービスを提供すれば、ブランドイメージは低下し登録者が減少するため、紹介先の企業から得られる報酬額は減ってしまいます。
人材業界では、スケールメリットの報酬額を増やすバランスをみながら、企業規模を拡大させていくことが重要です。
教育業

教育業界では、塾などの営利目的である教育職業は、学習プログラム・実績・ネームバリューなどが重要です。
教室の数が多い塾は、多くの生徒を抱えることになりますが、これに伴い認知度や知名度、信頼度が上がります。
また、生徒の数が多いほど実績も伸ばしやすく、その情報を知った知人が入学するという好循環ループが生まれます。
生徒が増えれば講師の経験値も増え、成績アップのためのプログラムを作れるようになるでしょう。
スケールメリットによる恩恵を受けよう!

スケールメリットの意味や仕組みを具体的に解説していきましたが、ビジネスにおいて非常に重要な知識であるということが分かったのではないでしょうか。
スケールメリットの仕組みやメリット・デメリットは企業経営をする上で理解しておくべき知識の一つです。
スケールメリットを理解しておくことで、人件費や固定費などの経費を削減することができます。
企業経営をする上で余分な出費をなくし、必要な経費だけを使用して経営をするのが理想的な状態です。
新規事業を立ち上げるときや起業をするときなど、スケールメリットを活用することで、理想的な経営に近づくことができるため、検討している企業は試してみはいかがでしょうか。
M&A・事業承継のご相談ならM&A総合研究所
M&A・事業承継のご相談なら経験豊富なM&AアドバイザーのいるM&A総合研究所にご相談ください。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴
- 譲渡企業様完全成功報酬!
- 経験豊富なM&Aアドバイザーがフルサポート
- 圧倒的なスピード対応
- 独自のAIシステムによる高いマッチング精度
M&A総合研究所は、成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A仲介会社です。
M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。
また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。
相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。
>>完全成功報酬制のM&A仲介サービスはこちら(※譲渡企業様のみ)
M&A・事業承継のご相談なら24時間対応のM&A総合研究所
M&A・事業承継のご相談は成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A総合研究所にご相談ください。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴
- 譲渡企業様完全成功報酬!
- 最短43日、平均7.2ヶ月のスピード成約(2025年9月期実績)
- 上場の信頼感と豊富な実績
- 譲受企業専門部署による強いマッチング力
M&A総合研究所は、M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。
また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。
相談も無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたにおすすめの記事

M&Aとは?メリット・手法・最新動向を専門家がわかりやすく徹底解説
M&Aは事業拡大や事業承継の有効な手段です。本記事ではM&Aの基礎知識から、2025年以降の最新動向、手法、メリット・デメリット、成功させるためのポイントまで、専門家が分かりやす...

買収とは?用語の意味やメリット・デメリット、M&A手法、買収防衛策も解説
買収には、友好的買収と敵対的買収とがあります。また、買収に用いられるM&Aスキーム(手法)は実にさまざまです。本記事では、買収の意味や行われる目的、メリット・デメリット、買収のプロセスや...

現在価値とは?計算方法や割引率、キャッシュフローとの関係をわかりやすく解説
M&Aや投資の意思決定するうえでは、今後得られる利益の現時点での価値を表す指標「現在価値」についての理解が必要です。今の記事では、現在価値とはどのようなものか、計算方法や割引率、キャッシ...

株価算定方法とは?非上場企業の活用場面、必要費用、手続きの流れを解説
株価算定方法は多くの種類があり、それぞれ活用する場面や特徴が異なります。この記事では、マーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチといった株価算定方法の種類、株価算定のプロセス、株...

赤字になったら会社はつぶれる?赤字経営のメリット・デメリット、赤字決算について解説
法人税を節税するために、赤字経営をわざと行う会社も存在します。しかし、会社は赤字だからといって、必ず倒産する訳ではありません。逆に黒字でも倒産するリスクがあります。赤字経営のメリット・デメリット...
関連する記事
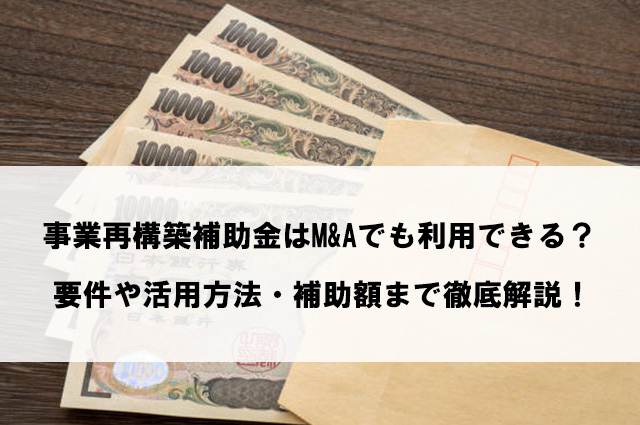
事業再構築補助金はM&Aでも利用できる?要件や活用方法・補助額まで徹底解説!
事業再構築補助金は要件を満たせば、中小企業や中堅企業に補助金を支給する制度です。中にはM&Aを実施するときに制度を利用する企業も存在します。この記事ではM&Aを実施しても事業再構...

DDSとは?DESとの違いや手順・活用方法・メリット・デメリットまで解説!
企業再建手法の1つとして注目されているDDS。そんなDDSとよく似た言葉にDESがありますが、それぞれの違いは何なのかを本記事で解説していきます。またDDSを実施する手順や活用方法、メリットやデ...

CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)とは?メリット・デメリットを解説!
ベンチャー企業へ投資をするCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)。VC(ベンチャーキャピタル)と混同されがちなCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)とは何なのか、活用するメリット・デメリ...

エンジェル投資家について徹底解説!メリットやデメリット・探し方は?
企業がイグジット(上場、ハイバリエーションでの売却)をした際のキャピタルゲインを目的とした投資を行うエンジェル投資家。返済義務がない投資をメインとしているエンジェル投資家について知らない人も多い...

シード期とは?定義やスタートアップの資金調達方法・成功のポイントを解説!
成長していく過程においてIPOやM&Aを活用することも重要ですが、具体的にどのようなポイントを抑えれば良いのでしょうか。 この記事では、シード期の定義やスタートアップの資金調達方法・成...

M&Aにおけるエスクローの意味とは?メリット・デメリットについて紹介!
日本のM&Aでは、活用されているケースは少ないとされている仲介サービス「エスクロー」があります。海外では多く活用されていますが、この「エスクロー」とはどういう意味なのでしょうか。ここでは...

投資銀行のM&Aにおける役割とは?部門ごとの業務内容や違いを解説!
投資銀行は銀行の一種ではないと聞くと、驚かれる方が多いかもしれません。投資銀行は、銀行業ではなく証券業に分類されます。本記事では、投資銀行の概要、投資銀行がM&Aにおける役割、投資銀行の4大業務...

スケールメリットが経営に与える効果は?意味や仕組みを具体例に徹底解説!
スケールメリットとは、同種の業種やサービスが多く集まることで単体よりも大きな成果を生み出せることです。会社経営を行う際、不必要な経費を活用しているケースが多いです。このような課題を解決できるスケ...

株式分割とは何?仕組みやメリット・デメリットなどをわかりやすく解説!
株式分割とは、1株をいくつかに分割して、発行済みの株式枚数を増やすことです。株式分割には企業側、投資家側にメリット・デメリットが存在します。理解していないとトラブルに発展する可能性があります。そ...
























立命館大学卒業後、地方銀行にて中堅中小企業を担当。ファイナンス、ビジネスマッチング等に従事した後、本部専門部署にて事業承継支援を専門として実績を積む。
その後、大手M&A仲介会社において、事業承継や戦略的な成長を目的としたM&Aを業種・規模問わず、多数成約に導く。
M&A総合研究所では、製造業や建設業、不動産業など幅広い業種を担当。