M&Aとは?メリット・手法・最新動向を専門家がわかりやすく徹底解説
2022年10月21日更新資金調達
資本コスト(WACC)とは?種類、計算方法をわかりやすく解説
資本コスト(WACC)とは、会社が資金調達するときに必要となる費用です。資本コストには、負債コストと株主資本コストの2つがあります。本記事では、資本コスト(WACC)の種類、計算方法、資本コストを下げる方法などをわかりやすく解説します。
資本コスト(WACC)とは

資本コストとは、会社が資金調達の際に必要となる費用のことです。資金を集めたいときに、会社は銀行からの融資に頼ったり、新株を発行して株主からの投資を依頼したりします。こうした銀行融資の利息や、株主への配当などに必要となる費用が、資本コストです。
一方、投資家の観点から見ると、資本コストの意味は少し変わります。会社にとっては費用でも、投資家にとっては、投資に対する利益(配当)です。会社を経営する際は、常にこの資本コストを意識しなくてはなりません。
資本コストに対して、キャッシュフロー(利益)が上回っている会社は優良な会社ですので、投資家からの資金が集めやすくなり、安定してキャッシュフローを生み出している会社として、銀行融資の審査もとおりやすいです。
利益よりも資本コストが大きい会社は、投資に対する配当を出せない、融資の返済能力がない会社であると判断されるため、会社は資本コストを支払っても、利益が生み出せるよう注意しなければなりません。
日本のビジネス界では、資本コストの考え方がしっかり認識されている状況ではありません。資本コストは、事業の価値計算において必須です。また、グローバルに事業を広げるうえでも欠かせない概念といえます。
資本コストと資金調達の関係性
上述したとおり、会社が円滑に資金調達するには、資本コスト(WACC)を意識し会社を経営しなければなりません。その指標の一つが、キャッシュフローがWACCを上回っているかどうかになります。
WACCを上回るキャッシュフローを得られると、銀行、投資家、株主などに魅力的と思われるでしょう。その結果、資金調達を行いやすくなります。キャッシュフローがWACCを下回る場合は、リスクに見合ったリターンが得られない投資先と思われるので、資金調達は困難となるでしょう。
M&Aによる資金調達を検討するなら、専門家に相談を
M&Aを目的とする資金調達をご検討の際は、ぜひM&A総合研究所にご相談ください。M&A総合研究所では、M&Aの知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーが、案件をフルサポートいたします。
料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。無料相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
資本コストの種類

会社が資金を調達する際、その方法は大きく分けて以下の2種類があります。
- 株主資本コスト
- 負債コスト
①株主資本コスト
株式を保有している株主に還元する、いわゆる配当が株主資本コストです。株主が会社に投資する動機はさまざまですが、最終的には会社の利益からもらえる配当を期待しています。
投資してもらったからには会社は株主に対し、より多額の配当金を渡すため、利益を獲得する必要があります。つまり、株主資本コストは、投資家と会社の両方の観点から見た配当金です。
②負債コスト
銀行や債権者などからの借り入れには利息が付きますが、その利息が負債コストです。銀行や債権者は、会社にお金を貸してくれますが、無料では貸しません。銀行や債権者などから資金を借り入れする際は、利息を支払う必要があります。
銀行などの融資をしてくれる機関は、返済能力がある会社にしか資金を貸しません。負債コストは、融資を実施する機関で利率が変動するため、どこの機関から融資を受けるかをしっかりと検討する必要があります。
資本コストとは、会社に求める期待値です。株主や銀行にとっては、どれほどのリターンが得られるのか、が鍵です。
資本コストの計算方法

資本コストは、株主資本コストと負債コストの加重平均となります。資本コストを算出する際は、WACC(ワック)を利用します。WACCの計算式は以下です。
- 資本コスト=D/(D+E)×rD(1−T)+E/(D+E)×rE
このときに1から実効税率を引いた数字を掛け算すると、利息が税務上では損金扱いとなるので、会社にとっては税金対策になります。
資本コストを計算式にすると複雑に見えますが、株主資本コストと負債コストを足して平均値を求めた式が、資本コストです。WACCの計算式に必要な基礎知識は、以下になります。
- D:有利子の負債額
- E:株主資本の時価
- rD:負債資本コスト
- T:実効税率
- rE:株主資本コスト
①D:有利子の負債額
利子が付いている負債額のことです。基本的には時価で計算をする必要がありますが、負債は時価で計算するのが難しいので、簿価で計算する場合もあります。
②E:株主資本の時価
株式保有にかかる時価総額のことです。株主資本の時価を求める際は、株価と発行している株式の数を乗算します。
③rD:負債資本コスト
前項で解説した負債コストのことです。銀行融資や債権者からの借り入れに対し、支払う利息のことをさします。この利息は会社によって異なるため、当然利率の低い融資を選択すれば、資本コスト自体も高額になりません。
④T:実効税率
税金の負担額のことです。損金として算入される税金を考慮し、基本的には40%で計算します。
⑤rE:株主資本コスト
前項で解説した株主資本コストのことですが、金額そのものを計算式に当てはめられません。WACCでは、株主に対する期待収益率として考えます。
株主資本コスト単体の利率を求めるためには、リスクフリーレート、自社株式のβ値、株式市場全体の期待収益率の計3つの要素を用います。
資本コストを下げる方法

経営者であれば、資本コストをできるだけ少なくしたいと考えるのが自然です。資本コストを下げるための方法として、その会社のリスクを開示する方法があります。基本的に投資家や銀行は、会社に対して利益を求めてお金を出すので、会社の情報開示は投資の判断材料として有力です。
リスクを開示すれば、リスクに見合ったリターンを要求してもらえます。「私の会社は◯億円の赤字が出ました」などと投資に対するリスクを公表すると、投資家が会社に持つ期待値も低くなるでしょう。その結果、投資家が求めるリターンも低くなり、それに伴い資本コストも低くなります。
銀行や債権者からの借り入れに対する資本コストを下げるには、各金融機関で、できるだけ低金利で借りるのが有効です。一般的には、信頼があり返済能力があるとみなされた会社であれば、低金利でお金を借りられる可能性が高まります。
借り入れ期間が短い、他の借り入れ機関からの乗り換えなどでも、低金利で融資を受けられる場合があるでしょう。融資の金利には変動制と固定制があるため、どちらの金利を選択するかを社内で検討する必要があります。
資本コストで悩んだら、専門家に相談を
資本コストを考えるときは、正しい知識を持つ専門家に相談するのがおすすめです。
M&A総合研究所では、経験や知識の豊富なM&Aアドバイザーが、案件をフルサポートいたします。資本コストでお悩みの際は、ぜひご相談ください。
料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。無料相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
資本コスト(WACC)のまとめ

資本コストは、資金調達に必要なコストのことで、その会社に対する期待値が明確に現れます。会社はその期待に応える必要があります。
一方で、資本コストのために経営が思うように回らないケースもあるでしょう。そうしたリスクを避けるため、できるだけ資本コストは低いほうが好ましいです。会社は、常に資本コストを意識して経営する必要があります。
資本コストは、未来に対して発生するコストでもあるため予測するのは難しいですが、資本コスト以上の利益を獲得することは、会社にとって必要不可欠です。
M&A・事業承継のご相談なら24時間対応のM&A総合研究所
M&A・事業承継のご相談は成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A総合研究所にご相談ください。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴
- 譲渡企業様完全成功報酬!
- 最短43日、平均7.2ヶ月のスピード成約(2025年9月期実績)
- 上場の信頼感と豊富な実績
- 譲受企業専門部署による強いマッチング力
M&A総合研究所は、M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。
また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。
相談も無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたにおすすめの記事

M&Aとは?メリット・手法・最新動向を専門家がわかりやすく徹底解説
M&Aは事業拡大や事業承継の有効な手段です。本記事ではM&Aの基礎知識から、2025年以降の最新動向、手法、メリット・デメリット、成功させるためのポイントまで、専門家が分かりやす...

買収とは?用語の意味やメリット・デメリット、M&A手法、買収防衛策も解説
買収には、友好的買収と敵対的買収とがあります。また、買収に用いられるM&Aスキーム(手法)は実にさまざまです。本記事では、買収の意味や行われる目的、メリット・デメリット、買収のプロセスや...

現在価値とは?計算方法や割引率、キャッシュフローとの関係をわかりやすく解説
M&Aや投資の意思決定するうえでは、今後得られる利益の現時点での価値を表す指標「現在価値」についての理解が必要です。今の記事では、現在価値とはどのようなものか、計算方法や割引率、キャッシ...

株価算定方法とは?非上場企業の活用場面、必要費用、手続きの流れを解説
株価算定方法は多くの種類があり、それぞれ活用する場面や特徴が異なります。この記事では、マーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチといった株価算定方法の種類、株価算定のプロセス、株...

赤字になったら会社はつぶれる?赤字経営のメリット・デメリット、赤字決算について解説
法人税を節税するために、赤字経営をわざと行う会社も存在します。しかし、会社は赤字だからといって、必ず倒産する訳ではありません。逆に黒字でも倒産するリスクがあります。赤字経営のメリット・デメリット...
関連する記事
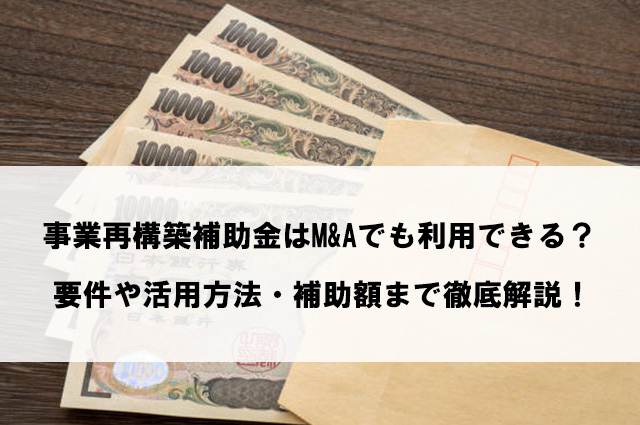
事業再構築補助金はM&Aでも利用できる?要件や活用方法・補助額まで徹底解説!
事業再構築補助金は要件を満たせば、中小企業や中堅企業に補助金を支給する制度です。中にはM&Aを実施するときに制度を利用する企業も存在します。この記事ではM&Aを実施しても事業再構...

DDSとは?DESとの違いや手順・活用方法・メリット・デメリットまで解説!
企業再建手法の1つとして注目されているDDS。そんなDDSとよく似た言葉にDESがありますが、それぞれの違いは何なのかを本記事で解説していきます。またDDSを実施する手順や活用方法、メリットやデ...

CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)とは?メリット・デメリットを解説!
ベンチャー企業へ投資をするCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)。VC(ベンチャーキャピタル)と混同されがちなCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)とは何なのか、活用するメリット・デメリ...

エンジェル投資家について徹底解説!メリットやデメリット・探し方は?
企業がイグジット(上場、ハイバリエーションでの売却)をした際のキャピタルゲインを目的とした投資を行うエンジェル投資家。返済義務がない投資をメインとしているエンジェル投資家について知らない人も多い...

シード期とは?定義やスタートアップの資金調達方法・成功のポイントを解説!
成長していく過程においてIPOやM&Aを活用することも重要ですが、具体的にどのようなポイントを抑えれば良いのでしょうか。 この記事では、シード期の定義やスタートアップの資金調達方法・成...

M&Aにおけるエスクローの意味とは?メリット・デメリットについて紹介!
日本のM&Aでは、活用されているケースは少ないとされている仲介サービス「エスクロー」があります。海外では多く活用されていますが、この「エスクロー」とはどういう意味なのでしょうか。ここでは...

投資銀行のM&Aにおける役割とは?部門ごとの業務内容や違いを解説!
投資銀行は銀行の一種ではないと聞くと、驚かれる方が多いかもしれません。投資銀行は、銀行業ではなく証券業に分類されます。本記事では、投資銀行の概要、投資銀行がM&Aにおける役割、投資銀行の4大業務...

スケールメリットが経営に与える効果は?意味や仕組みを具体例に徹底解説!
スケールメリットとは、同種の業種やサービスが多く集まることで単体よりも大きな成果を生み出せることです。会社経営を行う際、不必要な経費を活用しているケースが多いです。このような課題を解決できるスケ...

株式分割とは何?仕組みやメリット・デメリットなどをわかりやすく解説!
株式分割とは、1株をいくつかに分割して、発行済みの株式枚数を増やすことです。株式分割には企業側、投資家側にメリット・デメリットが存在します。理解していないとトラブルに発展する可能性があります。そ...
























立命館大学卒業後、地方銀行にて中堅中小企業を担当。ファイナンス、ビジネスマッチング等に従事した後、本部専門部署にて事業承継支援を専門として実績を積む。
その後、大手M&A仲介会社において、事業承継や戦略的な成長を目的としたM&Aを業種・規模問わず、多数成約に導く。
M&A総合研究所では、製造業や建設業、不動産業など幅広い業種を担当。