M&Aとは?メリット・手法・最新動向を専門家がわかりやすく徹底解説
2022年6月6日更新資金調達
TOBの不成立/ディスカウントの代表事例10選!
TOBとは、買い手が株式の数や価格、期間などを定め、株式取引市場外で株式の公募を行う取引手法のことです。本記事では、TOBが不成立やディスカウントになる意味と、TOBが不成立になった事例やディスカウントTOBが行われた事例をご紹介します。
目次
TOBの不成立/ディスカウントとは

TOB(株式公開買付け)は、経営戦略のひとつとして以前から多く用いられている株式売買方法ですが、そのなかには、TOBが不成立になる事例や割安な買取価格でTOBを行う事例もあります。
本記事では、TOBが不成立となった事例やディスカウントTOBの事例を紹介しますが、まずはTOB、不成立TOB、ディスカウントTOBとはどのようなものなのかについて解説します。
TOBとは
株式の売買は、取引市場内で行う方法と取引市場外で行う方法とがありますが、TOB(株式公開買付け)は取引市場外で株式を売買する方法のひとつです。
TOBは株式公開買付けとも呼ばれ、買い手が買い集めたい株式数・価格・期間などの情報を公開し、対象の株主から買い集める方法です。
取引市場内で大量の株式を短期間に買い集めようとすると、株価がどこまで上昇するかわからないというリスクがあります。
しかし、TOBであれば買取価格が設定されているので、買い手は買取予算などの計画を立てやすい点がメリットです。
もし募集株式数の下限に満たなかった場合、買い手はTOB自体をキャンセルできるため、不要なリスクを背負う必要もありません。
友好的TOBと敵対的TOBの違い
TOBを実施する際は、事前に買い手が買収先企業の経営陣や主要な大株主と交渉し、賛同を得ることが一般的です。
買収先経営陣の賛同を得られた状態で行われるTOBは友好的TOBとなり、TOBの成功率はかなり高くなります。
一方、買い手が相手企業の経営陣から賛同を得られないままTOBを強行した場合は敵対的TOBとなり、経営陣の抵抗によってTOBの成功率は格段に下がります。
M&A先進国の米国では、敵対的TOBが実施されて成功するケースも少なくありませんが、日本では米国に比べて敵対的TOBの成功率は低く、件数自体も多くはありません。
かつて、日本でも敵対的TOBが相次いだことはありましたが、成功率の低さからほとんど行われなくなっていきました。
しかし、近年再び敵対的TOBの件数が増え始めており、その背景にはさまざまな業界に再編の波が来ていることで、株主の目が厳しくなっていることなどが挙げられます。
MBOとの違いを解説
TOBの買い手、は必ずしも第三者とは限らず、経営陣が自社の株式をTOBによって買い集めるケースもあります。
経営陣が自社の株式を買い集めることをMBOといい、経営陣が自社株を集約することによって上場を廃止し、株主の意向に左右されることなく経営を行うなどの目的で実行されます。
また、MBOの際は投資ファンドや金融機関がサポートするケースが多く、MBO後に企業価値を高め再上場することによって、投資ファンドや金融機関は多額の利益を得ることができます。
TOBの不成立とは
TOBは、買い手が設定した目標買取株式数の下限に届かなかった場合、不成立となります。TOBとなる原因はさまざまですが、特に不成立となる確率が高いのは敵対的TOBとなった場合です。
前述のように、買い手が相手企業の経営陣から賛同を得られないままTOBを強行した場合は、敵対的TOBとなります。
その際、相手企業の経営陣は買収防衛策によって対抗することが多いので、TOBが不成立となる確率も高くなります。
どのような買収防衛策を用いるかは事例によってさまざまです。買収防衛策には、予防策としてあらかじめ設定しておくものや、敵対的買収を仕掛けられてから実行するものがあります。
よく用いられる方法は、敵対的買収を仕掛けられた後に第三者割当増資を行ったり、新株予約権を発行したり、第三者に有効的TOBを依頼したりする方法です。
TOBのディスカウントとは
通常のTOBは、なるべく多くの株主から株式を買い集めるために、基準となる市場価格よりも高い買取価格を設定します。
一方、ディスカウントTOBの場合は、基準となる市場価格よりも安い価格で募集をかけます。市場価格よりも低価格でTOBを行う理由は、特定の株主から株式を買い取るためです。
あらかじめ株式の売買を確約し、ある株主から株式を買い取るために低価格に設定することで、ほかの株主が応募するメリットをなくします。
なお、特定の株主から株式を買い取るだけであれば、相対取引の方がスムーズに手続きを進めることができます。
しかし、短期間で対象企業の1/3以上の株式を買う場合は、株主間の公平性を保つためにTOBでなければならないと法令で定められています。
TOBの不成立/ディスカウントの代表事例10選

ここからは、TOBが不成立となった事例やディスカウントTOBが行われた事例をご紹介します。
- ドン・キホーテからオリジン東秀への不成立TOB
- 富士通からソレキアへの不成立TOB
- 夢真ホールディングスから日本技術開発への不成立TOB
- ベインキャピタルと廣済堂経営陣による不成立TOB
- 王子製紙から北越製紙への不成立TOB
- スティール・パートナーズから明星食品への不成立TOB
- TBIホールディングスとホリイフードサービスのディスカウントTOB
- RIZAPグループとジーンズメイトのディスカウントTOB
- 三菱商事と三菱自動車工業のディスカウントTOB
- 三井化学とアークのディスカウントTOB
1.ドン・キホーテからオリジン東秀への不成立TOB
不成立TOBの事例1件目は、ドン・キホーテからオリジン東秀への不成立TOBです。
ドン・キホーテは独自の要素を取り入れたコンビニエンスストアである「パワーコンビニ情熱空間」を展開するため、2005年にオリジン弁当を展開するオリジン東秀を買収しようとしました。
しかし、オリジン東秀はドン・キホーテによるTOBの提案に反対の意思を表明したことで敵対的TOBに発展します。
その後、友好的TOBによって敵対側に対抗するホワイトナイト役にイオングループが手を挙げたことで、ドン・キホーテとイオングループの直接対決となりました。
最終的にイオングループが勝利し、ドン・キホーテ側は保有していたオリジン東秀の株式をイオングループに売却しています。
その後ドン・キホーテは計画していたパワーコンビニ情熱空間の展開を進めようとしましたがうまくいかず、事業から撤退しています。
2.富士通からソレキアへの不成立TOB
不成立TOBの事例2件目は、富士通からソレキアへの不成立TOBです。ジャスダック市場に上場している電子部品商社のソレキアは2017年、実業家の佐々木ベジ氏からTOBの提案を受けました。
しかし、ソレキアは佐々木ベジ氏からのTOBに反対の意思を表明し、ソレキアと取引関係にあった富士通がホワイトナイトとして買収に対抗することとなります。
個人の佐々木ベジ氏と大企業である富士通のTOB競争は、富士通が圧倒的に有利と考える人が大半でしたが、佐々木ベジ氏と富士通は買取価格を次々と引き上げていき泥沼化していきます。
富士通は、ソレキアの完全子会社化を目指して買取株式数を設定していましたが、買取価格の高騰についていくことができずギブアップし、一方の佐々木ベジ氏は目標の買取株式数を達成し、富士通とのTOB競争に勝利します。
3.夢真ホールディングスから日本技術開発への不成立TOB
不成立TOBの事例3件目は、夢真ホールディングスから日本技術開発への不成立TOBです。
建設関連を中心に事業展開している夢真ホールディングスは2005年、建設コンサルタントの日本技術開発に対して敵対的TOBの実施を発表しました。
すでに買収防衛策を導入していた日本技術開発は対抗策を講じますが、それに対して夢真ホールディングスは訴訟を起こします。
しかし、裁判所への訴訟は却下され、さらに日本技術開発側には同じく建設コンサルタントのエイトコンサルタントがホワイトナイトとして現れます。
TOBはエイトコンサルタント側が成立となり、不成立となった夢真ホールディングスは日本技術開発の買収から撤退することとなりました。
その後、夢真ホールディングスは次々と買収を行いグループを拡大していきましたが、短期間で急速に買収を行ったことにより業績が悪化し、結果的に買収した企業を売却することになっています。
4.ベインキャピタルと廣済堂経営陣による不成立TOB
不成立TOBの事例4件目は、ベインキャピタルと廣済堂経営陣による不成立TOBです。
投資ファンドのベインキャピタルは2019年、印刷業や葬祭業を営む廣済堂の子会社化を目的としてTOBを提案し、廣済堂経営陣はTOBに賛同していました。
しかし、廣済堂の大株主である澤田ホールディングスやレノ、櫻井氏がTOBに反対を表明します。
さらに、南青山不動産がベインキャピタルと敵対する形でTOBを発表したことから、ベインキャピタルによるTOBの成功可能性はさらに低くなりました。
廣済堂のTOBが不成立に終わった要因は、廣済堂の子会社である東京博善にあります。
東京博善の企業価値はベインキャピタルが提示したTOB価格よりもかなり高いと見られていたことから、TOBによる機会損失の可能性に不満を持った大株主が反対することとなりました。
5.王子製紙から北越製紙への不成立TOB
不成立TOBの事例5件目は、王子製紙から北越製紙への不成立TOBです。2006年当時、製紙業界は業界再編が起きていたことから、王子製紙は北越製紙をグループに加えることで業界シェアを広げる計画でした。
しかし、北越製紙は三菱商事への第三者割当増資を実施することで、王子製紙による北越製紙株式の株式保有割合を下げる対抗策を講じます。
また、日本製紙グループが王子製紙の対抗勢力として参戦し、北越製紙の株式を買い取りました。
北越製紙が抵抗した結果、王子製紙は株式買取目標にまったく届くことなく失敗に終わっています。当時の王子製紙は失敗の要因を、友好的とも敵対的ともとれる中途半端なTOB戦略をとったことにあるとしています。
6.スティール・パートナーズから明星食品への不成立TOB
不成立TOBの事例6件目は、スティール・パートナーズから明星食品への不成立TOBです。スティール・パートナーズは2003年、会社の立て直しを進めていた明星食品の株式を取得しました。
その後も株式の取得を続けたスティール・パートナーズは、明星食品の大株主となります。そして2006年には、明星食品に対するTOBを発表します。
しかし、当時の明星食品経営陣はTOBへの抵抗姿勢を示したため、スティール・パートナーズは強制的にTOBを進めることとなりました。
それに対して明星食品は日清食品に助けを求め、日清食品は友好的TOBを実施します。日清食品がスティール・パートナーズよりも高額な買取価格を提示したことでスティール・パートナーズのTOBは不成立となりました。
当時業界4位であった明星食品を買収したことにより、日清食品はシェア拡大を果たしています。また、スティール・パートナーズはTOBは不成立に終わったものの、すでに保有していた明星食品株式の売却により利益を得ています。
7.TBIホールディングスとホリイフードサービスのディスカウントTOB
ディスカウントTOBの事例1件目は、TBIホールディングスとホリイフードサービスのディスカウントTOBです。
独自の経営戦略で飲食店を拡大しているTBIホールディングスは2017年、居酒屋チェーンのフランチャイジーとして成長してきたホリイフードサービスを、TOBによって子会社としました。
本買収は、TOB価格が基準となる市場価格よりも約22%安いディスカウントTOBとなっています。
TBIホールディングスはホリイフードサービス創業者の代表取締役会長からホリイフードサービス株式の過半数を取得するため、ディスカウントTOBを選択しました。
一方、ホリイフードサービスは業績不振が続いており、会社の立て直しにはTBIホールディングスの力が必要な状態でした。そのため、ホリイフードサービス創業者はあえて割安な価格での株式売却を決断しています。
8.RIZAPグループとジーンズメイトのディスカウントTOB
ディスカウントTOBの事例2件目は、RIZAPグループとジーンズメイトのディスカウントTOBです。
スポーツジムの運営などを行っているRIZAPグループは2017年、ジーンズを中心としたカジュアルウェアの販売を行なっているジーンズメイトをグループに加えました。
ジーンズメイトは競合他社との競争に苦戦し、業績の立て直しを進めている最中でした。
RIZAPグループはジーンズメイトを短期間で立て直す計画でジーンズメイトの創業者一族と交渉し、大半のジーンズメイト株式を創業者一族から取得することに同意を得ます。
RIZAPグループはディスカウントTOBによって計画通りジーンズメイトの子会社化に成功しますが、2019年にはRIZAPグループの業績悪化が発覚します。
原因は、短期間で次々と業績不振企業を買収し、会社の立て直しが追いつかなかったことにあります。
RIZAPグループは子会社の売却など経営体質の改善を進めていますが、そのような中でもジーンズメイトは長らく続けてきた経営改善策が成果として現れ始め、業績アップに成功しています。
9.三菱商事と三菱自動車工業のディスカウントTOB
ディスカウントTOBの事例3件目は、三菱商事と三菱自動車工業のディスカウントTOBです。三菱商事は2018年、三菱自動車工業をTOBにより関連会社化しました。
株式の募集対象株主は三菱関連の企業であることから、市場の基準価格よりも10%安いディスカウントTOBとなりました。三菱商事は三菱自動車工業への出資比率を増やすことで連携の強化を図っています。
また、三菱自動車工業関連会社化することで、利益の積み増しも期待できます。他にも、大転換期を迎えている自動車業界の流れについていくため、三菱自動車工業と協力することで新分野の事業開発を進めていく計画です。
10.三井化学とアークのディスカウントTOB
ディスカウントTOBの事例4件目は、三井化学とアークのディスカウントTOBです。三井化学は2017年、子会社のエムシーインベストメント01を通じてアークを買収することを発表しました。
アーク株式の大半をオリックスの子会社とみずほ銀行、三菱東京UFJ銀行から買い取ることが事前に決まっていたことから、三井化学は基準となる市場価格よりも約10%やすいディスカウントTOBを実施しています。
当時のアークは、M&Aによる負債の増加やリーマンショックによる業績悪化により経営再建中でした。三井化学によるアークへのTOBは2018年に完了し、三井化学はアークの会社立て直しと自動車業界での営業力強化を進めています。
TOBの不成立/ディスカウント後の対象株式はどうなる?

募集株式数の下限に満たなかった場合、TOBは不成立となりますが、買い手は下限に満たなかった株式を買い取る必要はありません。というのは、TOBに応募した株主の株式は元の株主の手もとへ戻るためです。
株式が元の株主の手もとに戻ってくるまで株式の売却はできないので、TOB期間中に対象株式の市場価格が下がった場合、手もとに戻ってきた時点では損をしていることになります。
逆に市場価格が上がっていれば、手もとに戻ってきた際にすぐ売却すると利益が出ます。また、ディスカウントTOBに応募した場合は、市場価格よりも安く対象株式を売却することになります。
TOBに応募せず、ディスカウントTOB後も株式を保有し続けることも可能ですが、TOB後に上場廃止の計画がある場合、少数株主の保有する株式は強制的に買い取られる可能性があるので注意が必要です。
TOBの不成立/ディスカウントを防ぐには?

TOBに対して、買収される側の経営陣が買収防衛策を実行するとTOBが不成立になる可能性は高くなります。また、経営陣が賛同していても、大株主がTOBに反対し応募しなければ、TOBは不成立となります。
買い手が不成立を防ぐには、経営陣や大株主を説得して賛同を得るか、裁判所に買収防衛策の不当性を訴えるかの方法をとるしかありません。
しかし、経営陣から反対されている場合、TOBが不成立になる確率はかなり高いのが現状です。
一方、買収される側の経営陣がTOBに賛同している場合は、株主の反対があっても成功しているケースは多く見られます。また、ディスカウントTOBは買い手と経営陣、大株主があらかじめ賛同した状態で行われることが大半です。
そのため、その他の株主がディスカウントTOBを止めるには、募集価格の不当性を裁判所に訴える方法がありますが、成功率は高くありません。
TOBの相談におすすめのM&A仲介会社

ここまで述べたように、TOBの際は買い手も売り手も事前の入念な準備が大切です。TOBを成功させるには、専門知識だけではなく、関係各所の関係を円滑にする交渉力もポイントになります。
M&A総合研究所では、豊富な知識・支援実績を持つアドバイザーが交渉などM&Aを徹底サポートします。
無料相談は随時受け付けておりますので、TOBについてなどM&Aについてお悩みの際は、M&A総合研究所までお気軽にご相談ください。
まとめ

本記事では、TOBが不成立となった事例やディスカウントTOBの事例をご紹介してきました。
TOBとは、買い手が買い集めたい株式の数や価格、期間などを公開し、対象の株主から買い集める方法を指します。
【今回紹介したTOBの事例】
- ドン・キホーテからオリジン東秀への不成立TOB
- 富士通からソレキアへの不成立TOB
- 夢真ホールディングスから日本技術開発への不成立TOB
- ベインキャピタルと廣済堂経営陣による不成立TOB
- 王子製紙から北越製紙への不成立TOB
- スティール・パートナーズから明星食品への不成立TOB
- TBIホールディングスとホリイフードサービスのディスカウントTOB
- RIZAPグループとジーンズメイトのディスカウントTOB
- 三菱商事と三菱自動車工業のディスカウントTOB
- 三井化学とアークのディスカウントTOB
M&A・事業承継のご相談なら24時間対応のM&A総合研究所
M&A・事業承継のご相談は成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A総合研究所にご相談ください。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴
- 譲渡企業様完全成功報酬!
- 最短43日、平均7.2ヶ月のスピード成約(2025年9月期実績)
- 上場の信頼感と豊富な実績
- 譲受企業専門部署による強いマッチング力
M&A総合研究所は、M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。
また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。
相談も無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたにおすすめの記事

M&Aとは?メリット・手法・最新動向を専門家がわかりやすく徹底解説
M&Aは事業拡大や事業承継の有効な手段です。本記事ではM&Aの基礎知識から、2025年以降の最新動向、手法、メリット・デメリット、成功させるためのポイントまで、専門家が分かりやす...

買収とは?用語の意味やメリット・デメリット、M&A手法、買収防衛策も解説
買収には、友好的買収と敵対的買収とがあります。また、買収に用いられるM&Aスキーム(手法)は実にさまざまです。本記事では、買収の意味や行われる目的、メリット・デメリット、買収のプロセスや...

現在価値とは?計算方法や割引率、キャッシュフローとの関係をわかりやすく解説
M&Aや投資の意思決定するうえでは、今後得られる利益の現時点での価値を表す指標「現在価値」についての理解が必要です。今の記事では、現在価値とはどのようなものか、計算方法や割引率、キャッシ...

株価算定方法とは?非上場企業の活用場面、必要費用、手続きの流れを解説
株価算定方法は多くの種類があり、それぞれ活用する場面や特徴が異なります。この記事では、マーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチといった株価算定方法の種類、株価算定のプロセス、株...

赤字になったら会社はつぶれる?赤字経営のメリット・デメリット、赤字決算について解説
法人税を節税するために、赤字経営をわざと行う会社も存在します。しかし、会社は赤字だからといって、必ず倒産する訳ではありません。逆に黒字でも倒産するリスクがあります。赤字経営のメリット・デメリット...
関連する記事
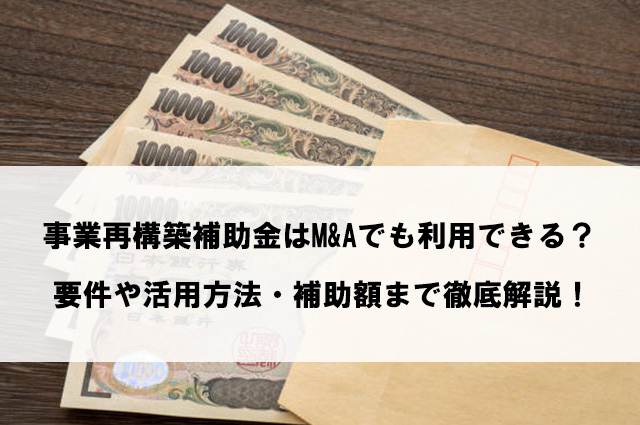
事業再構築補助金はM&Aでも利用できる?要件や活用方法・補助額まで徹底解説!
事業再構築補助金は要件を満たせば、中小企業や中堅企業に補助金を支給する制度です。中にはM&Aを実施するときに制度を利用する企業も存在します。この記事ではM&Aを実施しても事業再構...

DDSとは?DESとの違いや手順・活用方法・メリット・デメリットまで解説!
企業再建手法の1つとして注目されているDDS。そんなDDSとよく似た言葉にDESがありますが、それぞれの違いは何なのかを本記事で解説していきます。またDDSを実施する手順や活用方法、メリットやデ...

CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)とは?メリット・デメリットを解説!
ベンチャー企業へ投資をするCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)。VC(ベンチャーキャピタル)と混同されがちなCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)とは何なのか、活用するメリット・デメリ...

エンジェル投資家について徹底解説!メリットやデメリット・探し方は?
企業がイグジット(上場、ハイバリエーションでの売却)をした際のキャピタルゲインを目的とした投資を行うエンジェル投資家。返済義務がない投資をメインとしているエンジェル投資家について知らない人も多い...

シード期とは?定義やスタートアップの資金調達方法・成功のポイントを解説!
成長していく過程においてIPOやM&Aを活用することも重要ですが、具体的にどのようなポイントを抑えれば良いのでしょうか。 この記事では、シード期の定義やスタートアップの資金調達方法・成...

M&Aにおけるエスクローの意味とは?メリット・デメリットについて紹介!
日本のM&Aでは、活用されているケースは少ないとされている仲介サービス「エスクロー」があります。海外では多く活用されていますが、この「エスクロー」とはどういう意味なのでしょうか。ここでは...

投資銀行のM&Aにおける役割とは?部門ごとの業務内容や違いを解説!
投資銀行は銀行の一種ではないと聞くと、驚かれる方が多いかもしれません。投資銀行は、銀行業ではなく証券業に分類されます。本記事では、投資銀行の概要、投資銀行がM&Aにおける役割、投資銀行の4大業務...

スケールメリットが経営に与える効果は?意味や仕組みを具体例に徹底解説!
スケールメリットとは、同種の業種やサービスが多く集まることで単体よりも大きな成果を生み出せることです。会社経営を行う際、不必要な経費を活用しているケースが多いです。このような課題を解決できるスケ...

株式分割とは何?仕組みやメリット・デメリットなどをわかりやすく解説!
株式分割とは、1株をいくつかに分割して、発行済みの株式枚数を増やすことです。株式分割には企業側、投資家側にメリット・デメリットが存在します。理解していないとトラブルに発展する可能性があります。そ...


































立命館大学卒業後、地方銀行にて中堅中小企業を担当。ファイナンス、ビジネスマッチング等に従事した後、本部専門部署にて事業承継支援を専門として実績を積む。
その後、大手M&A仲介会社において、事業承継や戦略的な成長を目的としたM&Aを業種・規模問わず、多数成約に導く。
M&A総合研究所では、製造業や建設業、不動産業など幅広い業種を担当。