M&Aとは?意味や動向とM&Aを行う目的・メリットなどをわかりやすく解説!
2022年6月6日更新資金調達
第三者割当増資の手続きとは?メリット、契約書や取締役会についても解説
第三者割当増資とは、第三者に新株を割り当てて発行する行為をさします。会社が新たに資本金を得るための手段の1つですが、株主募集の条件決定から登記申請までさまざまな手続きが必要です。今回は、第三者割当増資の手続きやメリットについて幅広く解説します。
目次
第三者割当増資とは?

第三者割当増資とは、特定の第三者に新株を割り当てて発行する行為をさします。より具体的にいうと、会社が資本金を新たに獲得するために、特定の第三者に株式を割り当てる手続きのことです。基本的には、未上場の非公開中小企業により実施されています。
株式を割り当てる対象は、取引がある(もしくはこれからも良好な関係を保ちたいと考えている)企業や個人です。なお、第三者割当増資では、銀行から借り入れて返済が必要とされる借入金とは異なり、根本的に資本を増やせます。
また、新規の株主から見ても、自社に関係する会社利益のアップが期待できる点にメリットがあります。つまり第三者割当増資は、株式をパイプとして、より良い企業間の関係を築くための方法です。
実施する目的
第三者割当増資は、主に資金の調達を目的に実施されます。そのほか、M&Aを実施したい場合や、他社との関係性を強化したい場合などにも採用される手法です。
いずれの目的においても、第三者割当増資を行う際は、5段階の手続きを順番に進めなければなりません。この記事では、第三者割当増資に必要な手続きや、覚えておきたい注意点などを中心に説明します。
なお、この記事で取り上げるのは、一般的な第三者割当増資の手続きです。ケースによっては異なる手続きが必要な場合もあるため、状況に応じた手続きや手順を踏んで第三者割当増資を実施してください。
株式譲渡との相違点
第三者割当増資と株式譲渡の主な相違点は、取引後の株主構成に見られます。つまり、株式譲渡は現在の株主から株式を譲渡してもらう手法であるため、取引後に現在の株主が構成から抜けます。これに対して、第三者割当増資では、既存株主を維持したまま新株が発行されるため、現在の株主が構成に残るのです。
また、株式譲渡では株主間での取引であるために発行会社に影響を及ぼしませんが、第三者割当増資では新株を発行して発行会社に資金が入ります。以上の点から、経営権を移転させたいケースでは株式譲渡が採用される一方で、資金調達を行いたいケースでは第三者割当増資が採用される傾向にあるのです。
第三者割当増資はM&Aの手法の1つ
第三者割当増資は、M&Aの手法の1つと考えられています。もしもM&Aを見据えて第三者割当増資を検討している場合には、M&A総合研究所にご相談ください。
M&A総合研究所では、豊富な知識と経験を持つアドバイザーがM&Aをフルサポートいたします。料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。無料相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
第三者割当増資を行うメリット

第三者割当増資を行うメリットは、主に以下のとおりです。
- 資金を調達できる
- 引受先との関係を強固にできる
- 返済の義務を負わずに済む
- 税金が課されない
- 簡便な手続きで行える
それぞれのメリットを順番に詳しく紹介します。
①資金を調達できる
第三者割当増資では、株式を発行している会社が特定の第三者に向けて新株の権利を与えたうえで、その第三者に株式を購入してもらいます。中小企業が日頃より付き合いのある会社や金融機関に新株を購入してもらうケースが多く、これに由来して「縁故募集」とも呼ばれているのです。
つまり、株式を買い取ってくれる人に対して有利な条件で新株を買い取ってもらう手法だといえます。そのため、第三者割当増資は資金調達の手段として用いられています。
第三者割当増資では、同じように資金を会社に投入できる「公募増資」などの方法と比較しても手続きが少ないことから、資金調達をスムーズに進められる点がメリットです
公開会社における資金調達
公開会社の場合、公募増資を用いた資金調達が行われます。公募増資とは、不特定多数の投資家に向けて、新株を引き受ける権利を与える行為のことです。不特定多数の投資家が一斉に新株を購入することにより、多額の資金調達を実現できます。
とはいえ公開会社でも、特定の第三者に新株を購入してもらう第三者割当増資を採用するケースもあります。
②引受先との関係を強固にできる
第三者割当増資を行うと、引受先との関係を強固にできます。なぜなら、自社の株式を相手側に保有してもらうことで、お互いの関係性を明確化できるためです。
相手側からすると、株式の保有を通じて、配当金の受け取り・株式売却時の売却益などが目的として掲げられます。これに伴い、発行会社の規模を拡大するモチベーションが向上するために、発行会社との取引が増加する可能性があるのです。その結果として、引受先との関係が強固になると考えられています。
③返済の義務を負わずに済む
第三者割当増資を通じた資金調達では、返済義務を負わずに済みます。当然ながら、配当などによって株主に対する還元が求められるものの、社債や金融機関からの借入金などのように返済スケジュールが設定されないことから、より柔軟な資金調達が可能です。
④税金が課されない
第三者割当増資は、発行会社では新株を発行する一方で、引受先では資金を拠出して発行会社への払込を行う手法です。この仕組みの中で、株式の譲渡などは伴わないことから、税金は課されません。つまり、第三者割当増資では課税関係への配慮が不要であるため、余計な検討が必要ないのです。
⑤簡便な手続きで行える
特に公開会社では、取締役会決議において第三者割当の株式を発行できることから、手続きが非常に簡便です。
有利な発行価額で発行したケースでは株主総会の特別決議が求められるものの、それ以外のケースでは簡便な手続きで進められるため、短期間での資金調達が可能といえます。
第三者割当増資を行う際のデメリット

第三者割当増資を行う際には、以下のようなデメリットが問題となるケースがあります。
- 議決権の100%を取得できない
- 発行価格の妥当性を確認する必要
- 多額の資金を準備する必要
- 増税する可能性がある
- 希薄化というリスクがある
それぞれのデメリットを順番に詳しく紹介します。
①議決権の100%を取得できない
第三者割当増資を用いると、既存株主の株式が必ず残ってしまいます。そのため、議決権の100%の取得が行えません。株式のすべてを取得したい場合は他のM&A手法が求められます。
②発行価格の妥当性を確認する必要
第三者割当増資を用いるとき、株式の発行価額が発行法人の株式の時価と比べて高いのか安いのかが懸念されます。発行価額の方が高いケースでは問題にはなりませんが、発行価額の方が安いケースでは既存株主に不利益を及ぼすことから、既存株主を保護しなければなりません。
③多額の資金を準備する必要
株式譲渡と比べると、第三者割当増資では、株式の取得に多額の資金を準備しなければなりません。株式譲渡では、現時点における発行済株式数のうち、必要な割合を取得すれば実現できます。
これに対して、第三者割当増資では既存株主の株式数が存在し、その株式数をもとに必要な株式数が算出されることから、株式譲渡と比較すると多額の資金が必要です。
④増税する可能性がある
もともと企業では、資本金の額が1,000万円以上および1億円以上のラインを超えると増税するおそれがあります。具体的にいうと、資本金が1,000万円以上に達した場合、それまで消費税が免除されているならば、消費税が課されるために納税額が増加するのです。
また、資本金が1億円以上に達した場合、法人税の軽減税率が適用されなくなるほか、中小企業において優遇される税制も適用されなくなります。
以上のことから、第三者割当増資を用いる場合は、増資後の資本金額を注意しながら調達額を検討すると良いでしょう。
⑤希薄化というリスクがある
第三者割当増資を用いると、既存株主の保有割合が低下します。具体例を挙げると、発行済株式数が100株で株主1人の企業において第三者割当増資(100株追加で発行)を行ったケースを想定すると、既存株主の保有割合が100%から50%まで低下します。この現象を、株式の希薄化と呼んでいるのです。
株式の希薄化は、第三者割当増資に関連するさまざまな手続きによって引き起こされます。
- 有利発行
- 新株の発行
以上のことから、第三者割当増資を行う際は、希薄化を最小限に抑えるための対策が重要です。
第三者割当増資の手続き(全体の流れ)

第三者割当増資に関しては、会社法で細かく定められています。
- 第三者割当増資の手続きの方法
- それぞれのケースによる細かい手続き
- 新規に発行する株式に関して
会社法とは、会社の設立・運営・管理に関して定める法律です。第三者割当増資は、会社法に記載されている内容をもとに適切な手続きのもとで進める必要があります。
第三者割当増資の手続きは、基本的に5つのステップで進められます。
- 新株主募集の条件決定
- 募集事項の通知と株式の申し込み
- 株式の割当に関する決議
- 新株主による出資の履行
- 登記申請
まずは、第三者割当増資を実施する条件や、第三者となる個人や企業の決定基準などを決めます。そして条件などを通知したうえで、新株購入を希望する第三者が株式の申込手続きを行う流れです。
第三者割当増資を行う企業は、申込のあった中から株式を割り当てる相手や、割り当てる数などを決めます。その後、決められた割当数にもとづき、実際に個人や企業が出資を行って新株を購入する流れです。最後に、法務所に登記変更の申請手続きを行うと、手続きが完了します。
ここからは、それぞれの手続きを順番に詳しく紹介します。
①新株主募集の条件決定
まずは、第三者割当増資を行うための条件や第三者の選定基準などを決めます。
- 募集する株式の数
- 株式の金額と算出方法
- 現物出資の内容、または金額
- 振込期間・振込期日
- 増加する資本金・準備金に関する項目
上記以外にも、「申込の期日」「振り込みの取扱場所」なども決めます。第三者割当増資を用いる場合、取締役会が重要です。もともと取締役会を設置している会社であれば、第三者割当増資に関して取締役会で決議を取る必要があります。
このときに、上場している公開会社であれば、第三者割当増資の募集要項を取締役会において決定できます。その一方で、譲渡制限株式を発行している非公開会社の場合は、株主総会を行わなければなりません。
つまり、公開会社では取締役会で募集要項を決定できるため、よりスピーディーに第三者割当増資を実行可能です。なお、一部の事項のみを株主総会の特別決議で決定したうえで、具体的な内容の決定は取締役会への委任も認められています。
募集する株式の数
第三者割当増資に関して、株式の割当数や新規の発行株式数を決定します。具体的に、以下の2つの項目を決めるルールです。
- どのくらい株式を割り当てるのか
- 新規に発行する場合、新規にどのくらいの株式を発行するか
決定したからといって、その後に数を変更できないわけではありません。ステップ3の「株式の割当に関する決議」において実際の割当株式数を決定することから、募集事項よりも少なくなるケースは多く見られます。ここでは、目安となる株式数を決めておきましょう。
募集株式の金額、それに関する算定方法
前項の手続きを踏まえて、募集株式の金額を決定する流れです。ここでは、金額の算定方法も明確にしておく必要があります。
現物出資の内容及び金額
中には、株式の対価として得られるモノが現金ではなく現物出資であるケースもあります。その場合は、現物出資に関する内容や金額などを決めておく必要があります。
- 具体的な内容
- 価額
- それに関する算定方法
現物出資の対象は、基本的にその会社の財産に値するモノとされています。
振込期間、振込期日
第三者割当増資の対象となり株式の引受人となった第三者が、いつまでに対価を支払うのか決定します。もしも申込開始後に期間の延長や期日の変更がある場合は、期間や期日を再設定する必要があります。
すでに1人でも株主の申し込みがあった場合は、同意を得たうえで変更しなければなりません。
増加する資本金、準備金に関する事項
新株を発行する場合、増加する基本金や準備金に関する事項の決定が必須です。第三者割当増資によって振り込みや給付を受けた場合、総額の2分の1を超えたならば準備金の資本計上に関する手続きが求められます。
なお、新株を発行せずに発行済み株式を使用する場合、資本金が増加しないことが明らかであるため、手続きは不要です。
②募集事項の通知と株式の申し込み
次に、第三者割当増資の対象となる人物・企業に、ステップ1で決定した事項を通知する手続きを行います。 ここでは、募集事項・内容のほかにも、以下のような情報を通知するルールです。
- 株式の商号
- 申込期日
- 振り込みの取扱場所
これらの決定事項を承認した企業や個人が、第三者割当増資の対象者です。その後、第三者割当増資の対象者が期日までに株式の申込手続きを実施します。
- 氏名
- 住居地
- 引き受ける予定の株式数
上記の事項が記載された申込書を、第三者割当増資を行う会社に提出すれば、申し込みが完了します。
③株式の割当に関する決議
会社は、払込の期日や期間の初日の2週間前までに、割り当てる株式数や金額を通知する必要があります。そのため、第三者割当増資を検討している会社は、申込を集計したうえで、株式を割り当てる人物・企業のほか、株式の割当数を決定する手続きを遂行しなければなりません。
上記の手続きは、基本的に株主特別会議で決定されます。このときに、実際に割り当てる株式の数は、募集事項より少なくなっても問題ありません。ただし、会社の定款に特別定められている事項があれば、これに沿って決定します。なお、取締役会が設置されている会社では、取締役会の決議が優先されるルールです。
募集事項を決定する機関と本会議を行う機関が同じである場合、事前に割当会議を実施することが可能です。また、第三者割当増資の実施に際して、新株主候補がすべてを引き受ける場合、申込や割当行為などは不要です。その代わりに、「総数引受契約」と呼ばれる契約を締結します。
④新株主による出資の履行
新株主の出資方法には、以下の2つが存在します。
- 金銭
- 現物出資
金銭の場合は決められた金額を振り込むのみで済みますが、現物出資の場合は事前に裁判所の調査が必要な場合もあります。
金銭の場合
金銭で受け取る場合は、第三者割当増資の対象として決定された企業・人物が、期日までに株主の対価として設定された全額を支払います。
現物出資の場合
現物出資の場合は、対象の財産を期日までに会社へ引き渡します。このとき、引き渡す財産が株式の対価として妥当であるかどうか調査するために裁判所へ依頼するルールです。
ただし、以下の5つのいずれかに該当するケースでは、裁判所の調査は不要です。
- すべての現物出資に対して、引受人に当たる人物または企業に割り当てる株式総数が、第三者割当増資直前に発行された発行済株式の総数の10分の1
- すべての現物出資に対して、募集事項に定められた価額が50万円以下
- 株式の公開買い付け等に係る契約における価額よりも、募集事項に定められた現物出資の価額が低い
- 弁護士、弁護士法人、公認会計士、税理士、税理士法人のいずれかに、現物出資が対価として妥当であると事前に証明を受けている
- 該当する現物出資の財産が弁済期日到来済みの金銭債務であり、かつ募集事項決定の際に定められた当該金銭債務の価額が会社の負債の帳簿価額以下である
上記の場合は、裁判所の調査がなくても、対価として現物出資が認められています。
⑤登記申請
払込期間内(または払込期日から2週間以内)に、法務局において登記の変更申請手続きを行わなければなりません。具体的には、以下2つの手続きが必要です。
- 登記免許税の支払い
- 必要となる書類の提出
ぞれぞれの手続きを詳しく紹介します。
登記免許税の支払い
登記の変更申請手続きをする際は、登記免許税を支払います。登録免許税とは、登記手続きのとき国に納めなければならない税金のことです。登記の対象によって、登記免許税の金額は異なります。
募集株式発行の登記において支払う金額は、第三者割当増資によって増加する資本金の0.7%と設定されています。例外として、増加する資本金に0.7%を乗じた額が3万円以下ならば、3万円を支払うルールです。
必要書類の提出
添付書類はケースによって異なるものの、一般的には4つの書類を提出します。
- 株主総会と取締役会の議事録
- 株式の申込書
- 払込がされたと証明できる証明書
- 資本金の額の計上に関する証明書
また、第三者割当増資の対象となった人物や企業は、以下の基準で株主となる日が決定します。
- 払込期日を定めた場合:払込期日
- 払込期間を定めた場合:払込期間内で、出資を履行した日
第三者割当増資が株価にもたらす影響

第三者割当増資を用いる場合、株価が上昇するケースと下落するケースの双方が見られます。これは株価に見られる影響であることから、基本的には上場会社で生じる現象です。本章では、株価に与える影響をそれぞれの場合に分けて紹介します。
株価が上昇するケース
第三者割当増資に伴い株価が上昇するケースは、主に以下のとおりです。
- 事業の成長が期待されるケース
- 引受先との間でシナジー効果の獲得が見込まれるケース
- 上場廃止などネガティブな懸念が排除できたケース
- 潜在能力を秘めた事業計画を推進する会社への増資を行うケース
以上をまとめると、市場が第三者割当増資に対してポジティブな判断を下した場合、株価は上昇する傾向にあります。
株価が下落するケース
第三者割当増資に伴い株価が下落するケースは、主に以下のとおりです。
- 株式の希薄化を招くケース
- ネガティブな背景のもとで増資を行うケース
- 株式の発行が有利発行であるケース
つまり、第三者割当増資に対して市場がネガティブな判断を下す場合、株価は下落する傾向にあります。
第三者割当増資における株価算出の方法

第三者割当増資時の株価を算定する際は、一般的なM&A手法と同様に、以下3種類の手法が用いられます。
- コストアプローチ
- マーケットアプローチ
- インカムアプローチ
それぞれの手法に見られる特徴を順番に紹介します。
①コストアプローチ
コストアプローチは、企業における純資産の時価評価額などをもとに株主資本価値を算定する評価手法です。評価対象企業を構築するために発生するコストに着目して、企業価値を評価します。
コストアプローチでは、評価対象会社の純資産をもとに評価することから、対象企業の株価を容易に評価しやすいです。ただし、過去からの蓄積が反映された純資産をもとに純資産を評価するため、将来の収益を一切織り込まない点に注意が必要とされます。
また、取引の記帳が誤っている場合は適切に評価できない点もデメリットです。
②マーケットアプローチ
マーケットアプローチは、比較対象となる企業や業界をもとに企業価値を評価する手法です。評価対象企業の決算書などの数値に係数を乗じて価値を評価します。
マーケットアプローチでは、市場株価をもとに対象会社の株価を評価することから、客観的かつ公正に評価できます。その一方で、市場株価が一時的に異常値を示しているケースや、業種が類似する上場会社が存在しないケースなどでは、対象企業の株価を適切に評価できない点がデメリットです。
③インカムアプローチ
インカムアプローチは、企業の事業計画をもとにキャッシュフローの予測値から価値を評価する手法です。インカム(収入)にもとづいた企業価値評価の手法であり、将来的に得られるキャッシュフローや利益などの指標を用いて企業価値を算定します。
インカムアプローチでは、対象企業の利益・キャッシュフローから求めることから、対象企業ならではの収益力などを反映させられます。また、さまざまなシナリオや変動要素などシミュレーションできるため、柔軟な評価を行える点がメリットです。
その一方で、対象企業が自社で将来の予測を作成することから、主観的な要素が織り込まれるために恣意性の排除が難しい点にデメリットがあります。
第三者割当増資における注意点

第三者割当増資にて新しく株式を発行する場合、以下の点に注意が必要です。
- 有利発行の手続き
- 発行可能株式総数を確認する
第三者割当増資を行う際に起こり得る注意点を順番に紹介します。
有利発行の手続き
会社法では、有利発行に関しても定められています。有利発行とは、新規に発行した株式を時価よりも低い金額(買い手に有利な金額)で発行する行為です。新規に株式を発行して第三者割当増資を行う際は、注意しなければなりません。
なお上場企業では、日本証券業協会に沿って、取締役会の議決日の直前日株価に0.9をかけた金額以上であれば、原則として有利発行にならないと考えられています。
発行可能株式を確認する
会社が発行できる新株の数にも制限があるため、第三者割当増資で新しく株式を発行する際には注意する必要があります。
- 発行できる新規の株式数=発行可能株式数ー発行済みの株式数
上記のとおり発行できる新規株式数は、発行可能株式数と発行済みの株式数から影響を受けます。そのため、事前に発行可能株式総数を確認したうえで、新規に発行する株式を決めると良いでしょう。
第三者割当増資の契約書

第三者割当増資を行う際は、当事会社同士で「総数引受契約書」を作成します。「総数引受契約」とは、募集株式の引き受けを行う者が、そのすべてを引き受けることを証する契約です。
第三者割当増資における総数引受契約書には、株式を引き受ける者や株式数などが明記されます。そのため、「募集事項の通知と株式の申込」や、「株式の割当に関する決議」などの手続きが不要です。
つまり、総数引受契約書を作成すれば、第三者割当増資の手続きを大幅に省略できるため、当日中の増資実行につなげられます。
譲渡制限株式を用いて第三者割当増資を行う場合
第三者割当増資を行う際の株式が譲渡制限株式である場合、譲渡を行うために株主総会で特別決議を得る必要があります。
したがって、総数引受契約書を作成したうえで第三者割当増資により当日中の増資を行う場合は、当日中に株主総会を開催する必要があるため注意が必要です。
インターネット上で取得したひな型を利用する場合
総数引受契約書の作成に際して、インターネット上で取得したひな型を利用する場合は注意が必要です。
ひな型の使用自体に問題はありませんが、安易に流用すると実際に行う第三者割当増資の内容と異なる契約を締結してしまうリスクがあります。そのため、総数引受契約書を作成する際は、弁護士など専門家のチェックを受けると良いでしょう。
第三者割当増資における会計処理

本章では、第三者割当増資の会計処理における注意ポイントを、買い手側・売り手側ごとに取り上げます。
買い手側の会計処理
買い手側からすると、第三者割当増資を用いたM&Aの会計処理は、株式譲渡を採用するケースと同様です。なぜなら、費用の支払先に違いはあるものの、費用を支払って株式を取得する手法であることに変わりはないためです。
売り手側の会計処理
株式譲渡では売り手企業自体ではなく、売り手企業の株主に会計処理が求められます。その一方で、第三者割当増資では、売手企業自体で会計処理が必要です。売り手側からすると、あくまでも増資であるため、通常の増資と同様に会計処理を行います。
このときは新株を発行しますが、新株発行に要した費用は「新株発行費」とされて、以下の会計処理から選択できます。
- 新株発行費として資産に計上し、3年以内に均等額以上を償却する
- 一時の経費として処理する
第三者割当増資の最新事例

本章では、第三者割当増資の最新事例として以下の3件を取り上げます。
- オープンクラウドとマイナビによる第三者割当増資
- 大塚家具による第三者割当増資
- ユーザベースによる第三者割当増資
それぞれの事例を順番に詳しく紹介します。
①オープンクラウドとマイナビによる第三者割当増資
2020年5月、オープンクラウドとマイナビは、マイナビおよび「みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合」に対して、第三者割当による新株式の発行を行うと発表しました。
本件M&Aは、飲食業界と人材紹介業を手掛けているマイナビとの提携において、将来的に事業を展開する際にお互いの事業拡大を図る目的で実施されます。
②大塚家具による第三者割当増資
2019年12月、大塚家具はヤマダ電機に対して第三者割当増資により株式と新株予約権を発行しました。これにより、ヤマダ電機は大塚家具を子会社化しています。
本件M&Aによりヤマダ電機では、インテリアに強みを持つ大塚家具との資本提携を通じて、住空間におけるトータルコーディネート・坂路の拡大に伴う競争力の強化を図っています。
③ユーザベースによる第三者割当増資
2019年12月、ユーザベースは東京放送ホールディングスとの間で資本業務を提携する目的のもとで、第三者割当増資を用いて資金調達を実施しました。
本件M&Aにより、双方の強みを掛け合わせて5G時代を見据えながら、日本だけでなく海外も含めて若年層に支持されるコンテンツの配信やメディア展開が図られています。
第三者割当増資によるM&Aとは

「増資」の名称が付いていることから、イメージできない経営者の方もいますが、第三者割当増資は広義のM&A手法の1つとして考えられています。最後に、第三者割当増資によるM&Aを紹介します。
M&Aとして行われる第三者割当増資
M&Aとして行われる第三者割当増資は、買い手となる会社に新株を引き受ける権利を付与する点で、株式譲渡のスキームに似ています。株式譲渡とは、保有する株式を買い手の会社に譲渡することで、会社の経営権を移譲する方法です。
第三者割当増資では、買い手となる会社が引き受ける株式を経営権が獲得できる分の株数にしておくことで、経営権を買い手となる会社に移譲できます。ただし、株式譲渡と比べると複雑な方法です。
とはいえ、株式を購入する際の価格などを事前に取り決めて行うため、買い手となる会社とコンセンサスを取りやすい手法です。売り手となる会社にも、第三者割当増資はメリットのある手法だといえます。
第三者割当増資は、株式譲渡と同じように株式を購入してもらう方法であるため、売り手となる会社は売却益をそのまま資金として獲得可能です。獲得した資金を事業や運転資金に投入できるため、会社の成長にもつながります。
第三者割当増資によるM&Aの注意点
株式譲渡は募集要項に関する細かい決定や登記のようなプロセスが不要であるため、第三者割当増資よりもスピーディーに実行できます。つまり、第三者割当増資と株式譲渡では、それぞれM&Aが成立するまでに要する時間が異なる点が特徴的です。
そのほかにも、第三者割当増資によるM&Aでは、株式譲渡とは異なるデメリットがあるため注意が必要です。
- 手間や時間がかかる
- コストがかかる
- 株価に影響する
- 株主にとっては希薄化により損失のリスクがある
第三者割当増資の手続きまとめ

第三者割当増資の手続きは、本記事で取り上げた5つのステップで行われます。資金調達のほかにも、新株主と良好な関係を築ける点も第三者割当増資のメリットです。とはいえ、第三者割当増資を行った後も、信頼を維持するような経営を推進しなければなりません。
資本金が増えたからといって安心するのでなく、出資に見合った成果(利益)を上げることが必要不可欠です。また、登記の変更や出資に関する具体的な内容を十分に決定しておくことも、成功のカギを握っています。本記事の要点は、以下のとおりです。
◯第三者割当増資とは?
→会社が資本金を新たに獲得するために、特定の第三者に株式を割り当てる手続き
◯第三者割当増資を行うメリット
→資金を調達できる
→引受先との関係を強固にできる
→返済の義務を負わずに済む
→税金が課されない
→簡便な手続きで行える
◯第三者割当増資を行う際のデメリット
→議決権の100%を取得できない
→発行価格の妥当性を確認する必要
→多額の資金を準備する必要
→増税する可能性がある
→希薄化というリスクがある
◯第三者割当増資の手続き(全体の流れ)
→新株主募集の条件決定
→募集事項の通知と株式の申し込み
→株式の割当に関する決議
→新株主による出資の履行
→登記申請
◯第三者割当増資における株価算出の方法
→コストアプローチ
→マーケットアプローチ
→インカムアプローチ
M&A・事業承継のご相談なら24時間対応のM&A総合研究所
M&A・事業承継のご相談は成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A総合研究所にご相談ください。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴
- 譲渡企業様完全成功報酬!
- 最短43日、平均7.2ヶ月のスピード成約(2025年9月期実績)
- 上場の信頼感と豊富な実績
- 譲受企業専門部署による強いマッチング力
M&A総合研究所は、M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。
また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。
相談も無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたにおすすめの記事

M&Aとは?意味や動向とM&Aを行う目的・メリットなどをわかりやすく解説!
近年はM&Aが経営戦略として注目されており、実施件数も年々増加しています。M&Aの特徴はそれぞれ異なるため、自社の目的にあった手法を選択することが重要です。この記事では、M&am...

買収とは?用語の意味やメリット・デメリット、M&A手法、買収防衛策も解説
買収には、友好的買収と敵対的買収とがあります。また、買収に用いられるM&Aスキーム(手法)は実にさまざまです。本記事では、買収の意味や行われる目的、メリット・デメリット、買収のプロセスや...

現在価値とは?計算方法や割引率、キャッシュフローとの関係をわかりやすく解説
M&Aや投資の意思決定するうえでは、今後得られる利益の現時点での価値を表す指標「現在価値」についての理解が必要です。今の記事では、現在価値とはどのようなものか、計算方法や割引率、キャッシ...

株価算定方法とは?非上場企業の活用場面、必要費用、手続きの流れを解説
株価算定方法は多くの種類があり、それぞれ活用する場面や特徴が異なります。この記事では、マーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチといった株価算定方法の種類、株価算定のプロセス、株...

赤字になったら会社はつぶれる?赤字経営のメリット・デメリット、赤字決算について解説
法人税を節税するために、赤字経営をわざと行う会社も存在します。しかし、会社は赤字だからといって、必ず倒産する訳ではありません。逆に黒字でも倒産するリスクがあります。赤字経営のメリット・デメリット...
関連する記事
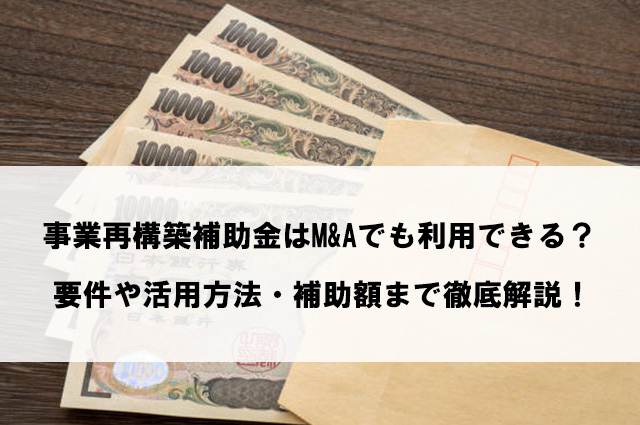
事業再構築補助金はM&Aでも利用できる?要件や活用方法・補助額まで徹底解説!
事業再構築補助金は要件を満たせば、中小企業や中堅企業に補助金を支給する制度です。中にはM&Aを実施するときに制度を利用する企業も存在します。この記事ではM&Aを実施しても事業再構...

DDSとは?DESとの違いや手順・活用方法・メリット・デメリットまで解説!
企業再建手法の1つとして注目されているDDS。そんなDDSとよく似た言葉にDESがありますが、それぞれの違いは何なのかを本記事で解説していきます。またDDSを実施する手順や活用方法、メリットやデ...

CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)とは?メリット・デメリットを解説!
ベンチャー企業へ投資をするCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)。VC(ベンチャーキャピタル)と混同されがちなCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)とは何なのか、活用するメリット・デメリ...

エンジェル投資家について徹底解説!メリットやデメリット・探し方は?
企業がイグジット(上場、ハイバリエーションでの売却)をした際のキャピタルゲインを目的とした投資を行うエンジェル投資家。返済義務がない投資をメインとしているエンジェル投資家について知らない人も多い...

シード期とは?定義やスタートアップの資金調達方法・成功のポイントを解説!
成長していく過程においてIPOやM&Aを活用することも重要ですが、具体的にどのようなポイントを抑えれば良いのでしょうか。 この記事では、シード期の定義やスタートアップの資金調達方法・成...

M&Aにおけるエスクローの意味とは?メリット・デメリットについて紹介!
日本のM&Aでは、活用されているケースは少ないとされている仲介サービス「エスクロー」があります。海外では多く活用されていますが、この「エスクロー」とはどういう意味なのでしょうか。ここでは...

投資銀行のM&Aにおける役割とは?部門ごとの業務内容や違いを解説!
投資銀行は銀行の一種ではないと聞くと、驚かれる方が多いかもしれません。投資銀行は、銀行業ではなく証券業に分類されます。本記事では、投資銀行の概要、投資銀行がM&Aにおける役割、投資銀行の4大業務...

スケールメリットが経営に与える効果は?意味や仕組みを具体例に徹底解説!
スケールメリットとは、同種の業種やサービスが多く集まることで単体よりも大きな成果を生み出せることです。会社経営を行う際、不必要な経費を活用しているケースが多いです。このような課題を解決できるスケ...

株式分割とは何?仕組みやメリット・デメリットなどをわかりやすく解説!
株式分割とは、1株をいくつかに分割して、発行済みの株式枚数を増やすことです。株式分割には企業側、投資家側にメリット・デメリットが存在します。理解していないとトラブルに発展する可能性があります。そ...


























立命館大学卒業後、地方銀行にて中堅中小企業を担当。ファイナンス、ビジネスマッチング等に従事した後、本部専門部署にて事業承継支援を専門として実績を積む。
その後、大手M&A仲介会社において、事業承継や戦略的な成長を目的としたM&Aを業種・規模問わず、多数成約に導く。
M&A総合研究所では、製造業や建設業、不動産業など幅広い業種を担当。