M&Aとは?メリット・手法・最新動向を専門家がわかりやすく徹底解説
2025年10月27日更新資金調達
商工会議所でM&A相談は可能?業務内容やメリット、商工会との違いも解説
商工会議所は、M&Aや事業承継など経営の悩みを相談できる公的経済団体です。本記事では、商工会議所の役割や業務内容、加入メリット、商工会との違いをわかりやすく解説します。
目次
商工会議所とは?その定義と3つの主な役割
商工会議所とは、商工業者で構成される自由会員制の公共経済団体です。地域の会社経営者、個人事業主が集まるための場所ともいえます。したがって、営利目的で運営している機関ではありません。しかし、商工会議所はただの寄り合いではなく、特別認可法人です。
法律に基づいて設立されているため、法律が改変されない限り存続する組織でもあります。つまり、商工会議所は、国や自治体のバックアップを受けている組織なのです。役所とは違いますが、役所が行うような仕事も請け負うため、公的な機関と位置付けされています。
そして、経営者は、商工会議所の会員になれば、経営に役立つさまざまなサービスを受けることが可能です。ただし、商工会議所の会員になれる事業には制限があります。消費者金融・風俗・病院などの事業主は、商工会議所の会員になれません。
なお、商工会議所の会員にならずとも、商工会議所で創業などについて相談することは可能です。
商工会議所の役割
商工会議所の役割は大きく3つあります。
- 地域経済社会の牽引
- 活力ある地域づくりの実現
- 中小企業のバックアップ
商工会議所は、管轄地域の経済を盛り上げるために存在しています。そして、そのためには中小企業のバックアップが不可欠と考え、力を入れているのです。具体的には、無料でのセミナー開催や経営相談などを随時、行っています。
商工会議所と商工会の違い
名称が似ていますが、商工会議所と商工会は別の組織です。管轄省庁や設立の基準が異なります。しかし実際には、商工会も商工会議所と類似する業務を行っており、同じように国や自治体がバックにいる公的機関であるため、区別がつきにくい存在です。
わかりやすい相違点としては、主に市および特別区に設置されるのが商工会議所です。一方、商工会は主に町村に設置されるため規模は小さい傾向にありますが、その分、数が多いのが特徴です。実際、2024年4月時点で全国に515ある商工会議所に対し、商工会は1,600以上組織されています。
また、組織の規模の違いは会員の事業規模にも反映されており、商工会議所の会員は小規模事業者から大企業までの会員が加入していますが、商工会の会員はほとんどが小規模事業者です。
商工会議所の歴史・設立の経緯
商工会議所の前身である商業会議所が設立されたのは、1878(明治11)年です。東京・大阪・神戸の3カ所に設立されました。明治維新を迎えた日本では、先進諸国のさまざまな制度を導入しており、商工会議所制度もその一環です。
ちなみに、東京商業会議所の初代会頭は渋沢栄一でした。その当時の諸外国の商工会議所制度は、英米系と仏独系の2つに大別されます。その最大の違いは、英米系は任意加入制であるのに対し、仏独系は強制加入制である点です。
日本では、現在と同じく当時も任意加入制で発足していますから、英米系の商工会議所制度を取り入れたということになります。その後、法改正などとともに、何度か名称や組織は変遷しました。
そして、現在の商工会議所制度か確立したのは、第2次世界大戦後の1954(昭和29)年に商工会議所法が制定されたときからです。
商工会議所の根拠となる「商工会議所法」
商工会議所法とは、商工会議所を成立させている法律です。商工会議所法では、商工会議所にとって必要な事柄や運営の目的などが定められており、それに基づいて商工会議所は運営されています。
商工会議所法の代表的な条文は、以下のとおりです。
- 特定の個人、法人、その他の利益を目的に事業を行わない(第4条)
- 特定の政党のために利用しない(第4条)
- 商工会議所は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする(第6条)
これらの条文は、商工会議所が公的かつ中立的な機関であることを明確に示しています。この法律を知っておくことで、商工会議所が公正な立場で地域経済の発展に貢献する組織であることがより深く理解できます。
商工会議所の主な収入源
商工会議所は公的機関とはいえ役所ではありませんから、活動するための資金を得なければなりません。商工会議所の収入確保手段には、以下の3つがあります。
- 会費の徴収
- 事業の運営
- 補助金の獲得
①会費の徴収
日本商工会議所が公開している2023年度の収支計算書によると、会費収入は約7億5,000万円でした。また、事業収益全体(約102億円)に占める割合は約7.4%となっています。
②事業の運営
商工会議所では、各種ビジネス検定、講習会・研修会参加料、手帳・記章販売、GS1コード(商品識別システム)手数料、TOAS(情報共有OAシステム)登録料などの事業収入と、広告収入があります。2023年度は、約65億円で事業収益全体の約63.6%を占めており、活動の大きな柱となっています。
③補助金の獲得
商工会議所は、会員や事業者からの相談対応や経営指導を行っていることで、補助金収入も得ています。2023年度は、約24億円の補助金収入がありました。これは事業収益全体の約23.5%に相当します。
商工会議所の仕事・業務内容
商工会議所の仕事・業務内容についてまとめると、以下のようになります。
- 政策提言活動:国や自治体への意見具申
- 中小企業振興:研修やセミナーの開催、融資支援
- 地域振興:各地域に特化した情報サイトの運営
- 国際交流:企業の国際化を支援
- 検定試験:簿記検定など10数種類の検定実施
- 会員交流:会員の相互親睦を図る
- 産業振興(調査・研究):景気調査、各種事業の市場データ収集
- 情報化推進:各事業者のIT化実現のための支援
- 共済事業:生命保険・傷害保険に該当する共済制度の実施
- 広報活動:商工会議所活動のPR
これらの中から、会員である事業者向けに行われている以下の3つの活動について、その内容を説明します。
- 経営に関する相談
- 会員との交流
- 福利厚生の支援
なお、商工会議所の提供する融資・補助金、セミナーの詳細については後述します。
①経営に関する相談
商工会議所では経営に関する相談を受け付けており、会員でなくても利用可能です。専門の経営指導員が担当し、決算書などの重要書類を参照しながら経営に関する的確なアドバイスを受けられます。
また、商工会議所では、弁護士や税理士、社労士といった士業の専門家が相談を受ける窓口も活用可能です。必要があれば専門家が事業所に赴き、より直接的なアドバイアスや補助を依頼できます。商工会議所が行っているこれらの相談は全て無料です。
日常の経営問題はもちろん、事業承継の方向性やM&Aの初期検討といった悩みまで、幅広い相談に対応しています。地域のさまざまな企業と繋がりを持つ商工会議所ならではの視点で、経営戦略に悩む経営者にとって有益な情報提供が期待できます。
ただし、M&Aの検討であれば、最初から専門家であるM&A仲介会社に相談するのがおすすめです。仮にM&A仲介会社の選択にお困りの場合は、ぜひM&A総合研究所へご相談ください。
全国の中小企業のM&Aに数多く携わっているM&A総合研究所では、さまざまな業種・規模の豊富なM&A支援実績を持つアドバイザーが案件ごとに専任となり、相談時からクロージングまでM&Aを徹底サポートいたします。
また、通常は10カ月~1年以上かかるとされるM&Aを、最短3カ月でスピード成約する機動力もM&A総合研究所の強みです。料金体系は、成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」となっています(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。
随時、無料相談をお受けしておりますので、M&A・事業承継をご検討の際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
商工会議所でのM&A・事業承継相談
商工会議所は、後継者不在などに悩む中小企業にとって、M&Aや事業承継の第一歩を踏み出すための身近な相談先となります。ここでは、商工会議所に相談するメリットや注意点を解説します。
商工会議所にM&A相談するメリット
最大のメリットは、公的で中立的な立場から無料で相談に応じてくれる点です。特定のM&A仲介会社に偏ることなく、客観的なアドバイスが期待できます。また、地域のネットワークを活かし、地元の税理士や弁護士などの専門家を紹介してもらえる場合もあります。初期段階の漠然とした悩みでも気軽に相談できるのが魅力です。
商工会議所にM&A相談する際の注意点
商工会議所の職員はM&Aの専門家ではないため、具体的な交渉や契約手続き(クロージング)までを直接サポートすることはできません。あくまでも初期相談や情報提供、専門家への橋渡しが主な役割となります。本格的にM&Aを進める段階では、別途M&A仲介会社などの専門家と契約する必要があります。
M&A専門家との違いと使い分け
商工会議所は「何から始めればよいかわからない」という初期段階の相談に適しています。一方、M&A仲介会社は、具体的な相手探しから交渉、契約成立までを一貫してサポートする専門家集団です。まずは商工会議所で情報収集や基本的な相談を行い、M&Aの意思が固まったら専門の仲介会社に依頼するなど、フェーズに応じた使い分けが効果的です。
②会員との交流
商工会議所は、会員である経営者や事業主の交流を目的とするイベントを開催しています。イベントはビジネス交流会や賀詞交換会といったお堅いものから、ボーリング大会などのような娯楽ものなどさまざまです。
それぞれの商工会議所によって規模も内容も違うため、目的に合わせて参加するとよいでしょう。どのイベントも基本的に任意参加であり、無理に参加する必要はありません。
しかし、これらは経営者や個人事業主にとって貴重な交流の機会であり、異業種の経営者との人脈形成や情報交換を通じて、新たなビジネスチャンスが生まれる可能性も秘めています。
③福利厚生支援
商工会議所は、中小企業向けに福利厚生の支援もしています。通常、中小企業は大企業のような手厚い福利厚生を用意することは難しいものです。しかし、商工会議所では、会員向けに旅行ツアーの割引や施設利用券など多彩な福利厚生を提供しています。
商工会議所の融資
商工会議所の融資といっても、商工会議所が直接、お金を貸してくれるわけではありません。一例としては、商工会議所に相談し経営指導を受けることによって、金融機関からの融資が優遇されます。
また、商工会議所が信用保証協会や日本政策金融公庫、自治体や国と連携し、商工会議所会員向けの特例融資を受けられるためのサポートを行っているのです。そして、各商工会議所によって、具体的な融資支援の取り組み内容は異なります。
したがって、商工会議所に相談することで受けられる融資支援の具体的な内容は、それぞれの地域の商工会議所に確認しましょう。ここでは、全国共通の商工会議所の融資支援策である「マル経融資」について説明します。
マル経融資
マル経融資(小規模事業者経営改善資金)とは、国の政策金融機関である日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を実施する制度です(沖縄県の場合は沖縄振興開発金融公庫が実施)。具体的な融資内容は以下のようになっています。
- 融資限度額:2,000万円
- 返済期間A:運転資金は7年以内(据置期間1年以内)
- 返済期間B:設備資金は10年以内(据置期間2年以内)
- 保証人:不要
- 担保:不要
- 利率:情勢により変動(2024年5月15日現在の利率は1.40%)
このマル経融資が申し込める大前提として、商工会議所で6カ月以上の経営指導を受け、商工会議所会頭からの推薦を受ける必要があります。また、それ以外にも、以下の条件を満たしている事業者でなければ申し込み資格を得られません。
- 従業員が20人以下の法人・個人事業主
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業は除く)の場合は5人以下の法人・個人事業主
- 最近1年以上、商工会議所の地区内で事業を継続していること
- 所得税、法人税、事業税、都道府県民税などの税金を完納していること
- 日本政策金融公庫の融資非対象業種でないこと
なお、日本政策金融公庫の融資非対象業種は以下のとおりです。
- 競輪、競馬などの競争場や同競技団
- 場外馬券売場・場外車券売場
- 一部の風俗業
- パチンコホール
- ビンゴゲーム場・射的場
- 芸妓業
- 銀行業
- 協同組織金融業
- 信金業・クレジットカード業
- 補助的金融業
- 金融商品取引業・損害保険業・共済事業・少額短期保険業
- 郵政局・郵便業
- 取立業・集金業
- 社会保険事業団体
- 福祉事務所
- 更正保護事業
商工会議所の補助金

補助金や助成金は、融資と違って返済不要であることが大きな魅力です。ただし、それだけに条件や期間が限定され、審査も受けなければなりません。また、申し込みには準備も必要です。
商工会議所が行っている補助金制度としては、「小規模事業者持続化補助金」があります。これには2種類のタイプがあり、1つは定期的に行っている「一般型」です。もう一方は、社会・経済情勢の急激な悪化や甚大な自然災害が発生した場合などに臨時的に行われます。
一例としては、「災害対策型」、「コロナ特別対応型」などです。災害対策型の場合は、当然ながら被害を受けた地域限定の補助金助成になります。ここでは、小規模事業者持続化補助金の一般型について、内容を確認しておきましょう。
小規模事業者持続化補助金・一般型
小規模事業者持続化補助金・一般型の概要は以下のとおりです。
- 補助金額:原則上限50万円
- 補助金対象費用:販路開拓などに取り組む費用の3分の2まで
- 申し込み受付期間:公募開始後、通年において約4カ月ごとに締め切り
- 前提条件:地域の商工会・商工会議所の助言を受けて経営計画を作成し、その計画に基づいた費用であること
さらに詳しい条件を掲示します。
補助対象者
小規模事業者と一定の要件を満たした特定非営利活動法人が対象ですが、小規模事業者の具体的な条件は、業種によって以下のようになっています(マル経融資と同様)。
- 従業員数5人以下の宿泊・娯楽業を除いたサービス業者、商業者
- 従業員数20人以下の宿泊業者、娯楽業者、製造業者、その他の業者
対象事業の内容
対象事業とは、経営計画に基づいた生産性向上のための販路開拓の取り組み、または業務効率化の取り組みのことです。それぞれの具体例としては、以下のようなものがあります。
- 販路開拓:商品陳列用棚の購入、販促用チラシの作成・送付、新商品開発、展示会出展、店舗改装、ECサイト構築など
- 業務効率化:業務改善のための専門家コンサルティング、労務管理・倉庫管理・売上管理・経理・会計などのIT化など
補助対象経費
前項で掲示した各対象事業を経費の科目名に言い換えると、以下の経費が小規模事業者持続化補助金・一般型の対象経費となります。
- 機械装置等費
- 広報費
- 展示会等出展費
- 旅費
- 開発費
- 資料購入費
- 雑役務費
- 借料
- 専門家謝金
- 専門家旅費
- 設備処分費(補助対象経費総額の2分の1が上限)
- 委託費
- 外注費
なお、これら経費は、以下の3条件全てを満たしていることが必須です。
- 使用目的が事業遂行に必要と明確に特定できる
- 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了している
- 証拠資料などによって支払金額が確認できる
申請時の提出必要書類
小規模事業者持続化補助金・一般型に申し込みをする際は、以下の書類全てを用意しなければなりません。
- 地域の商工会議所が作成・発行した事業支援計画書
- 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書
- 経営計画書兼補助事業計画書①
- 補助事業計画書②(経費明細表・資金調達方法)
- 交付申請書
補助金交付後の義務
小規模事業者持続化補助金・一般型の申請が採択され、補助金を交付された場合には、以下の書類を定められた期日までに提出しなければなりません。
- 補助金を受けた事業の内容を報告する実績報告書
- 支出内容のわかる資料・書類
商工会議所のセミナー

商工会議所では、外部から講師を招いたセミナーや経営者、一般社員それぞれに向けた研修などを開催しています。商工会議所によっては、無料開催のセミナーや会員以外でも受講可能なものもあるのが特徴です。
また、有料のセミナーや研修でも、商工会議所の場合は、ほとんど実費負担だけですみます。経営者、社員ともに、必要な知識や情報、業務に関する新しい発想やノウハウなど得られる良い機会なので、大いに活用しましょう。
特に経営者や事業主が参加するセミナーであれば、ほかの経営者・事業主と交流を持つ場にすることも可能です。
商工会議所の加入メリット・デメリット

起業時などにおいて、商工会議所に会員として加入するかどうか悩むかもしれません。そこで、あらためて商工会議所に加入する場合のメリットとデメリットについて、まとめました。
加入のメリット
一般的に考えられる商工会議所加入後のメリットには、以下のようなものがあります。
- 経営の相談や助言が基本的に無料で得られる
- 会員限定サービスが受けられる(電子証明書発行割引、各種セミナーの特別待遇、損害賠償保障制度など)
- 交流会イベントなどで新たな人脈を持てる
- 福利厚生面の支援を受けられる
- マル経融資や小規模事業者持続化補助金申請時の補助・支援が受けられる
- 商工会議所が開催する展示会・商談会に参加できる
加入のデメリット
一概にデメリットと断じてしまうのは語弊があるかもしれませんが、商工会議所に加入する場合にちゅうちょする理由となるのが、費用が生じることです。商工会議所への加入時および加入後は、以下の費用がかかります。
- 入会費:法人3,000円、個人10,000円
- 年会費:15,000円~(資本金額に応じて会費は高くなる)
なお、商工会議所への入会費および年会費は、必要経費として損金算入ができます。また、どちらも消費税の対象費用ではありません。
商工会議所の会費と入会資格

商工会議所への入会時の費用については前項で触れましたが、その詳細と入会資格について掲示します。
東京商工会議所の会費
各地域の商工会議所によって会費の条件が異なっているため、ここでは東京商工会議所を例に具体内容を記載します。
- 入会費:3.000円
- 年会費:1万5.000円~30万円
東京商工会議所の会費は法人と団体で区分されていますが、金額に違いはありません。ただし、法人と団体では異なる条件が設けられており、その条件に応じて会費が変化します。
法人の場合は資本金によって会費が変動する規定になっており、資本金額500万円未満から100億円以上の間で段階ごとに会費が変わるのです。それに対して団体は、当該団体に従事している職員数が基準で会費が変わります。
具体的には、10人未満~2,000人以上の間で段階ごとに会費が変わる規定です。なお、会費は、毎年4~5月に指定された口座へ振り込まなければなりません。
東京商工会議所の入会資格
入会資格についても東京商工会議所の実例で掲示します。東京商工会議所の入会資格は「東京23区内で営業している」という条件のみです。したがって、東京23区内で営業していれば、法人、団体、個人事業主、外国法人でも入会できます。
これはほかの商工会議所も同様であり、基本的に入会したい商工会議所が管轄している地域で営業を行っていれば入会が可能です。また、東京商工会議所の趣旨に賛同していれば、この条件に該当しておらずとも特別会員という待遇で入会できる場合があります。
商工会議所への加入方法

商工会議所への加入は、いつでもすぐに加入できます。加入の手続きは、管轄の商工会議所へ行って申し込み用紙を提出するだけです。郵送での申し込みもできますが、どのようなサービスを受けられるか確認するためにも実際に足を運んだ方がよいでしょう。
加入手続きをする際には、法人印(個人事業主は認印)と銀行印が必要になります。申し込み用紙は商工会議所にあるので、その場で記入・捺印可能です。また、請求すれば、事前に用紙を郵送してもらえます。
商工会議所の加入率

日本商工会議所の発表によると、日本全体の商工会議所の会員数は122万(2021年3月現在)です。ただし、会員数に関して、それ以上の詳細な資料は公式に発表されていないため、加入率については推測の域を出ません。
一説によれば、地方では加入率50%超の地域もあれば、都市部では10~20%ともいわれています。こればかりは、実際に会員になってみないとわからない情報です。
商工会議所のまとめ

商工会議所とは、商工業者によって構成される公共経済団体です。商工会議所の主要な役割は以下の3つですが、経営者にとって商工会議所は、経営のアドバイスを得たり、融資・補助金の支援を得たりなど、ビジネスにおいて心強い存在といえます。
・地域経済社会の牽引
・活力ある地域づくりの実現
・中小企業のバックアップ
M&A・事業承継のご相談なら24時間対応のM&A総合研究所
M&A・事業承継のご相談は成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A総合研究所にご相談ください。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴
- 譲渡企業様完全成功報酬!
- 最短43日、平均7.2ヶ月のスピード成約(2025年9月期実績)
- 上場の信頼感と豊富な実績
- 譲受企業専門部署による強いマッチング力
M&A総合研究所は、M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。
また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。
相談も無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたにおすすめの記事

M&Aとは?メリット・手法・最新動向を専門家がわかりやすく徹底解説
M&Aは事業拡大や事業承継の有効な手段です。本記事ではM&Aの基礎知識から、2025年以降の最新動向、手法、メリット・デメリット、成功させるためのポイントまで、専門家が分かりやす...

買収とは?用語の意味やメリット・デメリット、M&A手法、買収防衛策も解説
買収には、友好的買収と敵対的買収とがあります。また、買収に用いられるM&Aスキーム(手法)は実にさまざまです。本記事では、買収の意味や行われる目的、メリット・デメリット、買収のプロセスや...

現在価値とは?計算方法や割引率、キャッシュフローとの関係をわかりやすく解説
M&Aや投資の意思決定するうえでは、今後得られる利益の現時点での価値を表す指標「現在価値」についての理解が必要です。今の記事では、現在価値とはどのようなものか、計算方法や割引率、キャッシ...

株価算定方法とは?非上場企業の活用場面、必要費用、手続きの流れを解説
株価算定方法は多くの種類があり、それぞれ活用する場面や特徴が異なります。この記事では、マーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチといった株価算定方法の種類、株価算定のプロセス、株...

赤字になったら会社はつぶれる?赤字経営のメリット・デメリット、赤字決算について解説
法人税を節税するために、赤字経営をわざと行う会社も存在します。しかし、会社は赤字だからといって、必ず倒産する訳ではありません。逆に黒字でも倒産するリスクがあります。赤字経営のメリット・デメリット...
関連する記事
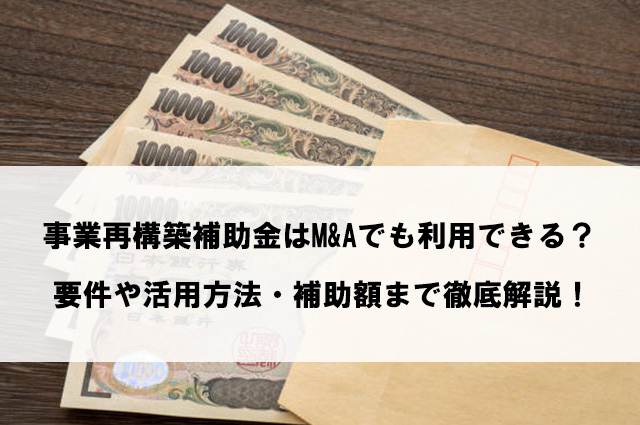
事業再構築補助金はM&Aでも利用できる?要件や活用方法・補助額まで徹底解説!
事業再構築補助金は要件を満たせば、中小企業や中堅企業に補助金を支給する制度です。中にはM&Aを実施するときに制度を利用する企業も存在します。この記事ではM&Aを実施しても事業再構...

DDSとは?DESとの違いや手順・活用方法・メリット・デメリットまで解説!
企業再建手法の1つとして注目されているDDS。そんなDDSとよく似た言葉にDESがありますが、それぞれの違いは何なのかを本記事で解説していきます。またDDSを実施する手順や活用方法、メリットやデ...

CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)とは?メリット・デメリットを解説!
ベンチャー企業へ投資をするCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)。VC(ベンチャーキャピタル)と混同されがちなCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)とは何なのか、活用するメリット・デメリ...

エンジェル投資家について徹底解説!メリットやデメリット・探し方は?
企業がイグジット(上場、ハイバリエーションでの売却)をした際のキャピタルゲインを目的とした投資を行うエンジェル投資家。返済義務がない投資をメインとしているエンジェル投資家について知らない人も多い...

シード期とは?定義やスタートアップの資金調達方法・成功のポイントを解説!
成長していく過程においてIPOやM&Aを活用することも重要ですが、具体的にどのようなポイントを抑えれば良いのでしょうか。 この記事では、シード期の定義やスタートアップの資金調達方法・成...

M&Aにおけるエスクローの意味とは?メリット・デメリットについて紹介!
日本のM&Aでは、活用されているケースは少ないとされている仲介サービス「エスクロー」があります。海外では多く活用されていますが、この「エスクロー」とはどういう意味なのでしょうか。ここでは...

投資銀行のM&Aにおける役割とは?部門ごとの業務内容や違いを解説!
投資銀行は銀行の一種ではないと聞くと、驚かれる方が多いかもしれません。投資銀行は、銀行業ではなく証券業に分類されます。本記事では、投資銀行の概要、投資銀行がM&Aにおける役割、投資銀行の4大業務...

スケールメリットが経営に与える効果は?意味や仕組みを具体例に徹底解説!
スケールメリットとは、同種の業種やサービスが多く集まることで単体よりも大きな成果を生み出せることです。会社経営を行う際、不必要な経費を活用しているケースが多いです。このような課題を解決できるスケ...

株式分割とは何?仕組みやメリット・デメリットなどをわかりやすく解説!
株式分割とは、1株をいくつかに分割して、発行済みの株式枚数を増やすことです。株式分割には企業側、投資家側にメリット・デメリットが存在します。理解していないとトラブルに発展する可能性があります。そ...
























立命館大学卒業後、地方銀行にて中堅中小企業を担当。ファイナンス、ビジネスマッチング等に従事した後、本部専門部署にて事業承継支援を専門として実績を積む。
その後、大手M&A仲介会社において、事業承継や戦略的な成長を目的としたM&Aを業種・規模問わず、多数成約に導く。
M&A総合研究所では、製造業や建設業、不動産業など幅広い業種を担当。