M&Aとは?メリット・手法・最新動向を専門家がわかりやすく徹底解説
2022年9月28日更新資金調達
新規事業に役立つ助成金・補助金とは?活用メリットも解説【2022年最新版】
新規事業において資金は重要であり、審査に通過すれば資金が得られる助成金・補助金は資金調達の有効的な手段です。今回は、新規事業に役立つ助成金や補助金の種類・注意点・申請手順・活用メリットなどについて解説するので、参考にしてください。
目次
新規事業で助成金・補助金を活用する背景

この章では、新規事業で助成金・補助金を活用する背景について見ていきましょう。
新規事業に必要な資金
新規事業を立ち上げたうえで維持していくには、資金が必要不可欠です。そもそも新規事業の立ち上げは、以下のさまざまな動機から実施されます。
- 現状の事業だけでは会社の成長が望めない
- 会社のさらなる発展を実現したい
最近は、大企業・中小企業にかかわらず新規事業の立ち上げを積極的に行っている会社が多いです。ここからは、「資金が必要となる理由」「個人による既存事業の買収」の2項目に分けて詳しく紹介します。
資金が必要となる理由
まず、新規事業の実行に資金が必要となる理由について取り上げます。以下の理由から「新規事業の立ち上げおよび維持は難しい」という認識が一般的です。
- 新規事業を立ち上げてもすぐに失敗してしまう
- 新規事業を立ち上げる段階にすら至らなかった
新規事業を立ち上げても、軌道に乗る可能性は非常に少ないです。そのため、ほとんどの新規事業は成功しないと考えられています。事業立ち上げのために新規事業開発チームを結成しても、運用コストが会社の負担になるケースは珍しくありません。
立ち上げた新規事業が多少の収益を挙げたとしても、新規事業の開発チームが抱える負債や出費で相殺されてしまえば、新規事業の維持は困難です。
以上のことから、新規事業を立ち上げて維持し成功につなげるためには、資金が必要不可欠といえます。
個人による既存事業の買収
最近は、新規事業の立ち上げのために、個人が既存事業をM&Aで買収するケースも見られます。これは、事業の買収によって、新規事業をスムーズに立ち上げられるためです。
しかし、M&Aを成功させるには、業界に関する知識だけでなく、財務・会計・税務・法律などの専門知識が求められます。
M&Aをご検討の際は、ぜひM&A総合研究所にお任せください。M&A総合研究所では豊富な知識と経験を持つM&Aアドバイザーが、案件をフルサポートいたします。
料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。相談料は無料となっておりますので、新規事業の立ち上げを目的とするM&Aの実施をご検討の際は、お気軽にお問い合わせください。
助成金・補助金とは?
最近は、新規事業や創業に利用できる助成金や補助金が増えており、これに伴い活用を検討する経営者も増加中です。ここでは、助成金と補助金の意味を押さえておきましょう。
- 助成金:一定の要件を達成した場合に申請して得られるお金
- 補助金:申請を行い、審査を通過した後に事業を実行して得られるお金
いずれも、国や地方公共団体などがお金を支給してくれる制度です。大きな違いは、事業を実行するタイミングにあります。助成金は要件を満たせば申請可能ですが、補助金は申請および審査通過の後に事業を開始する仕組みです。
助成金と補助金の共通かつ最大のメリットは、一定以上のまとまったお金を返済不要で得られる点にあります。
融資との違い
ひとことに融資といっても、最近では「金利が低い融資」や「新規事業向けの融資」など、さまざまな種類が存在します。たとえ低金利でも、返済不要な助成金・補助金などとは異なり、融資は負債であり返済する必要があるのです。
また、融資を受けるには、社会的な信用が必要不可欠です。そのため、ベンチャー企業などでは、銀行や信用金庫といった一般的な金融機関から融資を受けられないケースも珍しくありません。
こうした点を踏まえると、助成金や補助金は、新規事業を立ち上げるうえで融資よりも有効的な資金調達手段といえるでしょう。
さまざまな自治体や商工会議所による助成金・補助金がある
新規事業に活用できる助成金や補助金は、以下のとおりさまざまな主体により実施されています。
- 経済産業省
- 厚生労働省
- 地方自治体
- 公益経済団体(商工会議所)
- 民間団体・企業
自治体の中には、地域振興の一環として新規事業を応援する助成金・補助金・融資を展開している機関も多く見られます。自社が拠点とする地域の自治体の取り組みについて調べてみると良いでしょう。
ただし、自治体は地域によって取り組み内容に大きな差異があり、地域によっては有効的な助成金や補助金が少ないケースもあります。
新規事業に役立つ助成金・補助金の種類

本章では、新規事業に役立つ助成金や補助金の一例として11種類を取り上げます。
- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
- 創業助成金
- 小規模事業者持続化補助金
- 事業承継・引継ぎ補助金
- キャリアアップ助成金
- トライアル雇用奨励金
- 特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)
- 労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)
- 生涯現役起業支援助成金
- 特定求職者雇用開発助成金
- 事業再構築補助金
メジャーな助成金や補助金を中心に紹介しますが、今後も新しい助成金や補助金が登場する可能性は大いにあるので、助成金や補助金の申請を検討している方は、こまめにチェックしておくと良いでしょう。
①ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金とは、生産性向上を目的とした革新的な取り組みを行う中小企業・小規模事業者の設備投資などの支援を目的とした補助金です。名前のとおり、新規事業立ち上げに取り組む会社に適した補助金といえます。
主として設備投資に対する補助金であるため、設備投資を行う際は積極的に申請すると良いでしょう。
②創業助成金
創業助成金は、厳密にいうと新規事業の立ち上げではなく、都内で創業を予定している人や創業後5年未満の中小企業者などを対象とする助成金です。主な条件には、「TOKYO創業ステーションの事業計画書策定支援修了者」「東京都制度融資(創業)利用者」「都内の公的創業支援施設入居者」などが挙げられます。
新規事業と直接的な関係はないものの、創業初期に欠かせない人件費・賃借料・専門家謝金・産業財産権出願/導入費・広告費・備品費などの一部を助成してもらえます。
③小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金とは、商工会議所が実施している補助金のことです。小規模事業者持続化補助金の特徴は、主に以下の3つです。
- 小規模事業者向けの補助金
- 補助金の限度額は50万円
- 販路開拓や事業計画作成に対して商工会議所から助言を得られる
限度額が小さいですが、立ち上げたばかりの新規事業や創業当初の会社にとっては、貴重な資金源となります。
また、新規事業や創業間もない会社を軌道に乗せるうえで、外部からの助言は必要不可欠であるため、商工会議所などさまざまな会社の情報や知識が集まる組織からアドバイスを得られる点は非常に有益です。
④事業承継・引継ぎ補助金
事業承継をきっかけに、新しい取り組みなどを実施する中小企業者など、そして事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業者などをサポートする制度が、事業承継・引継ぎ補助金です。
これらの中小企業者や個人事業主へ、その取組に必要な経費の一部を補助します。また、事業再編や事業統合に伴う経営資源の引継ぎに必要な経費の一部を補助する事業を実施することで、事業承継、事業再編や事業統合を促します。この補助金は、日本経済の活性化を見込んでいるのです。
⑤キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、厚生労働省が実施している助成金のひとつです。対象者は、以下の非正規雇用者とされています。
- 有期契約労働者
- 短時間労働者
- 派遣労働者
つまり、非正規雇用者が会社内でキャリアップしていくうえで役立てられる助成金です。キャリアアップ助成金は助成対象によって7つのコースに分かれており、会社の取り組みに合わせて選べます。
新規事業の立ち上げに際して新たに非正規労働者を雇用したい場合などに、キャリアアップ助成金の活用を検討しましょう。
⑥トライアル雇用奨励金
トライアル雇用奨励金とは、「ハローワークや職業紹介事業者などから紹介された、職業経験・技能・知識などの不足を理由に安定的な就職が困難な求職者」を一定期間試行雇用した場合に得られる助成金です。
キャリアアップ助成金は新規雇用を推進するための助成金であるのに対して、トライアル雇用奨励金は採用におけるリスクを低減するための助成金という位置づけにあります。
⑦特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)
特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)とは、学校などの既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図ることを目的とする助成金です。
既卒者などが応募可能な新卒求人の申し込みまたは募集を行ったうえで、既卒者などを新規学卒枠で初めて採用し、その後に一定期間定着させた事業主に対して助成金が支給されます。新規事業の展開に際して、既卒者の新規学卒枠での採用を検討している場合に適した助成金です。
現在は公募を終了していますが、今後も定期的に実施される可能性は大いにあるため、こまめに情報を得ましょう。
⑧労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)
労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)とは、離職を余儀なくされる労働者の早期再就職および定着の支援を目的とする助成金です。
離職日の翌日から3カ月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合や、その雇い入れた労働者に対して職業訓練を実施した事業主に対して助成金を支給します。
この助成金の支給対象となるのは、以下のいずれにも該当する労働者に限定されているため注意しましょう。
- 支給申請を行う事業主に雇い入れられる直前の離職時に再就職援助計画または求職活動支援書の対象者であったこと
- 再就職援助計画または求職活動支援書の対象者として雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと
⑨生涯現役起業支援助成金
生涯現役社会の実現を目指すべく、以下2つの側面助成金を支給する制度です。
- 雇用創出措置にかかる助成金
- 生産性向上にかかる助成金
前者では、40歳以上の中高年齢者などによる起業に際し、事業活動に関する従業員を雇い入れるために要した経費の一部を助成することで、起業者自らの就業機会の創出を図ると同時に新たに雇い入れられる労働者の就業機会の創出を目指しています。
後者は、前者の助成金を受給した企業において、助成金の受給後に企業活動における生産性が一定程度向上した場合、追加で生産性向上にかかる助成金を支給する制度です。
40歳以上で新規事業立ち上げを検討している場合には、両制度の積極的な利用を検討しましょう。
⑩特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金とは、高年齢者や障害者などの就職困難者をハローワークなどの紹介をつうじて継続的に雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成金を支給する制度です。対象となる労働者の性質により特定就職困難者コース・生涯現役コースなどに分かれています。
具体的な支給要件は、前者では「60歳以上65歳未満の高年齢者や障害者などを雇用すること」、後者では「雇い入れした日の満年齢が65歳以上の離職者を雇用すること」などです。
M&Aによる事業譲渡の利用も、新規事業のための資金調達方法のひとつです。例えば自社に不要な事業がある場合、M&Aによる譲渡を行えば売却利益を獲得でき、新規事業への資金投入につなげられます。
事業譲渡などM&Aをご検討の際は、ぜひM&A総合研究所にご相談ください。M&A総合研究所では知識・経験の豊富なM&Aアドバイザーが、培ってきたノウハウを生かして案件をフルサポートいたします。また、M&A総合研究所ではスピーディーなサポートを実践しており、最短3カ月での成約実績も有しております。
料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。無料相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
⑪事業再構築補助金
事業再構築補助金は、新型コロナウイルスによる経済社会の変化に対応するための企業の思い切った事業再構築をサポートする補助金になります。事業再編をとおし、下記に当てはまる中小企業などが対象です。
- 新製品などで新たな市場に進出する
- 主な「事業」を転換する
- 主な「業種」を転換する
- 製造方法などを転換する
新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことも要件になります。中小企業だけでなく、中堅企業、個人事業主、企業組合なども補助の対象です。
事業承継で助成金・補助金を活用するメリット

助成金や補助金を申請すると、新規事業の開始および維持に関する資金繰りの心配を軽減できるだけでなく、以下3つのメリットも獲得可能です。
- 原則、返済は不要
- 労働環境の整備につながる
- 信頼が得られる
それぞれの内容を、詳しく紹介します。
①原則、返済は不要
助成金や補助金は、基本的に返済する必要がありません。お金を借りる融資とは違い、援助を受けられるシステムです。特に助成金は、各企業が納めた雇用保険をもとにお金が支払われます。要件を満たすことで、支払ったお金を受け取ることが可能です。
②労働環境の整備につながる
助成金や補助金を申請する際は、会社の体制を整備する必要があります。そのため、就業規則の見直しにより、労働環境の整備が期待できます。労働環境の整備は、企業の存続やトラブル防止のために重要です。
労働環境が整っていないと、トラブルが起こる可能性があります。そこで助成金や補助金の申請をつうじて、会社の体制についても見直す機会が生まれるメリットがあるのです。
③信頼が得られる
助成金や補助金を得ると、国・地方公共団体・民間団体などから信頼を得たことを意味します。そのため、企業の信頼や印象のアップにもつながるでしょう。事業を進める中で融資を受ける際にも、信用があると融資を行ってもらえる可能性が高まります。
融資は返済が必要ですが、資金繰りや投資で困った場合に役立てられます。助成金や補助金を得ることは、その後の資金繰りにも有益な効果があるのです。
④時代の潮流を把握できる
国や地方自治体は国内外の問題を考慮し、国や地域をより良くするために政策目標を立てそれを実行します。政策や方針に沿った会社の事業展開などを、資金面からサポートすることで政策目標を実現しやすくするために、日本の機関や地方自治体は助成金や補助金を交付します。
逆手に取ると、これにより国内外の課題や時代の潮流を把握できるでしょう。
⑤経営計画を明確化できる
補助金を申請する際は、ほとんどのケースで経営計画書の提出が必要です。経営計画書には、顧客ニーズ、市場動向、事業内容や自社の強みなど、必要とする費用や将来得られる利益などを具体的に書かなければなりません。
申請書を書くことにより、会社の事業を見直したり、整理したりすることが可能です。
新規事業における助成金・補助金の申請手順

本章では、助成金と補助金それぞれの申請手順を取り上げます。
- 助成金の申請手順
- 補助金の申請手順
助成金や補助金の申請手順は共通点も多いですが、一部の手順が異なっているため注意して把握しましょう。
助成金の申請手順
助成金の申請は、大まかに以下6つのステップで行われます。
- 申請したい助成金のホームページから必要な書類をダウンロードする
- 必要事項を記入する
- 記入した書類を所定の窓口に提出する
- 書類に不備がなければ審査に入る
- 審査に通過すると会社に支給決定通知書が届く
- 通知書が届いた1~2週間後に指定の口座に助成金が振り込まれる
書類を提出し、審査に合格すると助成金が振り込まれる流れです。
補助金の申請手順
補助金は、大まかに以下9つのステップで行われます。
- ホームページから必要な書類をダウンロードする
- 必要事項を記入する
- 記入した書類を所定の窓口に提出する
- 書類に不備がなければ審査に入る
- 審査通過後に決定された事業を実行する
- 事業の実行が完了したら補助金を行っている機関からチェックを受ける
- 事業内容やかかった経費を報告する
- 補助金の金額が決定
- 補助金が振り込まれる
助成金と大きく異なる点は、申請してから事業を開始する点です。実際に決定した事業を行うことで補助金の金額が決まり、それが実際に振り込まれる流れになります。
新規事業で助成金・補助金を活用する際の注意点

新規事業を立ち上げるうえで、助成金や補助金は非常に役に立ちます。活用する際は、以下7つの注意点を把握しましょう。
- 採択率は決して高くない
- 応募期間が限られている
- 基本的には後払い
- 提出書類を準備するために時間と労力が必要
- 複数・重複してもらえない
- 自己資金ゼロではダメ
- 本来の目的を忘れない
ただやみくもに助成金や補助金に申請しても、思った効果が得られないといったトラブルは十分に想定されるため、注意点を意識しましょう。
①採択率は決して高くない
補助金や助成金の採択率は、決して高くありません。たとえメジャーな補助金でも、採択率は3割を切るケースもあり、狭き門といえます。せっかく適した補助金を見つけても、審査を通過できなければ利用できません。
そこで実際に補助金を活用したい場合は、審査を通過できるよう入念に準備してください。準備を行う際のポイントは、主に以下の2つです。
- 信ぴょう性の高い事業計画を作成する
- 補助金獲得のためのサポートをしてくれるサービスを利用する
補助金の審査を通過するために重要なのは、事業計画です。「どれだけ具体的で、信ぴょう性の高い事業計画を作成できるか」が、審査を通過するうえで最も大事なポイントといえます。たとえ熱意があっても、ずさんな事業計画では補助金の獲得は困難です。
経営コンサルティング会社によっては、補助金獲得に向けたサポートを提供している機関も見られます。自力で事業計画を作成する自信がない場合は、外部の専門家のアドバイスを得るのがおすすめです。
②応募期間が限られている
助成金・補助金の申請時は、応募期間に気を付けましょう。応募期間は1年の間に1~2カ月程度に限られているケースもあるため、うっかりしていると期間を逃してしまうトラブルも十分に考えられます。
第二次募集を行ってくれる制度もありますが、1年に1回だけ募集して終わるパターンも少なくありません。政府や自治体の意向で次年度以降は募集しない制度もあるため、応募期間を事前に把握しましょう。
③基本的には後払い
助成金や補助金は、後払いが基本です。つまり、設備投資や経営革新を行った際は、出費が発生します。そのため、ある程度は資金力に余裕を持たせておく必要があります。特に補助金は事業を行った後で補助金の金額が決定されるため、審査を通過したからといって油断できません。
場合によっては、せっかく助成金や補助金が得られても、振り込まれるまでに発生した出費で経営が悪化してしまうおそれもあるため、注意が必要です。
④提出書類を準備するために時間と労力が必要
助成金や補助金を申請する際は、非常に多くの書類を準備する必要があります。
- 事業計画書
- 会社概要
- 確定申告書
- 登記簿抄本・開業届
- 本人確認書
- 収支計画書
- その他、申請のための書類
書類を準備するだけでなく、審査に通過するには事業について十分にアピールする必要もあります。すべての書類をそろえてアピールするための準備を整えるには、膨大な時間と労力が必要です。自分で準備する自信がない場合は、専門家に一部の書類作成を依頼すると良いでしょう。
⑤複数・重複してもらえない
助成金や補助金の中には、重複して受け取れない制度も多いです。対象の経費が重なってしまうと実際にかかった経費よりも受け取る金額が多くなってしまうため、さまざまなルールが定められています。
ただし、複数の制度を同時に申請することは可能です。最近では、さまざまな助成金や補助金があり、自分の事業にあったものすべてに申請できます。採択された制度の中から、最終的に利用する制度を選ぶと良いでしょう。
⑥自己資金ゼロではダメ
助成金や補助金の申請を考えるあまり、自己資金は不要と考えてしまう経営者の方も少なくありません。しかし、自己資金がゼロでは事業を進められないため、ある程度の自己資金が必要となります。
助成金や補助金は、あくまでも不足分を補うための制度です。特に補助金の場合は、実際にかかった経費を申請して、はじめて受け取る金額が決定しお金が振り込まれます。つまり、最初に資金がないと事業を開始できません。
⑦本来の目的を忘れない
助成金や補助金の利用が決まったからといって、新規事業を推進する本来の目的を忘れないよう注意しましょう。助成金や補助金は、新規事業を支えるために使われるべき制度です。しかし、以下のように、助成金や補助金の恩恵を無駄にしてしまうケースも少なくありません。
- 新規事業の維持とは関係のないことに使ってしまう
- 無駄な出費を重ねてしまう
確かに助成金や補助金は返済不要であり、振り込まれた後は自由に使えます。とはいえ、新規事業を維持していくうえで、資金繰りは慎重に行う必要がある点を忘れないようにしましょう。
新規事業に役立つ助成金・補助金のまとめ

新規事業において資金は重要であり、審査に通過すれば資金が得られる助成金や補助金は資金調達の手段として非常に有効的です。ただし、助成金には守るべき一定要件があり、補助金には厳しい審査を通過する必要があるため、採択率は一概に高いとはいえません。
助成金や補助金を得るには、相応の準備が必要である点を覚えておきましょう。
M&A・事業承継のご相談なら24時間対応のM&A総合研究所
M&A・事業承継のご相談は成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A総合研究所にご相談ください。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴
- 譲渡企業様完全成功報酬!
- 最短43日、平均7.2ヶ月のスピード成約(2025年9月期実績)
- 上場の信頼感と豊富な実績
- 譲受企業専門部署による強いマッチング力
M&A総合研究所は、M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。
また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。
相談も無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたにおすすめの記事

M&Aとは?メリット・手法・最新動向を専門家がわかりやすく徹底解説
M&Aは事業拡大や事業承継の有効な手段です。本記事ではM&Aの基礎知識から、2025年以降の最新動向、手法、メリット・デメリット、成功させるためのポイントまで、専門家が分かりやす...

買収とは?用語の意味やメリット・デメリット、M&A手法、買収防衛策も解説
買収には、友好的買収と敵対的買収とがあります。また、買収に用いられるM&Aスキーム(手法)は実にさまざまです。本記事では、買収の意味や行われる目的、メリット・デメリット、買収のプロセスや...

現在価値とは?計算方法や割引率、キャッシュフローとの関係をわかりやすく解説
M&Aや投資の意思決定するうえでは、今後得られる利益の現時点での価値を表す指標「現在価値」についての理解が必要です。今の記事では、現在価値とはどのようなものか、計算方法や割引率、キャッシ...

株価算定方法とは?非上場企業の活用場面、必要費用、手続きの流れを解説
株価算定方法は多くの種類があり、それぞれ活用する場面や特徴が異なります。この記事では、マーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチといった株価算定方法の種類、株価算定のプロセス、株...

赤字になったら会社はつぶれる?赤字経営のメリット・デメリット、赤字決算について解説
法人税を節税するために、赤字経営をわざと行う会社も存在します。しかし、会社は赤字だからといって、必ず倒産する訳ではありません。逆に黒字でも倒産するリスクがあります。赤字経営のメリット・デメリット...
関連する記事
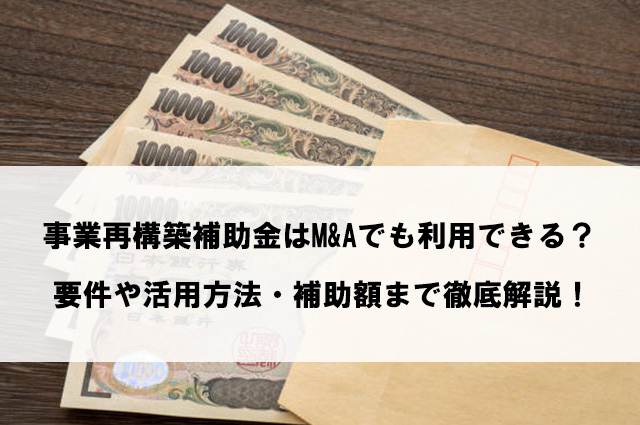
事業再構築補助金はM&Aでも利用できる?要件や活用方法・補助額まで徹底解説!
事業再構築補助金は要件を満たせば、中小企業や中堅企業に補助金を支給する制度です。中にはM&Aを実施するときに制度を利用する企業も存在します。この記事ではM&Aを実施しても事業再構...

DDSとは?DESとの違いや手順・活用方法・メリット・デメリットまで解説!
企業再建手法の1つとして注目されているDDS。そんなDDSとよく似た言葉にDESがありますが、それぞれの違いは何なのかを本記事で解説していきます。またDDSを実施する手順や活用方法、メリットやデ...

CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)とは?メリット・デメリットを解説!
ベンチャー企業へ投資をするCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)。VC(ベンチャーキャピタル)と混同されがちなCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)とは何なのか、活用するメリット・デメリ...

エンジェル投資家について徹底解説!メリットやデメリット・探し方は?
企業がイグジット(上場、ハイバリエーションでの売却)をした際のキャピタルゲインを目的とした投資を行うエンジェル投資家。返済義務がない投資をメインとしているエンジェル投資家について知らない人も多い...

シード期とは?定義やスタートアップの資金調達方法・成功のポイントを解説!
成長していく過程においてIPOやM&Aを活用することも重要ですが、具体的にどのようなポイントを抑えれば良いのでしょうか。 この記事では、シード期の定義やスタートアップの資金調達方法・成...

M&Aにおけるエスクローの意味とは?メリット・デメリットについて紹介!
日本のM&Aでは、活用されているケースは少ないとされている仲介サービス「エスクロー」があります。海外では多く活用されていますが、この「エスクロー」とはどういう意味なのでしょうか。ここでは...

投資銀行のM&Aにおける役割とは?部門ごとの業務内容や違いを解説!
投資銀行は銀行の一種ではないと聞くと、驚かれる方が多いかもしれません。投資銀行は、銀行業ではなく証券業に分類されます。本記事では、投資銀行の概要、投資銀行がM&Aにおける役割、投資銀行の4大業務...

スケールメリットが経営に与える効果は?意味や仕組みを具体例に徹底解説!
スケールメリットとは、同種の業種やサービスが多く集まることで単体よりも大きな成果を生み出せることです。会社経営を行う際、不必要な経費を活用しているケースが多いです。このような課題を解決できるスケ...

株式分割とは何?仕組みやメリット・デメリットなどをわかりやすく解説!
株式分割とは、1株をいくつかに分割して、発行済みの株式枚数を増やすことです。株式分割には企業側、投資家側にメリット・デメリットが存在します。理解していないとトラブルに発展する可能性があります。そ...
























立命館大学卒業後、地方銀行にて中堅中小企業を担当。ファイナンス、ビジネスマッチング等に従事した後、本部専門部署にて事業承継支援を専門として実績を積む。
その後、大手M&A仲介会社において、事業承継や戦略的な成長を目的としたM&Aを業種・規模問わず、多数成約に導く。
M&A総合研究所では、製造業や建設業、不動産業など幅広い業種を担当。