M&Aとは?メリット・手法・最新動向を専門家がわかりやすく徹底解説
2022年12月1日更新資金調達
LBOファイナンスとは?LBOとの違いや特徴/リスクを解説【図解】
LBOファイナンスとは、対象の信用力や資産を担保にして金融機関から買収資金を調達する買収方法のことです。名称の由来は、比較的少額の自己資金を梃子(レバレッジ)にすることからきています。本記事では、LBOファイナンスの特徴やメリット・リスクを解説します。
目次
LBOファイナンスとは?
LBOファイナンスとは、買収対象のキャッシュフローや信用力を担保にして買収資金を調達する手法であり、いかに自己負担を軽減しながら買収を実行するとの考えにもとづいた買収手段です。
LBOファイナンスは、主に大企業同士のM&Aで使用されます。中堅・中小規模の案件には関わりが少ないですが、将来的に実践する可能性を考えて数あるM&A手法の1つとして把握しておくと、有効活用できる場合もあります。
LBOファイナンスの特徴
LBOファイナンスは、対象会社のキャッシュフローを担保にする手法であり、以下のようにさまざまな特徴があります。
- 負債の割合を増やし、純資産の割合を減らす
- ノンリコース
- 特別目的会社の利用
負債の割合を増やし、純資産の割合を減らす
LBOファイナンスで融資を受けると、譲渡企業の負債が増加して元本返済による経常利益以下の利益減少や利息払いによる手元資金の減少で、純資産の割合も減少します。
一般的なM&A買収では、譲受企業から譲渡企業に対して譲渡代金の支払いが行われるため、金銭的な余裕が生まれます。しかし、LBOファイナンスでは譲渡企業の負担が大きくなるので、譲渡企業のリスクが高いです。
ノンリコース
LBOファイナンスの2つ目の特徴は、ノンリコースであることです。譲受企業に担保や保証責任はないため、譲渡企業が返済不可能な状態になったとしても、債権者(金融機関等)は譲受企業に対して返済請求できません。
LBOファイナンスは、譲渡企業だけでなく債権者にとってもリスクの高い方法です。対象となる譲渡企業には、債権者の審査基準を満たせるほどのキャッシュフローや信用力が求められます。
特別目的会社の利用
LBOファイナンスの3つ目の特徴は、買収専用のSPC(特別目的会社)を利用することです。譲受企業がSPCを設立して、SPCがLBOファイナンスで金融機関等から買収資金を調達します。
SPCは、調達した資金を元手に譲渡企業の買収を行い、その後に合併を実施します。返済義務のあるSPCと譲渡企業が合併して、実質的に譲渡企業に返済義務を負わせることで、LBOファイナンスが完了する流れです。
LBOファイナンスとLBOとの違い
LBOファイナンスは、LBO(レバレッジド・バイアウト)から派生した買収手法です。LBOの特徴はLBOファイナンスの特徴ともいえますが、この章ではLBOの特徴とLBOファイナンスとの違いを解説します。
LBOとは
LBO(レバレッジド・バイアウト)とは、譲渡企業の資産や将来的な収益を担保に金融機関等から資金調達して買収するM&A手法です。
LBOが成功すれば、譲受企業は大きな出費をすることなく、譲渡企業を傘下に加えられます。大量にリソースを投入する必要がないので、事業の多角化を目指す企業などが有効活用しています。特にPEファンドが活用しており、企業価値が向上した段階で売却して数倍のリータンを得るやり方で、一大資産を築いているファンドも少なくありません。
LBOの特徴
LBOは、譲受企業にとって利用価値が大きい特徴を持ち合わせています。特に影響の大きな特徴は、以下の2点です。
- 買収側の投資額削減
- 売却側の社会的信用を活用
買収側の投資額削減
LBOの1つ目の特徴は、買収側の投資額を削減できることです。譲渡企業の事業内容や今後の事業計画に基づき金融機関から買収資金を借り入れて、最終的に譲渡企業の負債にできます。通常のM&Aでは資金調達が問題になることが多いですが、LBOを用いたM&Aは自己負担を軽減できるため資金調達が問題になりにくいのがメリットです。
少ない資本でM&A買収を実行できるため、企業全体にリソースの余裕が生まれて複数の事業を同時並行しやすくなるメリットもあります。
売却側の社会的信用を活用
LBOの2つ目の特徴は、売却側の社会的信用を活用できることです。通常の融資は買収側である譲受企業の信用力にもとづいて行われますが、LBOは譲渡企業が返済義務を負うため売却側の社会的信用が重要なポイントになります。
これにより、譲受企業は自らが調達できないような巨額の資金も譲渡企業の社会的信用で調達できるようになり、積極的にM&A買収を実行しやすくなります。
LBOファイナンスとLBOの違い
LBOの譲渡企業の社会的信用を活用する特徴に加えて、負債増加・純資産の割合減少やノンリコースなどの特徴を強めたものがLBOファイナンスです。
LBOファイナンスは、資金を貸し出す金融機関のリスクがさらに高まっているため、融資を受けるためには譲渡企業に返済能力があることを示せるよう、M&A買収の時点で具体性のある事業計画を提示することが求められます。
LBOファイナンスを利用するメリット
数あるM&A手法のなかでも特徴的なLBOファイナンスですが、利用するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。この章では、買収側・売却側・融資側のそれぞれの視点からメリットを解説します。
買収する側のメリット
LBOファイナンスの買収側における最大のメリットは、少ない資本で買収を行えることです。LBOファイナンスで売却側の社会的信用を活用して大規模な融資を受ければ、自己資本を持ち出すことなくM&A買収を実現させることも可能です。
LBOファイナンスは返済義務を売却側に負わせられるため、事業計画に失敗して売却側である譲渡企業が倒産しても買収側に返済義務はありません。買収側の譲受企業は、M&Aの買収資金の一部として投じた自己資本を失うだけで済み、LBOファイナンスの失敗が他事業に悪影響を与えるようなこともないため、積極的に挑戦しやすいメリットがあります。
売却する側の株主のメリット
LBOファイナンスの買収側における最大のメリットは、株式を高値で売却できることです。LBOファイナンスを用いた買収の場合、TOB(株式公開買付)と呼ばれる手法が用いられます。TOBは市場価格に上乗せしたプレミアム価格で買い取ることが一般的です。
過去のTOB事例にもとづいた相場は20〜40%前後となっており、市場価格100円の株式であれば120〜140円で買い取ってもらえます。
融資する金融機関のメリット
LBOファイナンスの融資側における最大のメリットは、高金利で貸し付けることができることです。LBOファイナンスは金融機関にとってリスクが伴うもので、リターンとして高金利設定になることが多いとされています。
LBOファイナンスは短期返済計画になることが多く、短期間で資金を増やせるために金融機関にとって大きなメリットです。特にPEファンドは複数のLBOファイナンスを同時並行し、買収を繰り返しています。数年間のスパンで資本回収を見込んでいるので、金融機関が資本を回収できるスパンも短くなる傾向にあります。
LBOファイナンスを利用するリスク
LBOファイナンスには多様なメリットがありますが、当然ながら一定のリスクが伴います。この章では、買収・売却・融資のそれぞれの立場からLBOファイナンスのリスクを解説します。
買収する側のリスク
LBOファイナンスで買収側の最大のリスクは、信用を損なうおそれがあることです。LBOファイナンスは売却側に返済義務を負わせて、買収側が負うリスクは少ない自己資本程度です。しかし、LBOファイナンスが失敗に終わった場合は、無計画な買収を行ったとして会社の社会的信用や評判を大きく損なう可能性があります。
LBOの失敗事例が買収側の失敗として紹介されるケースも多くなっており、売却側からの反感の声や周囲からの指摘により最悪の場合は買収側の経営に影響が及ぶおそれもあります。
売却する側のリスク
LBOファイナンスで売却側の最大のリスクは、経営の自由度が低いことです。LBOファイナンスで返済義務を負わされた売却側は、今後の事業の利益で短期間の返済をしなくてはならないため、経営戦略に幅を持たせることが難しくなります。
事業を展開するうえで追加融資が必要になった際も、すでに高額な負債を抱えているため金融機関からの資金調達は期待できません。借入金を完済するまでは自由が縛られている状態なので、完済まではLBOファイナンスの際に策定した事業計画にもとづいて経営する必要があります。
融資する金融機関のリスク
LBOファイナンスで融資側の最大のリスクは、回収不能になる可能性があることです。金融機関は売却側の信用力やキャッシュフローを担保に貸し付けているため、売却側である譲渡企業が事業計画に失敗した場合は資金を回収できなくなる可能性があります。
金融機関にとって不良債権は絶対に避けたいものなので、LBOファイナンスの融資を決定する際は的確な判断が求められます。
LBOファイナンスを活用してM&Aを実行する流れ
この章では、LBOファイナンスを活用したM&Aの流れを解説します。LBOファイナンスの要素が絡むポイントは、主に以下の4つです。
- SPC(特別目的会社)を設立
- 買収するための資金調達
- M&Aの実行
- SPCと買収先企業の合併
SPC(特別目的会社)を設立
LBOファイナンスは、まずは買収側がSPC(特別目的会社)を設立します。SPC(特別目的会社)とは、企業が特定の資産だけを切り離して、特定の資産やプロジェクトのためだけに設立する会社です。LBOファイナンスでは、ここで設立したSPCが最終的な受け皿会社としての役割を果たすことになります。
資本金はいくらでも構いませんが、LBOファイナンスで買収側が自己負担する分は、この段階で資本金としてSPCに移しておく流れが一般的です。
| 買収側 | → | 買収側 |
| ↓ | ┃ | |
| SPCを設立 | 受け皿会社 |
買収するための資金調達
続いて、金融機関から買収資金を調達します。LBOファイナンスによる買収を実行するのはSPCなので、融資先もSPCです。この段階では、SPCに買収資金と借金の返済義務の両方が存在している状況です。LBOファイナンスの借金は、LBOローンなどと呼ばれることもあります。
| 金融機関からSPCへ融資 → |
買収側 | → | 買収側 | |
| ┃ | ┃ | |||
| 受け皿会社(SPC) | 受け皿会社(SPC) (資金+借金) |
|||
M&Aの実行
買収資金を調達したら、SPCにより買収先企業のM&A買収を実行します。買収先企業の株式の対価として資金を払い込み、買収先企業をSPCの傘下に加えます。この段階でSPCと買収先企業の親子関係が構築され、SPCには買収先企業の株式と借金が残っている状態です。SPCが払い込んだ買収資金は、売却側の株主のものとなります。
| 売却側 | 株式→ ←資金 |
買収側 |
| ┃ | ┃ | |
| 買収先企業 (事業) |
受け皿会社(SPC) (借金) |
| 買収側 |
| ┃ |
| 受け皿会社(SPC) (株式+借金) |
| ┃ |
| 買収先企業 (事業) |
SPCと買収先企業の合併
LBOファイナンスの最後の流れは、受け皿会社と買収先企業の合併です。最終的に買収先企業に事業と借金が残る形となります。以降は、買収先企業が生み出す収益から、金融機関に対して返済を行います。万が一、買収先企業が事業に失敗した場合も、ノンリコースのために買収側が返済義務を負うことはありません。
| 買収側 | → | 買収側 |
| ┃ | ||
| 受け皿会社(SPC) (株式+借金) |
┃ | |
| ↑吸収合併↑ | 受け皿会社&買収先企業 (事業+借金) |
|
| 買収先企業 (事業) |
LBOファイナンスのご相談はM&A総合研究所へ
LBOファイナンスはメリットが大きい反面、リスクも高くなります。リスクを押さえながら実行するためには、M&Aの専門家などのサポートを受けながら十分に対策を施す必要があります。
M&A総合研究所は、M&Aの仲介事業を手掛けているM&A仲介会社です。幅広い規模のM&A案件を扱っており、案件に携わる際は常にLBOファイナンスを含めたM&A手法の比較検討をいたします。無料相談は随時お受けしています。LBOファイナンスやM&Aにお悩みの際は、お気軽にM&A総合研究所までご連絡ください。
LBOファイナンス関連業務に求められる能力
LBOファイナンスに携わる主体は、投資銀行・信託銀行・投資ファンド・リース会社・財務アドバイザリーをはじめ、戦略コンサルティングファーム・弁護士事務所などです。
M&Aおよび事業承継業務の経験者や金融関連の審業務査経験者のほか、MBA保有者・弁護士・公認会計士・税理士資格を有する人材が求められています。そのほか、ビジネスレベルの英語力が求められるケースも多いです。
LBOファイナンスのまとめ
LBOファイナンスは独特なM&A手法ですが、成功すれば飛躍的に企業成長を図ることも可能です。リスクを把握したうえで実行すれば、メリットを最大限に生かし、M&Aの専門家からのアドバイスも参考にすれば、成功確率が高まります。
M&A・事業承継のご相談なら24時間対応のM&A総合研究所
M&A・事業承継のご相談は成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A総合研究所にご相談ください。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴
- 譲渡企業様完全成功報酬!
- 最短43日、平均7.2ヶ月のスピード成約(2025年9月期実績)
- 上場の信頼感と豊富な実績
- 譲受企業専門部署による強いマッチング力
M&A総合研究所は、M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。
また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。
相談も無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたにおすすめの記事

M&Aとは?メリット・手法・最新動向を専門家がわかりやすく徹底解説
M&Aは事業拡大や事業承継の有効な手段です。本記事ではM&Aの基礎知識から、2025年以降の最新動向、手法、メリット・デメリット、成功させるためのポイントまで、専門家が分かりやす...

買収とは?用語の意味やメリット・デメリット、M&A手法、買収防衛策も解説
買収には、友好的買収と敵対的買収とがあります。また、買収に用いられるM&Aスキーム(手法)は実にさまざまです。本記事では、買収の意味や行われる目的、メリット・デメリット、買収のプロセスや...

現在価値とは?計算方法や割引率、キャッシュフローとの関係をわかりやすく解説
M&Aや投資の意思決定するうえでは、今後得られる利益の現時点での価値を表す指標「現在価値」についての理解が必要です。今の記事では、現在価値とはどのようなものか、計算方法や割引率、キャッシ...

株価算定方法とは?非上場企業の活用場面、必要費用、手続きの流れを解説
株価算定方法は多くの種類があり、それぞれ活用する場面や特徴が異なります。この記事では、マーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチといった株価算定方法の種類、株価算定のプロセス、株...

赤字になったら会社はつぶれる?赤字経営のメリット・デメリット、赤字決算について解説
法人税を節税するために、赤字経営をわざと行う会社も存在します。しかし、会社は赤字だからといって、必ず倒産する訳ではありません。逆に黒字でも倒産するリスクがあります。赤字経営のメリット・デメリット...
関連する記事
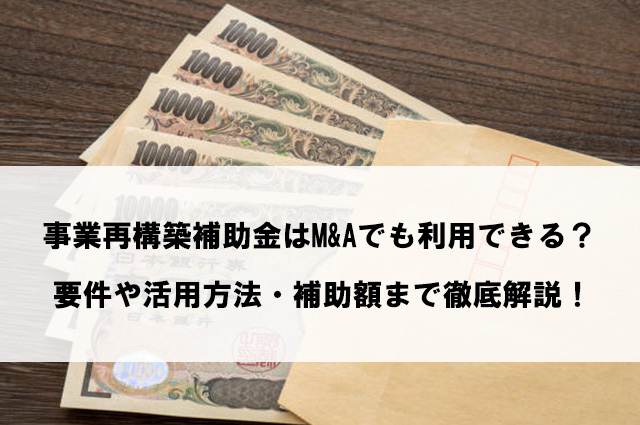
事業再構築補助金はM&Aでも利用できる?要件や活用方法・補助額まで徹底解説!
事業再構築補助金は要件を満たせば、中小企業や中堅企業に補助金を支給する制度です。中にはM&Aを実施するときに制度を利用する企業も存在します。この記事ではM&Aを実施しても事業再構...

DDSとは?DESとの違いや手順・活用方法・メリット・デメリットまで解説!
企業再建手法の1つとして注目されているDDS。そんなDDSとよく似た言葉にDESがありますが、それぞれの違いは何なのかを本記事で解説していきます。またDDSを実施する手順や活用方法、メリットやデ...

CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)とは?メリット・デメリットを解説!
ベンチャー企業へ投資をするCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)。VC(ベンチャーキャピタル)と混同されがちなCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)とは何なのか、活用するメリット・デメリ...

エンジェル投資家について徹底解説!メリットやデメリット・探し方は?
企業がイグジット(上場、ハイバリエーションでの売却)をした際のキャピタルゲインを目的とした投資を行うエンジェル投資家。返済義務がない投資をメインとしているエンジェル投資家について知らない人も多い...

シード期とは?定義やスタートアップの資金調達方法・成功のポイントを解説!
成長していく過程においてIPOやM&Aを活用することも重要ですが、具体的にどのようなポイントを抑えれば良いのでしょうか。 この記事では、シード期の定義やスタートアップの資金調達方法・成...

M&Aにおけるエスクローの意味とは?メリット・デメリットについて紹介!
日本のM&Aでは、活用されているケースは少ないとされている仲介サービス「エスクロー」があります。海外では多く活用されていますが、この「エスクロー」とはどういう意味なのでしょうか。ここでは...

投資銀行のM&Aにおける役割とは?部門ごとの業務内容や違いを解説!
投資銀行は銀行の一種ではないと聞くと、驚かれる方が多いかもしれません。投資銀行は、銀行業ではなく証券業に分類されます。本記事では、投資銀行の概要、投資銀行がM&Aにおける役割、投資銀行の4大業務...

スケールメリットが経営に与える効果は?意味や仕組みを具体例に徹底解説!
スケールメリットとは、同種の業種やサービスが多く集まることで単体よりも大きな成果を生み出せることです。会社経営を行う際、不必要な経費を活用しているケースが多いです。このような課題を解決できるスケ...

株式分割とは何?仕組みやメリット・デメリットなどをわかりやすく解説!
株式分割とは、1株をいくつかに分割して、発行済みの株式枚数を増やすことです。株式分割には企業側、投資家側にメリット・デメリットが存在します。理解していないとトラブルに発展する可能性があります。そ...
























立命館大学卒業後、地方銀行にて中堅中小企業を担当。ファイナンス、ビジネスマッチング等に従事した後、本部専門部署にて事業承継支援を専門として実績を積む。
その後、大手M&A仲介会社において、事業承継や戦略的な成長を目的としたM&Aを業種・規模問わず、多数成約に導く。
M&A総合研究所では、製造業や建設業、不動産業など幅広い業種を担当。