M&Aとは?目的・メリットから手法、最新動向までわかりやすく解説
2025年11月17日更新資金調達
中小企業のM&Aは資金調達の選択肢!現状の課題から成功のコツまで解説
中小企業の資金調達は経営の重要課題です。融資や増資に加え、近年はM&Aも有力な選択肢となっています。本記事では、中小企業が直面する資金調達の現状や課題、M&Aを含めた具体的な手法、成功のコツを解説します。
目次
中小企業における資金調達の重要性
中小企業の経営者にとって、資金調達は常に悩みの種です。特に近年は、ゼロゼロ融資の返済本格化や原材料価格の高騰、人手不足による人件費の上昇など、経営環境が厳しさを増しています。このような状況下で事業を継続・成長させるためにも、適切な資金調達は最優先で解決すべき課題の一つといえるでしょう。
資金調達の方法は多様化していますが、中小企業は大企業と比べて活用できる手段が限られる傾向にあります。本記事では、中小企業が実際に活用できる資金調達の方法を具体的に紹介します。
中小企業の資金調達の現状と特徴
中小企業の資金調達の現状はどうなっているでしょうか?中小企業の資金調達の必要性は成長ステージによって変化します。会社の成長ステージは成長初期、成長・拡大期、安定期の3つがあり、資金調達の重要性が増すのは成長初期の段階です。
成長初期は、事業を軌道に乗せたり、研究開発をしたりするのに資金が必要となるため、資金調達先の確保が経営課題になります。しかし、成長初期の段階で資金調達先を確保できる会社は少ない現状です。そのため、投資をあきらめて事業を断念してしまう会社も少なくありません。
そもそも成長初期のステージにある会社は創業したてのベンチャー企業であることが多く、銀行のような中小企業から融資を得ることも難しい傾向です。その段階で有力な資金調達先を確保できるかどうかが、その会社の将来を左右するといっても過言ではないでしょう。
中小企業が抱える資金調達の課題
中小企業の資金調達は業種を問わずさまざまな課題を抱えています。代表的なのが資金調達先を確保できないことです。中小企業やベンチャー企業は、銀行などの金融機関の融資に依存する一方、実際に融資される可能性は低くなっています。
大企業と比べて規模が小さい中小企業やベンチャー企業は、社会的な信用性が低くなりがちです。また、創業して日が浅いと赤字経営であることが多いため、銀行のような金融機関が融資に対して消極的になります。そのため、中小企業やベンチャー企業は資金調達が安定しません。
ただ、中小企業やベンチャー企業は、国が運営する公的機関から支援を受けられることがあり、金融機関以外にベンチャーキャピタルのような投資ファンドを活用する方法もあります。しかし、リスクが多いと判断されると手を貸してくれないケースが多いようです。
昨今の中小企業やベンチャー企業は、公的機関の支援などによって会社を黒字にした後、金融機関から融資を得るという流れがスタンダートだといえます。
【5選】中小企業が活用できる主な資金調達方法
資金調達の方法にはさまざまありますが、中小企業が取り得る資金調達の方法は限られてきます。ここでは、中小企業が活用できる資金調達方法を5つ紹介します。
経営者の自己資金を使う
中小企業の経営者が持つ資金を企業に使う方法です。中小企業の創業時に、経営者が取り得る資金調達方法として知られています。中小企業の一つを経営できる資金調達が可能ならば、対外的な信頼も得やすくなります。
また、中小企業の経営者自身が資金調達しているので、経営権を維持しやすいです。シンプルな構図であるため、スケールが小さい中小企業の経営者に適した方法といえるでしょう。
また、既に所有している資産を売却して資金を作る方法もあります。一方で、経営者自身が資金調達する以上、資金が不十分になる可能性があります。
時間がかかるほか、レバレッジが効かなくなることもあり、中小企業が自己資金で資金調達するのは難しいかもしれません。
資本を増やす
経営者が持つ資本を増やして資金調達する方法です。一般的に、中小企業や大企業は株式の発行によって資金を集めます。投資家などに株式を買ってもらうことで自動的に資金が入り続け、返済義務がない点も特徴的です。
また、会社の資産を担保にかけたり、保証人を立てたりする必要もありません。大企業や中小企業が資金調達の手段として用いるオーソドックスな方法の一つです。充分な資金調達が実現するまで準備に時間がかかることもある一方、投資を確定させれば着実に資金を獲得できます。
しかし、さまざまな投資家に株式を買ってもらう以上、中小企業は信頼に応えるだけの業績を出さなければなりません。もし、信頼に応えなければ、株式による資金調達が滞ってしまう恐れもあります。
また、株主の株式保有率などによっては、経営権が脅かされるリスクもあります。したがって、中小企業と大企業にとって、株主との付き合いは非常に重要です。
負債を増やしていく
負債を増やしていくのも、中小企業が活用できる資金調達方法の一つです。金融機関からの融資や借入がよい例でしょう。活用しやすく、中小企業が取り得る資金調達の方法として知れ渡っています。経営権を脅かされることなく資金調達が可能です。
また、長らく続いた低金利政策により、比較的低い利率(1~3%程度)で借入しやすい点もメリットでした。しかし、2024年に入り日銀が金融政策の正常化を進めているため、今後は金利が上昇する可能性があります。そのため、手元に資産がない場合に有効な手段ですが、将来の金利変動リスクも考慮することが重要です。融資や借入で重要なのは、事業計画の妥当性を含めた中小企業の信頼度です。
会社の信頼が低いほど、安定した額の融資を得ることは難しくなります。借入の際に担保を設定する必要性も生じ、ある程度のリスクは覚悟しておかねばなりません。そもそも負債は借金と同義で、資金を借りた以上返済する義務が生じます。
そのため、経営の先行きを見据えながら実施することが大切です。加えて、書類作成などに手間がかかる一面もあるため、経営者には慎重さが求められます。
補助金や助成金を得る
国や地方自治体は、中小企業の経営を支援するために多様な補助金・助成金制度を用意しています。例えば、2024年度以降も継続されている「事業承継・引継ぎ補助金」は、M&Aを行う際の専門家活用費用や設備投資費用の一部を補助する制度で、多くの経営者に活用されています。これらの制度は公募期間や要件が頻繁に更新されるため、中小企業庁の公式サイトなどで常に最新情報を確認することが不可欠です。
一部例外はありますが、基本的には返済義務がないため、補助金や助成金が負債になる心配もありません。ただ、実質的に国からサポートを得ることになり、審査が厳しいケースも少なくありません。
そのため、書類の作成が難しかったり、助成金や補助金の入金が遅くなったりする場合があります。スムーズに資金調達したい中小企業にはあまり向いていない方法です。
クラウドファンディング
インターネットを通じて不特定多数から資金を募るクラウドファンディングも、中小企業の有効な資金調達方法です。製品やサービスを提供する「購入型」や、活動を応援してもらう「寄付型」など複数の種類があります。事業内容や製品の魅力を広くアピールでき、テストマーケティングとしても活用できる点が大きなメリットです。
昨今では、中小企業がクラウドファンディングで新たな事業や開発を実施した事例も増加しています。ただし、クラウドファンディングの活用は手数料がかかるため、集めた金額に対して出費の割合が多くなる可能性があります。
また、調達できる資金が不十分で目標金額に達成しないこともあります。したがって、入念な準備と企画の精査が重要です。
※関連記事
中小企業が資金調達で失敗しないための注意点
資金調達を成功させるには、ただ方法を知るだけでなく、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。ここでは、資金調達で失敗しないための注意点を3つ解説します。
事業計画書の重要性と作成のポイント
金融機関からの融資や投資家からの出資を受ける際、事業計画書の提出はほぼ必須です。事業計画書は、自社の事業内容や成長戦略、資金の使途、返済計画などを具体的に示す「会社の未来図」です。説得力のある事業計画書を作成するには、市場分析や競合調査に基づいた客観的なデータと、実現可能な数値目標を盛り込むことが重要です。
資金繰り表の作成と管理
資金調達を検討する前に、まずは自社の資金状況を正確に把握することが不可欠です。日々の現金の出入りを記録・管理する「資金繰り表」を作成し、将来の資金ショートのリスクを予測しましょう。資金繰り表によって、いつ、いくらの資金が不足するかが明確になり、計画的な資金調達活動が可能になります。
専門家への相談を惜しまない
資金調達には、財務や法務に関する専門的な知識が求められます。自社だけで対応するのが難しい場合は、税理士や公認会計士、中小企業診断士、M&Aアドバイザーといった専門家に相談することを検討しましょう。専門家は、最適な資金調達方法の選定や事業計画書のブラッシュアップ、金融機関との交渉など、多角的なサポートを提供してくれます。
資金調達の選択肢としてのM&A|中小企業の新たな可能性
中小企業が資金調達する方法としてM&Aも選択肢に含まれます。M&Aを実施すると会社を第三者に預ける、あるいは、子会社化することになりますが、大企業やグループの傘下に入れば財務基盤を強化できます。
潤沢な資金を得られれば、資金調達の問題は一気に解決する可能性があります。M&Aに対して「会社を売り払う」というネガティブなイメージを持つ経営者もいるかもしれませんが、近年では効果的な経営戦略として広く認知されています。特に中小企業においては、後継者不在問題の解決策としても注目されており、レコフデータの調査によると2023年のM&A件数は過去最高を記録しました。2024年以降もこの傾向は続くと見られ、M&Aはますます重要な選択肢となっています。
本場のアメリカではベンチャー企業がM&Aによって創業することも珍しくありません。また、赤字状態になりがちなベンチャー企業でもM&Aを活用できます。大企業の中には節税対策もかねて赤字経営の会社を買収しているケースがあり、買収後に経営再建も成功させています。
ただし、M&Aには財務や法務、人事など多岐にわたる専門知識と交渉力が不可欠です。買い手企業とのマッチングから条件交渉、契約締結まで複雑なプロセスを経るため、成功させるには信頼できる専門家のサポートが欠かせません。
M&Aを具体的に検討する際は、実績豊富なM&A仲介会社や経営コンサルタントといった専門家に相談し、二人三脚で進めることが成功の鍵となります。
M&Aをご検討の際は、ぜひM&A総合研究所にご相談ください。M&A総合研究所はさまざま業種で成約実績があり、経験豊富なアドバイザーがM&Aをフルサポートいたします。
料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です。(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)
無料相談をお受けしておりますので、M&Aをご検討の際はどうぞお気軽にお問い合わせください。
中小企業が資金調達を円滑に行うコツ

金融機関の種類や融資の方法などによっても融資の方針や流れが変わります。中小企業が資金調達を円滑に行うコツをご説明します。
自社の規模にあった金融機関を選ぶ
金融機関は、メガバンク、第一地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合など、さまざまな種類にわかれます。中小企業は、第一地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合などから融資を受ける機会が多い傾向です。
特に、信用金庫や信用組合は地域の発展・貢献を目的とした存在であることから、中小企業の融資に親身に応じてくれることでしょう。ただし、存在する地域が限られています。
また、地域に根差した金融機関のなかには、融資先の課題を把握して本業をサポートするところもあります。事業を支援する姿勢の有無を確認したいのであれば、金融機関のHPを確認したり、融資担当者と話したりするとよいでしょう。
融資の種類を知って適切な方法を選択
融資にはさまざまな種類があり、それぞれにメリットやデメリットがあります。メリットやデメリットを吟味しながら適切な方法を選択しましょう。
信用保証協会の保証にもとづく融資
信用保証協会は、中小企業の借り入れをサポートする公的機関です。中小企業が地方自治体や民間金融機関に融資を依頼する際に保証人になります。融資を申請した場合、信用保証協会にも保証の申し込みを行います。担保なしで融資を受けられる一方で、支払利息や保証料が必要です。
不動産を担保にする融資
不動産担保融資は、建物や土地などの不動産を担保に金融機関から借り入れする方法です。不動産の価値や借入者の支払い能力に応じて融資額が決定されます。無担保の場合と比べて高額の融資が受けられるだけでなく、返済期間を長期的に設定できるという長所があります。
その反面、担保の審査に時間がかかったり、返済不能になった場合に不動産を失ったりする点が短所です。
事業評価をもとにした融資
事業性評価融資は、財務データや保証・担保だけではなく、事業内容や成長可能性などを考慮に入れた融資方法です。
今まで、成長力があるのにかかわらず、決算書の内容が信頼性に欠けることにより、融資を受けられない企業がありました。その問題を受けて、金融庁は事業性評価にもとづく融資を促す方針を取るに至っています。
金融機関が事業性評価を行う際に注目する要素はさまざまです。経営理念や事業概要をはじめ、自社の強みや課題、今後の経営方針などがあります。事業性評価をもとにした融資を受ける際は、これらの要素を含めた事業計画書を作成して金融機関に事業を説明することが有効です。
自社の魅力をスムーズに伝える
金融機関の担当者は一人で数多くの案件を抱えているケースも少なくありません。時間が限られている以上、円滑に融資してもらうためには、自社の魅力をスムーズに伝える工夫が必要です。会社の状況や展望を言葉だけで話すのではなく、数値にもとづく計画を共有するとよいでしょう。
経営状態を伝えるのにおすすめなのがローカルベンチマークです。ローカルベンチマークとは、経営者や金融機関が企業の経営状態を共有して対話を行うためのフレームです。労働生産性や営業利益率などの財務情報や、企業の外部環境や技術力などの被財務情報を共有できます。
中小企業の資金調達の注意

中小企業は資金調達方法が限られているので、資金調達するために注意すべき点があります。方法によって注意点は変わりますが、ここでは基本事項を説明します。
会社の信頼を得る
株式や融資を利用するにせよ、重要なのは信頼を得ることです。金融機関は融資や借入をする際に、中小企業を信頼できるかどうかを絶対視します。もちろん、信頼が低くても担保を設定すれば借入できます。しかし、万が一を考えると中小企業にとってあまりよい選択肢とはいえません。
また、大企業と違って、中小企業の経営には不安定なイメージがともないます。したがって、信頼が得られるように、経営者は支援者に適切なビジネスプランを伝えることが重要です。そのため、経営者はビジネスプランや自社の強み、製品などを精査する必要があります。
しかし、せっかく練り上げたビジネスプランも、伝え方が悪ければ相手の印象が変わってしまう恐れがあります。その点、プレゼンスキルを磨いたり、自社の担当者と綿密にコミュニケーションを取ったりすることも大切です。
株式を発行する時はバランスを考慮
資本を増やす際に、株式発行による資金調達方法を取る場合、株式の設定方法が重要です。議決権を付与することを含め、設定によっては株式の購入者数が変わります。株式の権限を強くすれば購入者が増える可能性は高いですが、発行しすぎると経営権を脅かされるリスクがあります。
対して株式の権限を弱くすると購入者が減る可能性があります。したがって、株式を発行する場合、いかに経営権を維持しながら資金調達するかが重要です。
資金の運用は慎重に
中小企業の経営者にとって重要なのは、資金調達に成功した後の資金の運用です。なぜなら、会社の売上を増加させることで信頼を勝ち得るからです。せっかく得た資金を無駄にしては、経営に支障をきたすだけではなく、企業の信頼を損なう恐れがあります。
あくまで倹約を第一に掲げて無駄なく資金を運用し、着実に売上を引き伸ばすことが経営者にとって大切です。
※関連記事
中小企業が資金不足に陥らないためには

最後に、中小企業が資金不足に陥らない方法をお伝えします。ここまでに資金の運用にかんする注意点をお伝えしましたが、その点は日ごろから徹底すべきことです。日常業務のプロセスや役員報酬などを見直し、無駄なコストを省くだけでもかなり出費を抑えられます。
ましてや経営者が節税対策と称して経営に影響しない資産(高級外車など)を購入するようなことは避けるべきでしょう。会社によってはコスト削減を徹底するだけで赤字状態から脱却したケースもあります。
また、中小企業が注意を怠ってしまいがちなのが現金です。中小企業は現金を確保しているケースが少なく、緊急で運転資金が必要な時に資金を投入できないことも珍しくありません。現金を確保していないために、売り上げが入る前に運転資金が底を尽いて黒字倒産する場合もあります。
この点は、大企業でも起こり得るリスクであり、黒字だからといって決して油断できません。現金を一定以上確保するには、コストの削減と適切な資金繰りが重要になります。
まとめ

中小企業の資金調達について紹介しましたが、理解していただけたでしょうか?中小企業が資金調達する際は、リスクや将来的な経営について考慮する必要があります。専門家に相談し、サポートを受けながら進めていきましょう。
M&A・事業承継のご相談なら24時間対応のM&A総合研究所
M&A・事業承継のご相談は成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A総合研究所にご相談ください。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴
- 譲渡企業様完全成功報酬!
- 最短43日、平均7.2ヶ月のスピード成約(2025年9月期実績)
- 上場の信頼感と豊富な実績
- 譲受企業専門部署による強いマッチング力
M&A総合研究所は、M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。
また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。
相談も無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたにおすすめの記事

M&Aとは?目的・メリットから手法、最新動向までわかりやすく解説
M&Aは、事業承継や事業拡大の有効な手段として注目されています。しかし、成功には目的や手法の正しい理解が不可欠です。本記事では、M&Aの基礎知識から目的、メリット・デメリット、最...

買収とは?用語の意味やメリット・デメリット、M&A手法、買収防衛策も解説
買収には、友好的買収と敵対的買収とがあります。また、買収に用いられるM&Aスキーム(手法)は実にさまざまです。本記事では、買収の意味や行われる目的、メリット・デメリット、買収のプロセスや...

現在価値とは?計算方法や割引率、キャッシュフローとの関係をわかりやすく解説
M&Aや投資の意思決定するうえでは、今後得られる利益の現時点での価値を表す指標「現在価値」についての理解が必要です。今の記事では、現在価値とはどのようなものか、計算方法や割引率、キャッシ...

株価算定方法とは?非上場企業の活用場面、必要費用、手続きの流れを解説
株価算定方法は多くの種類があり、それぞれ活用する場面や特徴が異なります。この記事では、マーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチといった株価算定方法の種類、株価算定のプロセス、株...

赤字になったら会社はつぶれる?赤字経営のメリット・デメリット、赤字決算について解説
法人税を節税するために、赤字経営をわざと行う会社も存在します。しかし、会社は赤字だからといって、必ず倒産する訳ではありません。逆に黒字でも倒産するリスクがあります。赤字経営のメリット・デメリット...
関連する記事
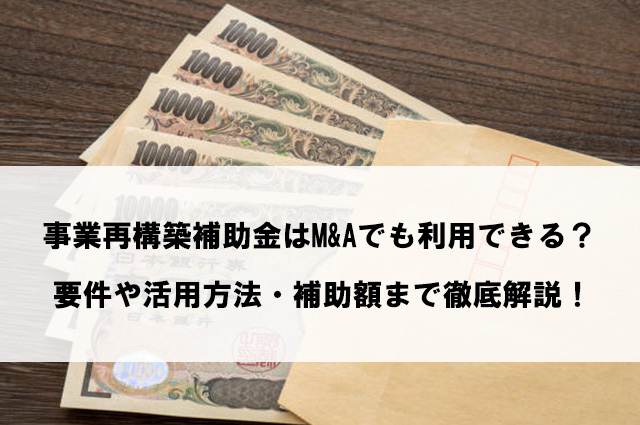
事業再構築補助金はM&Aでも利用できる?要件や活用方法・補助額まで徹底解説!
事業再構築補助金は要件を満たせば、中小企業や中堅企業に補助金を支給する制度です。中にはM&Aを実施するときに制度を利用する企業も存在します。この記事ではM&Aを実施しても事業再構...

DDSとは?DESとの違いや手順・活用方法・メリット・デメリットまで解説!
企業再建手法の1つとして注目されているDDS。そんなDDSとよく似た言葉にDESがありますが、それぞれの違いは何なのかを本記事で解説していきます。またDDSを実施する手順や活用方法、メリットやデ...

CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)とは?メリット・デメリットを解説!
ベンチャー企業へ投資をするCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)。VC(ベンチャーキャピタル)と混同されがちなCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)とは何なのか、活用するメリット・デメリ...

エンジェル投資家について徹底解説!メリットやデメリット・探し方は?
企業がイグジット(上場、ハイバリエーションでの売却)をした際のキャピタルゲインを目的とした投資を行うエンジェル投資家。返済義務がない投資をメインとしているエンジェル投資家について知らない人も多い...

シード期とは?定義やスタートアップの資金調達方法・成功のポイントを解説!
成長していく過程においてIPOやM&Aを活用することも重要ですが、具体的にどのようなポイントを抑えれば良いのでしょうか。 この記事では、シード期の定義やスタートアップの資金調達方法・成...

M&Aにおけるエスクローの意味とは?メリット・デメリットについて紹介!
日本のM&Aでは、活用されているケースは少ないとされている仲介サービス「エスクロー」があります。海外では多く活用されていますが、この「エスクロー」とはどういう意味なのでしょうか。ここでは...

投資銀行のM&Aにおける役割とは?部門ごとの業務内容や違いを解説!
投資銀行は銀行の一種ではないと聞くと、驚かれる方が多いかもしれません。投資銀行は、銀行業ではなく証券業に分類されます。本記事では、投資銀行の概要、投資銀行がM&Aにおける役割、投資銀行の4大業務...

スケールメリットが経営に与える効果は?意味や仕組みを具体例に徹底解説!
スケールメリットとは、同種の業種やサービスが多く集まることで単体よりも大きな成果を生み出せることです。会社経営を行う際、不必要な経費を活用しているケースが多いです。このような課題を解決できるスケ...

株式分割とは何?仕組みやメリット・デメリットなどをわかりやすく解説!
株式分割とは、1株をいくつかに分割して、発行済みの株式枚数を増やすことです。株式分割には企業側、投資家側にメリット・デメリットが存在します。理解していないとトラブルに発展する可能性があります。そ...

























立命館大学卒業後、地方銀行にて中堅中小企業を担当。ファイナンス、ビジネスマッチング等に従事した後、本部専門部署にて事業承継支援を専門として実績を積む。
その後、大手M&A仲介会社において、事業承継や戦略的な成長を目的としたM&Aを業種・規模問わず、多数成約に導く。
M&A総合研究所では、製造業や建設業、不動産業など幅広い業種を担当。