M&Aとは?メリット・手法・最新動向を専門家がわかりやすく徹底解説
2022年6月6日更新資金調達
種類株式とは?意味や一覧、活用事例をわかりやすく解説
原則として株主の権利は平等とされていますが、種類株式を保有している株主は通常とは異なる処遇を受ける決まりです。本記事では、種類株式の一覧・事業承継対策や資金調達など種類株式の活用事例・種類株式の登記事項などを中心に解説します。
種類株式

株式会社にとって株式は資金調達や経営権の行使などを行う際に必要不可欠な存在ですが、株式は普通株式のほかに種類株式の発行も可能です。原則的に各株主の権利は平等とされていますが、種類株式を保有している株主は通常とは異なる処遇を受けます。
本記事では、種類株式とはどういった株式なのかわかりやすく紹介します。大企業のみならず中小企業・ベンチャーの経営に携わっている方にも必見の内容です。
種類株式とは?種類株式の意味

はじめに、種類株式の意味を解説します。種類株式とは、株式会社が内容の異なる2種類以上の株式を発行した場合における各株式のことです。国際的に使われている株式様式のひとつであり、英語では「Class Share」と呼ばれています。
通常、株式会社の各株主は平等の権利を有しており、保有する株式数に応じて株主総会において経営権の行使や配当金の受領などが可能です。一方で、株主が持つ経済的な面や会社支配の面など多様なニーズを捉えるために、種類株式によりこうした株主の権利について通常(普通株式)と異なる規則を定めています。
とはいえ、既存の株主などが不測の損害を被らないように、株式の内容に関してはある程度の枠が設定されています。種類株式の発行は会社法で認められており、所定の手続きを踏めば合法的に発行(変更)可能です。代表例としては、「(配当)優先株式」が挙げられます。
上記は、普通株主よりも優先的に配当金を授受できる権利が付された種類株式です。保持する株主にとって有利な権利が付されており、その他の種類株式と合わせて利用されるケースも多く見られます。例えば、配当優先株式によって優先的に配当金を受け取れる代わりに、議決権が付されていないケースが多いです。
このように、普通株式とは異なる権利などが付されており、株式会社の運営におけるさまざまな場面で活用されています。また、種類株式は、交付時期に応じてA種類株式・B種類株式と名付けられるケースもあります。
通常、後から発行された種類株式の効力が優先されますが、このシステム自体も規定により変更可能です。なお、定款に定められたすべての株式が均一な内容である場合は、種類株式には該当しません。
加えて、種類株式発行会社の要件を満たすには内容の異なる2種類以上の株式を発行できる旨が定款に規定されていれば足りるため、実際に2種類以上の株式を発行している必要はない点にも留意しておきましょう。
種類株式の一覧

ひとことに種類株式といっても、種類株式には全9種類が存在しており、それぞれ規定内容が異なるため注意が必要です。本章では、9種類の種類株式を一覧にして取り上げます。
①剰余金の配当規定付株式
これは、企業が剰余金を配当する際に、その配当について地位の優劣が規定されている種類株式です。「優先株式」はこの一種であるほか、配当が後回しになるよう規定された「劣後株式」も存在します。
②残余財産の分配規定付株式
これは、会社の解散時などに発生する残余財産の分配について規定された種類株式です。剰余金と同様に優先株式や劣後株式などが存在しており、残余財産の分配順が区別されています。とはいえ、一般的な優先株式は、剰余金に関する優先を意味するため注意してください。
③譲渡制限株式
これは、すべてまたは一部の株式について、譲渡する際に会社の承認を得る義務を定めた種類株式です。ほとんどの中小企業では、経営権の分散防止を目的に掲げて譲渡制限株式を導入しています。
なお、譲渡制限株式を導入している会社を「株式譲渡制限会社」、譲渡制限を設定していない会社を「公開会社」、発行されている株式がすべて譲渡制限株式である会社を「非公開会社」と呼んでいます。
④拒否権付株式
これは、会社に関する決議事項について、株主総会決議に加えて種類株主から構成される種類株主総会の決議を必要とする旨を定めた種類株式です。普通株主の賛成数とは無関係に決議事項を否決できることから、「拒否権付株式」と呼ばれています。
また、「黄金株」とも呼ばれており、敵対的買収に対する防衛策としての活用事例が多く存在します。例えば、敵対的買収により相当数の議決権を取得された場合でも、拒否権付株式を友好的な株主に保有させておけば買収の成立を阻止することが可能です。
なお、拒否権付株式の流出は通常の経営判断に悪影響を及ぼすおそれがあることから、譲渡制限規定を同時に付与してリスクを防ぐケースが多いです。
また、敵対的買収に限らず有効的なM&Aも、拒否権付株式の存在は非常に大きな影響を及ぼします。もし、M&A実施に際して拒否権付株式の存在に不安がある場合は、M&A総合研究所にご相談ください。
M&A総合研究所には知識・経験が豊富なアドバイザーが在籍しており、これまでに培ってきたノウハウを生かしてM&A手続きをフルサポートしております。
通常、M&Aでは半年〜1年程度の期間が必要ですが、M&A総合研究所ではスピーディーなサポートを実践しており、最短3ヵ月での成約実績を有している点も強みです。
料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。相談料は無料となっておりますので、拒否権付株式の存在によりM&A実施に不安がある場合はお気軽にお問い合わせください。
⑤議決権制限株式
これは、決議事項の一部または全部について議決権を行使できない旨を定めた種類株式です。このうち、議決権を一切行使できないものは、「無議決権株式」と呼ばれています。
この種類株式を利益にのみ興味がある(経営権に興味がない)株主に対して付与すると、株主総会における議決権が制限されるために経営陣の決定権を強化できます。なお、この種類株式は、配当優先株式と組み合わせて使用するケースがほとんどです。
⑥取得請求権付株式
これは、株主が会社に対して、保有する株式の対価に金銭や他の株式などの財産を請求できる権利が規定された種類株式です。株主からすれば投資リスクを軽減できるため保持しやすくなる一方で、会社にとっては資金調達が容易になるメリットがあります。
⑦取得条項付株式
これは、会社に一定事由が生じた際に、会社側がその株式を強制的に株主から取得できる旨が定められた種類株式です。取得請求権規定と同様に最終的に会社が株式を回収するものの、こちらでは会社側が主体となって株式取得を行います。
会社側は強制的に株式を取得できるため、株式の保有者は原則株主としての地位や権利を完全に失います。
⑧全部取得条項付株式
取得条項付株式の中でも、会社が対象のすべての株式を取得できるものは、「全部取得条項付株式」と呼ばれています。この種類株式を活用すると、100%減資を能動的に行うことが可能です。しかし、株式取得の際は、株主総会で決議を得る必要があるため注意してください。
⑨役員選任権付株式
これは、種類株主総会において取締役または監査役を選任する議決権が付された種類株式です。つまり、この種類株式を保有する株主は、普通決議などを経ずに役員を選任できます。
この種類株式は主にベンチャーキャピタルから出資を募る際に多用されていますが、「公開会社」と「指名委員会等設置会社」では法律の定めにより役員選任権付株式を発行できない点に注意が必要です。
種類株式の活用事例

株式会社があえて種類株式を発行する背景には、活用により得られるメリットが大きい点が深く関係しています。本章では、種類株式の活用事例を3つに絞ってまとめました。
①事業承継対策
事業承継とは、現経営者から後継者に対して会社の経営権や資産などを引き継ぐ手続きをさします。多くの中小企業が課題に掲げている事業承継問題を解消するうえで、種類株式の活用は有効策です。もしも株式が分散している状況で事業承継を行えば、後継者に議決権が集中させられないおそれがあります。
もともと株式会社では保有する議決権数により経営への影響力が決まるため、後継者の持ち株数が少ないと事業承継後の経営に支障が生ずる可能性が高いです。
上記の問題を解決するには、後継者に議決権のある普通株式や拒否権付株式を承継させる一方で、経営に関係しない相続人に対しては無議決権株式を引き継いで議決権を後継者に集める対策が有効です。このような形式で種類株式を活用すると、事業承継後の経営を円滑に進められます。
②資金調達
もともとベンチャー企業では、資金調達の手段としてVCから出資を受けるケースが一般的です。しかし、このときの資金調達方法が普通株式の付与による場合、経営権の行使に悪影響が生じるおそれがあるため、種類株式(議決権制限株式や配当に関する優先株式など)の利用により付与する事例が多く見られます。
また、種類株式は、上場企業の資金調達方法としても活用されています。例えば、銀行からの自己資本規制への対策として非累積的優先株式の発行により自己資本比率を上昇させるケースや、企業再生のために優先株式などを用いて資本を集めるケースなどが代表的です。
③合弁会社の設立
合弁会社とは、複数の会社が互いに出資し合って設立・運営する会社です。複数の事業者が合弁会社を設立する際、柔軟な機関設計を意図して種類株式を用いる事例が見られます。そもそも1:1の比率でそれぞれの企業が普通株式を所持するケースを除き、少数株主は株主総会の議決に関与できません。
しかし、種類株式を活用すれば、株式保有割合とは異なる方法で剰余金の配当・残余財産の分配などを実施できます。また、無議決権株式を活用すれば、特定の役員に対するインセンティブの付与も可能です。
このように出資割合による不公平性などを控除できる点で、合弁会社の設立時に種類株式を使用する施策は非常に有効です。
種類株式の発行・変更手続き

本章では、種類株式の発行や普通株式を種類株式に変更する手続きなどを取り上げます。新たに種類株式の発行を希望する場合、まずは種類株式発行会社になるために定款変更の特別決議を経なければなりません。
特別決議では原則として議決権の過半数出席と出席議決権の3分の2を上回る賛成が必要となるため、普通決議と比べて決議要件が厳しいです。この要件を満たして種類株式発行会社と認められれば、晴れて種類株式を発行できます。
また、実際に「種類株式を交付する」もしくは「普通株式から変更する」際は、種類株式の内容ごとに異なる手続きを行う必要があります。例えば、「全部取得条項付株式」の発行には株主総会の特別決議、「議決権制限株式」の発行には特殊決議がそれぞれ必要です。
以上のことから、種類株式の内容に応じていかなる手続きが必要となるのか、事前に調べておく必要があります。
種類株式の登記事項

「種類株式を発行する」もしくは「普通株式から種類株式に変更する」際は、登記手続きが求められます。種類株式の主な登記事項は、以下の3項目です。
- 発行済み株式総数
- 発行可能株式総数
- 発行可能種類株式の総数及び種類株式の内容
相続における種類株式の評価

最後に、相続における種類株式の評価方法を取り上げます。相続(事業承継)シーンは、会社の株式を各相続人が受け継ぐ仕組みです。このときには、一定の評価方法を用いて株式の価格を評価したうえで、その価格を参考に相続税の課税を受ける必要があります。
相続税を正確に把握するには、それぞれの種類株式の株価を評価する方法を事前に把握しておかなければなりません。ここからは、「拒否権付株式」「配当優先株式」「無議決権株式」「社債類似株式」の4つの種類株式ごとに評価方法を紹介します。
①拒否権付株式
拒否権付株式では、普通株式と同様の方法で相続時の価格を算定します。株式の評価方法は、会社の規模などにより異なる仕組みです。株価算定方法に関しては別の記事で詳しくまとめておりますので、章末の関連記事をご参照ください。
②配当優先株式
配当優先株式は、「類似業種比準方式」もしくは「純資産価額方式」により評価を行います。ここからは、それぞれの方式についてまとめました。
類似業種比準方式
類似業種比準方式とは、評価対象と事業内容などが類似する上場企業を基準に株価算定を行う方法です。この評価方法は、一般的に大会社の株式相続で活用されています。類似業種比準方式を用いて種類株式の株価を評価する場合、株式に関わる配当金(資本金額の減少を除く)にもとづいて評価する仕組みです。
計算方法を簡単に紹介すると、類似業種の株価に対して、類似業種と評価対象の配当金・年利益・純資産のそれぞれの比を乗じます。
純資産価額方式
純資産価額方式とは、貸借対照表に記載された純資産額を基準に株価を評価する方法です。この評価方法は、主に小会社の相続で利用されています。純資産価額方式を用いる場合、種類株式・普通株式を問わず、通常どおりの株式計算によって評価を行う仕組みです。つまり、下記の計算式が用いられます。
- 株価=(時価資産ー負債ー法人税等)÷発行済株式総数
③無議決権株式
無議決権株式は原則として普通株式と同様に評価を行いますが、例外的に一定要件を満たす場合は「原則的評価方式」により評価した価格から5%を控除した金額を使用できます。一定要件とは、「相続税の法定申告期限までに遺産分割協議が確定している」などです。
ただし、無議決権株式の評価時に控除した5%については、議決権株式の価額に加算しなければなりません。これは、相続した方の総株価額は変わらないことを意味します。
④社債類似株式
社債類似株式とは実質的に社債の性質を保有している株式であり、以下の要件を満たすものです。
- 配当金を優先分配する
- 残余財産の分配は発行価額を超えて分配しない
- ある一定の期日に、発行会社は本件株式のすべてを発行価額で償還する
- 他の株式を対価とする取得請求権が設定されていない
- 議決権が設定されていない
評価方法は社債と同様の方法を適用する一方で、既経過利息に値する配当金の加算調整については実行しない点に注意しましょう。
種類株式のまとめ

種類株式を保有している株主は、通常とは異なる処遇を受けます。事業承継対策や資金調達など種類株式の活用事例を参考にしながら、種類株式の有効活用を目指しましょう。
とはいえ、種類株式を効果的に利用すれば会社にさまざまな利益をもたらしますが、株主側にも利益をもたらすよう設定する必要がある点は留意しておく必要があります。種類株式は専門性の高い内容であるため、税理士・会計士などの専門家にサポートを依頼するのも良いでしょう。
本記事の要点は、以下のとおりです。
・種類株式の一覧
→剰余金の配当規定付株式、残余財産の分配規定付株式、譲渡制限株式、拒否権付株式をはじめとする9種類
・種類株式の活用事例
→事業承継対策、資金調達、合弁会社の設立
・種類株式の登記事項
→発行済み株式総数、発行可能株式総数、発行可能種類株式の総数及び種類株式の内容
M&A・事業承継のご相談なら24時間対応のM&A総合研究所
M&A・事業承継のご相談は成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A総合研究所にご相談ください。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴
- 譲渡企業様完全成功報酬!
- 最短43日、平均7.2ヶ月のスピード成約(2025年9月期実績)
- 上場の信頼感と豊富な実績
- 譲受企業専門部署による強いマッチング力
M&A総合研究所は、M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。
また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。
相談も無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたにおすすめの記事

M&Aとは?メリット・手法・最新動向を専門家がわかりやすく徹底解説
M&Aは事業拡大や事業承継の有効な手段です。本記事ではM&Aの基礎知識から、2025年以降の最新動向、手法、メリット・デメリット、成功させるためのポイントまで、専門家が分かりやす...

買収とは?用語の意味やメリット・デメリット、M&A手法、買収防衛策も解説
買収には、友好的買収と敵対的買収とがあります。また、買収に用いられるM&Aスキーム(手法)は実にさまざまです。本記事では、買収の意味や行われる目的、メリット・デメリット、買収のプロセスや...

現在価値とは?計算方法や割引率、キャッシュフローとの関係をわかりやすく解説
M&Aや投資の意思決定するうえでは、今後得られる利益の現時点での価値を表す指標「現在価値」についての理解が必要です。今の記事では、現在価値とはどのようなものか、計算方法や割引率、キャッシ...

株価算定方法とは?非上場企業の活用場面、必要費用、手続きの流れを解説
株価算定方法は多くの種類があり、それぞれ活用する場面や特徴が異なります。この記事では、マーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチといった株価算定方法の種類、株価算定のプロセス、株...

赤字になったら会社はつぶれる?赤字経営のメリット・デメリット、赤字決算について解説
法人税を節税するために、赤字経営をわざと行う会社も存在します。しかし、会社は赤字だからといって、必ず倒産する訳ではありません。逆に黒字でも倒産するリスクがあります。赤字経営のメリット・デメリット...
関連する記事
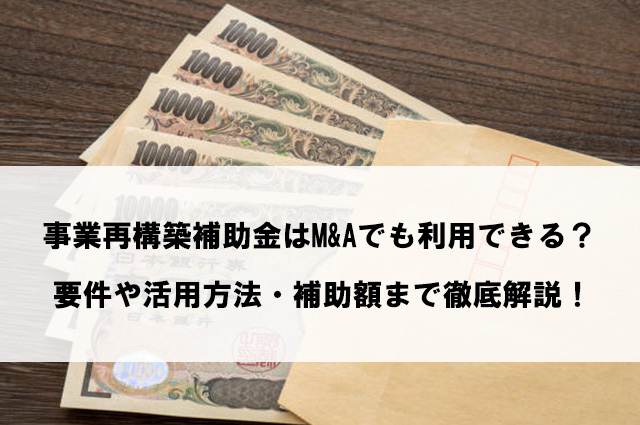
事業再構築補助金はM&Aでも利用できる?要件や活用方法・補助額まで徹底解説!
事業再構築補助金は要件を満たせば、中小企業や中堅企業に補助金を支給する制度です。中にはM&Aを実施するときに制度を利用する企業も存在します。この記事ではM&Aを実施しても事業再構...

DDSとは?DESとの違いや手順・活用方法・メリット・デメリットまで解説!
企業再建手法の1つとして注目されているDDS。そんなDDSとよく似た言葉にDESがありますが、それぞれの違いは何なのかを本記事で解説していきます。またDDSを実施する手順や活用方法、メリットやデ...

CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)とは?メリット・デメリットを解説!
ベンチャー企業へ投資をするCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)。VC(ベンチャーキャピタル)と混同されがちなCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)とは何なのか、活用するメリット・デメリ...

エンジェル投資家について徹底解説!メリットやデメリット・探し方は?
企業がイグジット(上場、ハイバリエーションでの売却)をした際のキャピタルゲインを目的とした投資を行うエンジェル投資家。返済義務がない投資をメインとしているエンジェル投資家について知らない人も多い...

シード期とは?定義やスタートアップの資金調達方法・成功のポイントを解説!
成長していく過程においてIPOやM&Aを活用することも重要ですが、具体的にどのようなポイントを抑えれば良いのでしょうか。 この記事では、シード期の定義やスタートアップの資金調達方法・成...

M&Aにおけるエスクローの意味とは?メリット・デメリットについて紹介!
日本のM&Aでは、活用されているケースは少ないとされている仲介サービス「エスクロー」があります。海外では多く活用されていますが、この「エスクロー」とはどういう意味なのでしょうか。ここでは...

投資銀行のM&Aにおける役割とは?部門ごとの業務内容や違いを解説!
投資銀行は銀行の一種ではないと聞くと、驚かれる方が多いかもしれません。投資銀行は、銀行業ではなく証券業に分類されます。本記事では、投資銀行の概要、投資銀行がM&Aにおける役割、投資銀行の4大業務...

スケールメリットが経営に与える効果は?意味や仕組みを具体例に徹底解説!
スケールメリットとは、同種の業種やサービスが多く集まることで単体よりも大きな成果を生み出せることです。会社経営を行う際、不必要な経費を活用しているケースが多いです。このような課題を解決できるスケ...

株式分割とは何?仕組みやメリット・デメリットなどをわかりやすく解説!
株式分割とは、1株をいくつかに分割して、発行済みの株式枚数を増やすことです。株式分割には企業側、投資家側にメリット・デメリットが存在します。理解していないとトラブルに発展する可能性があります。そ...
























立命館大学卒業後、地方銀行にて中堅中小企業を担当。ファイナンス、ビジネスマッチング等に従事した後、本部専門部署にて事業承継支援を専門として実績を積む。
その後、大手M&A仲介会社において、事業承継や戦略的な成長を目的としたM&Aを業種・規模問わず、多数成約に導く。
M&A総合研究所では、製造業や建設業、不動産業など幅広い業種を担当。