M&Aとは?メリット・手法・最新動向を専門家がわかりやすく徹底解説
2021年4月24日更新資金調達
有利子負債=悪とは限らない
有利子負債とは、利子が付帯している負債です。一般的に有利子負債が多い企業は、経営が苦しいイメージがあります。しかし成長過程の企業では半ば当然であり、業種の特性でも判断が分かれるのが有利子負債です。有利子負債の正体に迫ります。
有利子負債を検証する

有利子負債と聞くと悪いイメージを連想されてしまうことが間々あるようです。つまり、「有利子負債=借金経営=経営が苦しい」という三段論法が、一般的には思い浮かべられがちな傾向であるということでしょう。
確かに事業収益の中から有利子負債の返済のやり繰りをするのは、大変な部分があるかもしれません。しかし、返済ができなさそうな会社に資金を融資する金融機関などありません。そう考えると、有利子負債があることは、その会社の収益性に対する信用の証しとも言えます。
ただし、有利子負債が過剰にあるならば、それは会社の経営を左右しかねない問題にもなります。果たして有利子負債とは、どう解釈していいものなのか、その実態について検証してみましょう。
※関連記事
企業価値とは?企業価値向上施策、計算方法をわかりやすく解説
企業評価とは?企業評価方法や企業評価のメリット・デメリット
有利子負債とは

有利子負債の実態を明らかにするには、まず具体的に有利子負債とは何をさしているのか特定しましょう。有利子負債とは、利子がある負債を意味します。考えられる実在するものとしては、以下のものが該当することになります。
- 金融機関などからの借入金
- 普通社債
- 転換社債
- コマーシャルペーパー
同じ負債ではあるものの利子が発生しないものは、当然ながら有利子負債に該当しません。有利子負債ではない負債の具体的なものとしては、以下のものがあります。
- 支払手形
- 買掛金
- 未払金
なお、通常は有利子負債に該当しない支払手形ですが、割引手形として用いた場合には有利子負債として扱われます。割引手形とは、端的に言えば、支払手形の期日到達前に資金調達の必要が生じたときに、手形を担保にして銀行から借入をすることです。
この時、割引料という名目の手数料を支払うことになります。この割引料は実質的に利子に該当することになるため、手形の割引を行ったときは有利子負債と見なされるわけです。このように、有利子負債に該当するものが変化する場合があることも覚えておいてください。
そして、結局のところ一般的には、有利子負債は会社の財務状況の健全性を計るバロメーターとして注視されることになります。その場合に用いられる考え方が有利子負債比率です。有利子負債比率は、以下の計算式で求めることになっています。
- 有利子負債比率(%)=有利子負債の残高÷会社の自己資本×100
上記の計算結果が100%以下であれば、優良企業とされています。また、300%までは標準の水準ですが、それを超えていると要注意であり、数値が高ければ高いほど危険度が高いという判定になります。
有利子負債とM&A
有利子負債はM&Aでも大きな影響を与えます。自社が売却対象であれば、有利子負債の内実をきちんと説明しなければなりません。こちらが買収側であれば、相手の有利子負債について精査する必要があります。そして、その結果がM&Aの取引価格や条件に反映されることになります。
M&Aで有利子負債への十分な対応が必要なときは、M&A総合研究所にご相談ください。M&A総合研究所では豊富な知識と経験を持つアドバイザーがM&Aを徹底サポートいたします。
料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です。(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)会社売却・事業譲渡に関して、無料相談をお受けしておりますのでお気軽にお問い合わせください。
※関連記事
M&Aとは?M&Aの意味から手続きまでをわかりやすく解説!
M&Aのメリットとは?買い手・売り手のメリットやM&A戦略策定のメリットをご紹介
有利子負債の指標性

前述の有利子負債比率計算以外にも、自社の有利子負債の健全性を確認する方法があります。それは、他社の有利子負債状況との比較です。ただし、他社と有利子負債の比較を行うにあたっては、注意点があります。
有利子負債を比較するときの注意点
自社と他社との間で有利子負債を比べるケースでは、どのような相手を選ぶかが最重要ポイントです。結論から言うと、有名無名を問わず、同一業種の会社を比較対象に選びましょう。その理由は、業種によって有利子負債比率の傾向が変わるからです。
例えば、製造業のような設備投資・生産ラインの維持などに負担がかかる業種や、ソフトウェア業のように長期の開発期間を要する先行投資型のビジネスモデルの業種などは、資金繰り上、日常的に有利子負債が多くなるタイプの業種です。
自社が全く別の異業種であるにもかかわらず、上記のような有利子負債の多いタイプの会社との間で有利子負債の比率を比較しても、何の意味もありません。有利子負債の比較対象企業としてふさわしいのは、あくまでも同一業種の会社だけです。
有利子負債の比較判断
他社と有利子負債の比較を行う場合には、有利子負債の比較そのものだけでなく、比較対象企業の業績状況を確認しましょう。本来であれば、同一業種で業績状況も似ている会社との有利子負債比較がベストですが、そう簡単には注文どおりの対象は見つからないはずです。
その場合、業績状況の異なる同一業種を複数探し、自社との有利子負債の比較を行います。どちらの企業と有利子負債比率が近いかによって、自社の業績状況も含めた客観的な比較判断が得られるでしょう。
そして、大切なことは有利子負債の比較を行った後、その判断内容によっては、財務状況の改善など具体的な行動を取ることです。もちろん、財務状況が健全であると判断できたのなら何もすることはないのですが、その場合も状況を維持していくことには絶えず注意していくようにしましょう。
有利子負債は悪いものなのか?

有利子負債には利子があるわけですから、それが多過ぎれば会社の財務を圧迫するのは明白です。その状況ではお世辞にも、有利子負債に害はないとは言えません。また、現実に無借金経営を実現している会社もあり、その代表例である任天堂などは高収益経営を続けてきた成果と言えます。
しかし、無借金経営は優秀企業で、有利子負債のある会社はダメな会社と決めつけてしまうのは暴論です。まず、先の例として挙げた任天堂については、特筆的な成功を成し遂げてきたイレギュラーなケースであり、それをもって他社と比較できる類いのものではありません。
また、非上場企業でも有利子負債がない会社はいくつもありますが、その全てが必ずしも業績好調というわけではないという実態もあります。もっと言えば、有利子負債はないが経営状態は赤字であるという会社も少なくないのです。
有利子負債の存在意義
上述した製造業やソフトウェア業以外でも、例えば不動産業なども有利子負債があって当然の業種です。不動産業では、大型の不動産や物件を購入したり、ビルを建設する際に有利子負債を負い、その後、収入として入ってくるテナント料で返済する手法を取ります。
この場合、業態として有利子負債は必要不可欠な存在であり、経営上の欠点や害とは無縁のものです。有利子負債が、財政を圧迫しているわけでも何でもありません。むしろ、有利子負債の存在が事業の成長の証であるとする見方もできます。
また、成長過程にある企業であれば、どうしても先行投資型の資金繰りにならざるを得ません。そうなれば有利子負債に頼らざるを得ないでしょう。しかし、金融機関もその企業の将来性を見据えて融資します。
例えば、自転車操業のような資金繰り状態の会社には、それ以上の有利子負債を負わせるのは危険と判断し、融資は実行されないでしょう。そのことと比較して考えれば、有利子負債があるということは、金融機関から借入ができるだけの社会的信用性があると言えます。
この点に着目して有利子負債の存在を判断するなら、企業にとって有利子負債は決して悪とは限らないと言うことができるのです。ただし、それは、あくまでも適性、あるいは標準の有利子負債比率数値を維持している企業に限定されます。
※関連記事
経営に求められる判断
資金調達の方法
まとめ

有利子負債=借金と捉えれば、有利子負債はないほうが良いと考えるのが一般的です。無借金経営で高い利益率を誇る企業であれば、投資家からも支持されるでしょう。しかしながら、有利子負債がない事実が、必ずしもその会社の評価を上向きにさせるとは限らないのです。
業種によっては、有利子負債比率が異常な数値にならない限り、有利子負債があるのが当然のビジネススタイルということも多々あります。従って、有利子負債がある=良くない会社、有利子負債=悪という見方は、必ずしも全てのケースに当てはまるわけではありません。
M&A・事業承継のご相談なら24時間対応のM&A総合研究所
M&A・事業承継のご相談は成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A総合研究所にご相談ください。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴
- 譲渡企業様完全成功報酬!
- 最短43日、平均7.2ヶ月のスピード成約(2025年9月期実績)
- 上場の信頼感と豊富な実績
- 譲受企業専門部署による強いマッチング力
M&A総合研究所は、M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。
また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。
相談も無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたにおすすめの記事

M&Aとは?メリット・手法・最新動向を専門家がわかりやすく徹底解説
M&Aは事業拡大や事業承継の有効な手段です。本記事ではM&Aの基礎知識から、2025年以降の最新動向、手法、メリット・デメリット、成功させるためのポイントまで、専門家が分かりやす...

買収とは?用語の意味やメリット・デメリット、M&A手法、買収防衛策も解説
買収には、友好的買収と敵対的買収とがあります。また、買収に用いられるM&Aスキーム(手法)は実にさまざまです。本記事では、買収の意味や行われる目的、メリット・デメリット、買収のプロセスや...

現在価値とは?計算方法や割引率、キャッシュフローとの関係をわかりやすく解説
M&Aや投資の意思決定するうえでは、今後得られる利益の現時点での価値を表す指標「現在価値」についての理解が必要です。今の記事では、現在価値とはどのようなものか、計算方法や割引率、キャッシ...

株価算定方法とは?非上場企業の活用場面、必要費用、手続きの流れを解説
株価算定方法は多くの種類があり、それぞれ活用する場面や特徴が異なります。この記事では、マーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチといった株価算定方法の種類、株価算定のプロセス、株...

赤字になったら会社はつぶれる?赤字経営のメリット・デメリット、赤字決算について解説
法人税を節税するために、赤字経営をわざと行う会社も存在します。しかし、会社は赤字だからといって、必ず倒産する訳ではありません。逆に黒字でも倒産するリスクがあります。赤字経営のメリット・デメリット...
関連する記事
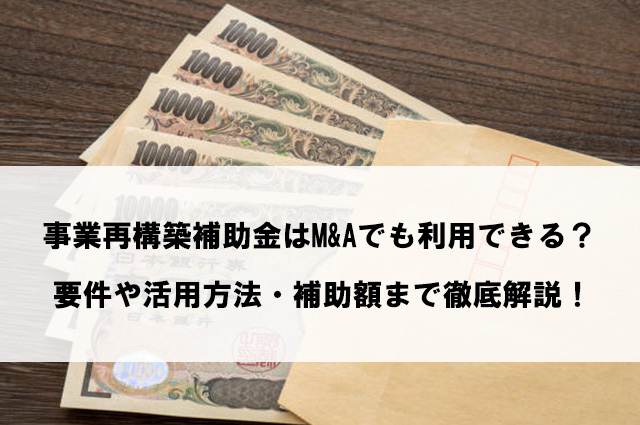
事業再構築補助金はM&Aでも利用できる?要件や活用方法・補助額まで徹底解説!
事業再構築補助金は要件を満たせば、中小企業や中堅企業に補助金を支給する制度です。中にはM&Aを実施するときに制度を利用する企業も存在します。この記事ではM&Aを実施しても事業再構...

DDSとは?DESとの違いや手順・活用方法・メリット・デメリットまで解説!
企業再建手法の1つとして注目されているDDS。そんなDDSとよく似た言葉にDESがありますが、それぞれの違いは何なのかを本記事で解説していきます。またDDSを実施する手順や活用方法、メリットやデ...

CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)とは?メリット・デメリットを解説!
ベンチャー企業へ投資をするCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)。VC(ベンチャーキャピタル)と混同されがちなCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)とは何なのか、活用するメリット・デメリ...

エンジェル投資家について徹底解説!メリットやデメリット・探し方は?
企業がイグジット(上場、ハイバリエーションでの売却)をした際のキャピタルゲインを目的とした投資を行うエンジェル投資家。返済義務がない投資をメインとしているエンジェル投資家について知らない人も多い...

シード期とは?定義やスタートアップの資金調達方法・成功のポイントを解説!
成長していく過程においてIPOやM&Aを活用することも重要ですが、具体的にどのようなポイントを抑えれば良いのでしょうか。 この記事では、シード期の定義やスタートアップの資金調達方法・成...

M&Aにおけるエスクローの意味とは?メリット・デメリットについて紹介!
日本のM&Aでは、活用されているケースは少ないとされている仲介サービス「エスクロー」があります。海外では多く活用されていますが、この「エスクロー」とはどういう意味なのでしょうか。ここでは...

投資銀行のM&Aにおける役割とは?部門ごとの業務内容や違いを解説!
投資銀行は銀行の一種ではないと聞くと、驚かれる方が多いかもしれません。投資銀行は、銀行業ではなく証券業に分類されます。本記事では、投資銀行の概要、投資銀行がM&Aにおける役割、投資銀行の4大業務...

スケールメリットが経営に与える効果は?意味や仕組みを具体例に徹底解説!
スケールメリットとは、同種の業種やサービスが多く集まることで単体よりも大きな成果を生み出せることです。会社経営を行う際、不必要な経費を活用しているケースが多いです。このような課題を解決できるスケ...

株式分割とは何?仕組みやメリット・デメリットなどをわかりやすく解説!
株式分割とは、1株をいくつかに分割して、発行済みの株式枚数を増やすことです。株式分割には企業側、投資家側にメリット・デメリットが存在します。理解していないとトラブルに発展する可能性があります。そ...
























立命館大学卒業後、地方銀行にて中堅中小企業を担当。ファイナンス、ビジネスマッチング等に従事した後、本部専門部署にて事業承継支援を専門として実績を積む。
その後、大手M&A仲介会社において、事業承継や戦略的な成長を目的としたM&Aを業種・規模問わず、多数成約に導く。
M&A総合研究所では、製造業や建設業、不動産業など幅広い業種を担当。