M&Aとは?メリット・手法・最新動向を専門家がわかりやすく徹底解説
2021年4月22日更新資金調達
銀行融資と金利の基礎知識!算出方法、低金利で融資を受ける方法をご紹介
銀行融資の金利は低い傾向ですが、融資の条件が厳しいことが知られています。低金利で融資してもらうには保証協会付き銀行融資の活用などがあげられます。本記事では銀行融資の基礎知識を中心に、金利算出方法や低金利で融資を受ける方法を解説します。
銀行融資の金利

会社が資金調達する方法には様々あります。そのほとんどは、金融機関からの借り入れか、株主からの投資募集です。借り入れ先は、銀行、商工会議所、消費者金融などが一般的です。一方で投資を募る場合、新規の株式を発行して株主を増やす方法があります。
資金調達の際には「信用」が必要です。返済能力、投資をする価値などの点を審査されます。特に銀行からの融資は、通常よりも借り入れ審査が厳しくなります。
信用力を前提として、金融機関から融資を受ける際には金利が発生します。今回は、銀行融資の金利を解説します。
※関連記事
中小企業向けの融資制度
銀行融資とは?

銀行融資における基礎知識と金利についてご紹介します。
銀行融資の基礎知識
銀行は、お金を貸してくれる場所でもあります。預金者のお金を貸し出して金利で利益を得ています。銀行融資は他の金融機関よりも低金利で、金利が1%を下回るケースが大半です。
一般の預金者は、銀行に絶大な信頼を置いてお金を預けています。銀行は預金者のお金を借りる形で融資を実施しているので、返済されない事態があってはいけません。それゆえ、銀行融資の審査は厳しいです。
銀行融資の金利
消費者金融と比較すると、銀行で受けられる融資は金利が圧倒的に低いです。銀行は日本銀行によって定められた金利によって融資を実施し、基本的に金利は統一されています。詳しい推移や金利の具体的な数字は、日本銀行のホームページに掲載されています。
バブル期は、銀行は8%程度の高金利で融資を行なっていました。しかしバブルが崩壊すると、景気と同様に金利も下落しました。さらに、1992年にはゼロ金利政策が導入され、ついに現在はマイナス金利になっています。
また、人口に対して金融機関が多く、業界内で価格競争状態になっているのも、低金利を引き起こしている要因の一つです。
銀行融資の金利算出方法

銀行融資の金利=「調達に要するコスト」+「経費」+「収益利率」+「信用にかかるコスト」です。各要素の内容をそれぞれ見てみましょう。
調達に要するコスト
銀行は無限にお金を持っているわけではないので、お金を調達しなくてはいけません。調達にはコストがかかります。販売店に例えると、仕入れのイメージです。
経費
金利の算出方法に関わる経費とは、上記の調達コストに伴う金額や、店舗運営に要する金額です。経費はその土地の物価などによっても左右されるので、金利に高低差が生まれます。
収益利率
収益利率とは、銀行が目指す売上高を表す数値です。銀行も利益を生み出せなければ潰れてしまいます。売上高を達成するために、一定の利率を加算します。
信用にかかるコスト
信用にかかるコストとは、主に中小企業を中心に掛けられる利率です。経営を継続させる力の有無を、独自のランク付けによって区分して、該当する利率を掛けます。信用コストは、借りる個人や会社によって変わります。融資期間が長いほど倒産リスクを孕んでいるとみなされ、金利も高くなる傾向にあります。
※関連記事
新規事業立ち上げにおける融資の活用
低金利で融資を受ける方法

銀行融資の金利は、他の金融機関と比較すると非常に低いです。ですが、さらに銀行融資の金利を低くする方法があります。
信用保証協会付き融資を利用する
中小企業が銀行から融資を受けやすくするために「信用保証協会」という公的な組織が存在します。会員に認定されれば、万が一のときには保証協会が返済を保証してくれます。
保証協会付き銀行融資を選択すると低金利になります。保証協会が付いている銀行融資では、銀行融資金利の信用にかかるコストが圧倒的に低く設定されています。金利には固定金利と変動制の金利があり、若干の違いが生じるので注意です。
また、保証協会が付いている融資には、金利の他に別途で保証料が必要になる点にも注意です。つまり、保証料と変動制の金利で、通常の銀行融資の金利よりも高くなる場合があります。
業績を良くする
会社の業績が上がると、返済の能力が高まったと銀行に認識されます。つまり、信用にかかるコストのランクも上がり、金利が下がります。融資期間を短くしたり、融資金額を少なくしたりするのも金利を下げる方法ですが、会社の資金繰りを考慮すると業績を良くする手法が適切です。
複数の銀行で見積もりを実施
複数の銀行で見積もりを行い、1番低い金利で融資を受けられる銀行を選ぶのも効果的です。銀行は、融資を実施して利益を獲得するのが目的です。よって、銀行間で価格競争が発生すると通常よりも低金利で融資を実行してくれる可能性があります。
しかし、時間がかかるので急いでいる場合には不向きな方法です。業績が悪い時にこの方法を使用すると、お金が足りないまま経営を続ける必要が生じます。したがって、あくまでも融資を最優先として考えるべきでしょう。
融資銀行を変更する
銀行融資の金利を低くするために、融資先の銀行を変更する方法もあります。銀行には新たな融資先を獲得する目標数値があるため、融資の乗り換えをした人に対して金利を下げるケースもあります。
キャンペーンの利用
銀行は新規顧客獲得のため、個人向けのキャンペーンを実施することが多いです。タイミングによっては法人向けのキャンペーンが行われることもあります。融資を受ける前に複数銀行のキャンペーン情報をチェックしておくと良いでしょう。
スプレッド融資を利用する
スプレッド融資とは、業績が良い会社が受けられる短期融資です。具体的な期間は1年以内です。1年以内に弁済可能と認められた会社のみが利用できます。しかし、通常の銀行融資よりも融資条件が厳しく、低金利ですが借りられない場合もあるので注意が必要です。
変動制の金利を選択する
銀行から融資を受ける際は、変動制金利を選択した方が安くなります。固定金利と比べると変動制金利には動きがあるため、融資期間内に金利が変動します。業績が良くなったり、市場の金利が低下したりした際には金利も当然下がります。しかし、業績悪化や金利価格の上昇となれば、銀行融資の金利も上がるリスクを伴います。
なぜ金利は低い方が良いのか

金利が低いと会社の財務体制を調整しやすいです。低金利で融資を受けるメリットと、銀行以外の低金利で融資が受けられる機関を簡単にご紹介します。
低金利で融資を受けるメリット
融資を検討している時点で、自社のお金だけでは経営が回らない可能性が高いです。そうなると、少しでも低金利で融資を受けたいと考えるのは当然です。
また、銀行から融資を受ければ利益を生み出す機材の導入や店舗の拡大なども実施可能になります。その結果業績が上がれば、銀行の融資を返済する必要があります。このとき、金利が高いと借りた額よりも高い金額を返済しなくてはなりません。
せっかく生み出した利益の多くを返済に充てるのは非常に残念です。 より低い金利で返済額を減らせるのであれば、低金利に越したことはありません。低金利であればあるほど返済額が少なくすみます。
低金利で融資が受けられる銀行以外の機関
なお、融資の相談先は何も銀行だけではありません。低金利で融資を受けたいと考える場合には、国が運営する日本政策金融公庫や地方自治体、商工会議所・商工会などに相談するのもおすすめです。詳しくは下記関連記事をご参考にしてみてください。
資金調達には様々な方法があり、近年ではM&A(企業・事業の合併と買収)を実施する中小企業が増えています。M&Aを実施し、事業再生や経営基盤の強化を成功させた企業も数多く存在します。
M&Aにおける資金調達も検討したい場合は、M&A総合研究所にご相談ください。M&A総合研究所ではM&Aアドバイザーによる専任フルサポートを行っています。
料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
まとめ

銀行融資の金利は低い方が良いですが、最優先は融資を受けることです。金利ばかり考えていると、時間が経過して業績が悪化してしまいます。その結果、さらに高い金利での融資を受ける事態に陥ります。
銀行融資を受ける条件はかなり厳しく、低い金利を目指すのは容易ではありません。まずは経営を安定させるのが大切なので、どの融資なら確実に借りられるのかを見極める必要があります。要点をまとめると下記になります。
・銀行融資の金利の特徴
→消費者金融と比較すると、低金利だが条件が厳しい
・銀行融資の金利算出方法
→調達に要するコスト+経費+収益利率+信用にかかるコスト・低金利で融資を受ける条件
→保証協会付き銀行融資の活用、業績の改善、複数の銀行を比較、融資銀行の変更、キャンペーンの利用、スプレット融資の利用、変動制金利を選択
M&A・事業承継のご相談なら24時間対応のM&A総合研究所
M&A・事業承継のご相談は成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A総合研究所にご相談ください。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴
- 譲渡企業様完全成功報酬!
- 最短43日、平均7.2ヶ月のスピード成約(2025年9月期実績)
- 上場の信頼感と豊富な実績
- 譲受企業専門部署による強いマッチング力
M&A総合研究所は、M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。
また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。
相談も無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたにおすすめの記事

M&Aとは?メリット・手法・最新動向を専門家がわかりやすく徹底解説
M&Aは事業拡大や事業承継の有効な手段です。本記事ではM&Aの基礎知識から、2025年以降の最新動向、手法、メリット・デメリット、成功させるためのポイントまで、専門家が分かりやす...

買収とは?用語の意味やメリット・デメリット、M&A手法、買収防衛策も解説
買収には、友好的買収と敵対的買収とがあります。また、買収に用いられるM&Aスキーム(手法)は実にさまざまです。本記事では、買収の意味や行われる目的、メリット・デメリット、買収のプロセスや...

現在価値とは?計算方法や割引率、キャッシュフローとの関係をわかりやすく解説
M&Aや投資の意思決定するうえでは、今後得られる利益の現時点での価値を表す指標「現在価値」についての理解が必要です。今の記事では、現在価値とはどのようなものか、計算方法や割引率、キャッシ...

株価算定方法とは?非上場企業の活用場面、必要費用、手続きの流れを解説
株価算定方法は多くの種類があり、それぞれ活用する場面や特徴が異なります。この記事では、マーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチといった株価算定方法の種類、株価算定のプロセス、株...

赤字になったら会社はつぶれる?赤字経営のメリット・デメリット、赤字決算について解説
法人税を節税するために、赤字経営をわざと行う会社も存在します。しかし、会社は赤字だからといって、必ず倒産する訳ではありません。逆に黒字でも倒産するリスクがあります。赤字経営のメリット・デメリット...
関連する記事
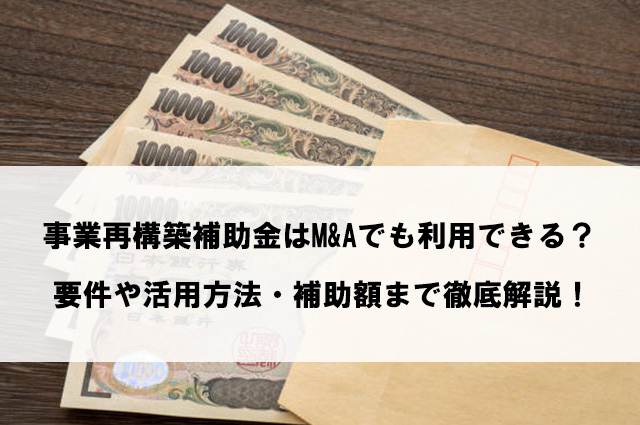
事業再構築補助金はM&Aでも利用できる?要件や活用方法・補助額まで徹底解説!
事業再構築補助金は要件を満たせば、中小企業や中堅企業に補助金を支給する制度です。中にはM&Aを実施するときに制度を利用する企業も存在します。この記事ではM&Aを実施しても事業再構...

DDSとは?DESとの違いや手順・活用方法・メリット・デメリットまで解説!
企業再建手法の1つとして注目されているDDS。そんなDDSとよく似た言葉にDESがありますが、それぞれの違いは何なのかを本記事で解説していきます。またDDSを実施する手順や活用方法、メリットやデ...

CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)とは?メリット・デメリットを解説!
ベンチャー企業へ投資をするCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)。VC(ベンチャーキャピタル)と混同されがちなCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)とは何なのか、活用するメリット・デメリ...

エンジェル投資家について徹底解説!メリットやデメリット・探し方は?
企業がイグジット(上場、ハイバリエーションでの売却)をした際のキャピタルゲインを目的とした投資を行うエンジェル投資家。返済義務がない投資をメインとしているエンジェル投資家について知らない人も多い...

シード期とは?定義やスタートアップの資金調達方法・成功のポイントを解説!
成長していく過程においてIPOやM&Aを活用することも重要ですが、具体的にどのようなポイントを抑えれば良いのでしょうか。 この記事では、シード期の定義やスタートアップの資金調達方法・成...

M&Aにおけるエスクローの意味とは?メリット・デメリットについて紹介!
日本のM&Aでは、活用されているケースは少ないとされている仲介サービス「エスクロー」があります。海外では多く活用されていますが、この「エスクロー」とはどういう意味なのでしょうか。ここでは...

投資銀行のM&Aにおける役割とは?部門ごとの業務内容や違いを解説!
投資銀行は銀行の一種ではないと聞くと、驚かれる方が多いかもしれません。投資銀行は、銀行業ではなく証券業に分類されます。本記事では、投資銀行の概要、投資銀行がM&Aにおける役割、投資銀行の4大業務...

スケールメリットが経営に与える効果は?意味や仕組みを具体例に徹底解説!
スケールメリットとは、同種の業種やサービスが多く集まることで単体よりも大きな成果を生み出せることです。会社経営を行う際、不必要な経費を活用しているケースが多いです。このような課題を解決できるスケ...

株式分割とは何?仕組みやメリット・デメリットなどをわかりやすく解説!
株式分割とは、1株をいくつかに分割して、発行済みの株式枚数を増やすことです。株式分割には企業側、投資家側にメリット・デメリットが存在します。理解していないとトラブルに発展する可能性があります。そ...
























立命館大学卒業後、地方銀行にて中堅中小企業を担当。ファイナンス、ビジネスマッチング等に従事した後、本部専門部署にて事業承継支援を専門として実績を積む。
その後、大手M&A仲介会社において、事業承継や戦略的な成長を目的としたM&Aを業種・規模問わず、多数成約に導く。
M&A総合研究所では、製造業や建設業、不動産業など幅広い業種を担当。